
ノヴァーリス (1772-1801) の墓
今回の夜稿百話はノヴァーリスを取り上げている。前回 part1 は前々回のヤコブ・ベーメとの繋りからヘルメス学や新プラトン主義、パラケルススやベーメの自然神秘主義、厳格なプロテスタントの敬虔主義などの繋がりを見て来た。今回は、中井章子さんの指摘する化学的音響学、ツヴェタン・トドロフの初期ロマン派の象徴、ジョン・ノイバウアーの『アルス・コンビナトリア』、ルネ・ホッケのいう「言葉の錬金術」などを取り混ぜてノヴァーリスの別の姿に迫りたい。
『ザイスの弟子たち』
「人はさまざまな道を歩む。その道をそれぞれ辿り、比べ合わせてみるならば、数多の不思議な形象(もの)が立ち現れてくるのに気付くだろう。こうした形象は、鳥の翼や卵の殻に、雲や雪や結晶、岩の紋様、凍った水面、山や草木や禽獣や人間の内面と外面に、天空の日月星辰に、あるいは瀝青板と玻璃板を擦り合わせたときや、磁石のまわりに蝟集する鉄粉や、偶然がもたらす数奇な廻り合わせの中などの至るところに見出せるあの偉大な暗号文字の一つであるようだ。こうした形象の中に、この秘密文字を解読する鍵が、そして、そのための言葉の手引きが予感されるのだが、しかし、この予感はいっかな確たる形をとろうとはせず、それ以上たしかな鍵になろうとはしないようである。人間の感覚の上には、一種の万物溶解液(アルカヘスト)がふりかけられているらしい。一瞬、願望と思念は一つところに凝集するかに見える。そして、さまざまの予感が湧く。だが、それも束の間、一切はふたたび朧にかき消えていってしまう。」(今泉文子 訳)
上に掲載した文章は『ザイスの弟子たち』の冒頭である。舞台はエジプトのザイスにある聖堂だった。引用にあるように甲殻類や植物や動物の形、雲の形や結晶、あるいは薄板上にまいた粒子を音で振動させて出来る波形(クラドニ図形のこと)などをノヴァーリスはフィギュアと呼んでいる。これら結晶や音の波形、動植物の形態は、内に働く力や運動の表れである。それらは電気、磁気、音(振動)によって生じるとされた。例えば、結晶とは彼にとって凍れる音楽だった。
「色が屈折させられた(gebrochen)光であると同じ意味で、音とはさえぎられた(gebrochen)運動にほかならいと思われる。色は、物質と光の平衡(ニュートラル)状態のようなもので――物質の光になろうとする努力――またその反対の、光が物質になろうとする努力だ。すべての性質は、このような意味で、さえぎられた状態ではないか?‥‥(『断章と研究』43 中井章子 訳)」とノヴァーリスは述べている。
化学的音響学
結晶などの形は運動がなんらかの妨げにぶつかり、中断されることによって生ずるというイメージないし「思考の型」が彼にはある。何らかの力、運動がある抵抗にあって形態化するといっていいだろう。その力、運動は当時の先端科学だった電気や磁気などに関連付けられた。それらをノヴァーリスは音あるいはその延長としての音楽というイメージで捉えているようなところがある。こう述べている。「自然学。結晶から人間に至るまで、あらゆる具象的形成物(plastische Biludung)は 、音響学的に、遮られた運動によって説明されるべきではないか。化学的音響学(chemische Akustik)(『断章と研究』376 中井章子 訳)。」
当然、音楽の音も、遮られた運動だった。さらに、絵画、彫刻は、音楽の形象化(Figuristik)に他ならなかったし、あらゆる病気は音楽的問題であり、治療は音楽的解決である。音楽的自然学もある。中心は協和音、その(森羅万象の)円周も協和音である。すべてのものは、音響的に刻印され、シルエット化し、暗号化するよう強いるべきであるとノヴァーリスは考えていた。『青い花』の第二章のメールヒェンでは楽器を演奏することによって星や動物たちに共感をひきおこした音楽詩人が登場し、第三章のアトランティスのメルへンではリュートの音楽が歌とともに重要な部分をしめる。ゲーテが極めて視覚的な人であったのにたいして、ノヴァーリスは極めて聴覚的な人であった。
ノヴァーリスの音楽論は、さかのぼってルネサンスを経て、ピュタゴラスの西洋古代の音楽論につながる。ピュタゴラス同様に音楽は数学と密接に関わっていた。ノヴァーリスは、このように述べている。「音楽的数学。音楽には結合解析学(Combinatorische Analysis)に通ずるところがあり、逆に結合解析学も音楽に通ずるものを含んでいるのではないか。数の調和 ―― 数の音響学は ―― 結合解析学に属している。[‥‥‥]結合解析学は、数の幻想曲(ファンタジー)につながり ―― 数の作曲術 ―― すなわち数学的通奏低音を教える。(ピュタゴラス。ライプニッツ。)(『断章と研究』547 中井章子 訳)」


左 キルヒャー『普遍的音楽芸術』1650 「世界創造のオルガン」
右 メッローゾ・ダ・フォルリ リュートを弾く『天使』 1480
このようにノヴァーリスの中では、物理や化学における力やエネルギーといったものは音と数学に密接に関連するものとイメージされていた。それには、古代ギリシア以来の不可思議な存在・力にたいする認識があったからである。それはエーテル(アイテール)と呼ばれる。彼はこう書いている。「私たちの内にはある能力があって、これは私たちの外なる大空 ―― エーテル ―― かの不可視に見える物質 ―― 至る所に存在し且つ何処にも存在せず、全てであると同時に何物でもない、賢者の石と同じ役割をはたしているのではないか ―― 私たちはそれを本能ないし天才と呼ぶ ―― それは至る所で先験的にある。それは、未来の充溢 ―― 時の充溢そのものであって ―― 時間の中で、空間における賢者の石に相当する‥‥ (『断章と研究』1036 中井章子 訳)」
あるいは、こう言い換える。「万有の創造的形成力[想像力]。」ベーメはこの「大空(=エーテル)を神が無から万物を造った時[無](『神智学の六つの要点』)」と述べ、「時と永遠のつなぎ目(『大いなる神秘』)」と呼んだ。
ドレスデンとロマン主義絵画の象徴

ドレスデン エルベ川と聖母教会
23歳のオットー・ルンゲ(1777-1810)がコペンハーゲンから、ドレスデンにやって来たのは1801年のことだった。彼の古典主義的な作品が、ワイマールに受け入れられなかったことや親友となった詩人ティークとの出会いによって新たな芸術への指向が高まっていた。「真性の感情」を持つにふさわしいテーマを選ぼうとし、全てがこれまでより軽やかになったが、それをどう始めてよいかわからないと漏らしている。しかし、1803年頃から1810年にかけての『一日の四つの時』あたりからロマン主義的と言える作風に変化し始めた。
この頃、詩人ティークからヤコブ・ベーメのことを教えられた。それは「神の手跡」としての自然、その象形文字としての花であったが、当時においても解説の必要なものだったと言われる。ゲーテはこれを「ほの暗い関係の迷路」と呼んだと言う (H.J.ナイトハルト『ドイツ・ロマン主義絵画』) 。1803年にドレスデンからハンブルクに移った後、彼に残された時間は7年だった。


オットー・ルンゲ 左『朝』 右 部分
「ロマン派設立の年」といわれる1798年秋、もう一人の若者がコペンハーゲンのアカデミーから新たな刺激を求めてドレスデンにやって来ていた。カスパー・ダヴィツド・フリードリヒ(1774-1840)である。彼は、ティークを中心としたドレスデンのロマン派の文人たちやルンゲの影響を受けるようになる。ルンゲとは対照的に彼の作品はワイマールに受け入れられ、1810年にはゲーテが彼をドレスデンに訪ねている。ゲーテはロマン主義には批判的だったが、フリードリヒの考え抜かれた主題に対して敬意をはらったという。やがて、彼の作品は、ナポレオンとの戦争に敗れたドイツへの憂国と愛国に彩られることになる。
その作品は17・18世紀の理想的自然の描写であって、極めて忠実な自然描写と精緻な観察眼を持っていたが、感覚的なものの中に超感覚的なものの啓示を見、そこに象徴としての「運命の形象」を表現しようとしていた (H.J.ナイトハルト『ドイツ・ロマン主義絵画』) 。

カスパー・ダヴィッド・フリードリヒ
『楢/樫の森の中の修道院』 1809-10
ゲーテは、象徴を生産的であり、自動詞的であり、有縁化であり、反対物の融合にまで達し、その内容は理性では捉えられず、言語に絶するものだと述べた。彼の言う象徴は、ロマン派が標榜した価値一式に当てはまっていたとフランスで活躍した哲学者・文芸批評家であるツヴェタン・トドロフは指摘する。確かに、ゲーテは一部ロマン派だという指摘も頷ける。A.W.シュレーゲルは、「美は無限の象徴的な表象である」とし、その中には崇高美も含まれるとしている。ロマン主義美学を一語に圧縮するとすればシュレーゲルの言うこの「象徴」という一語であるとトドロフは述べている (ツヴェタン・トドロフ『象徴の理論』) 。
このトドロフの言う象徴は、平凡なものと高貴なもの、有限と無限、ありふれたものと神秘なもの、既知と未知、此岸と彼岸、物と精神とを結びつけようとする「ロマン化」であった。それは、象徴の持つ動的機能とアルス・コンビナトリア (結合術) とに深く関わっていた。
近代科学の波と神学的自然学
1800年前後に自然神秘思想の再生によって自然観に革命をもたらそうとしていたのはノヴァーリスだけではなかった。特にゲーテの自然学は高く評価されていて、「来るべき自然学」の最初の実例となった人である。ノヴァーリスは、ゲーテを稀なる正確さをもって抽象するが、その際かならず、その抽象化が対応している対象をイメージに変える人だという。理論だけでなく、それをいかに述べるかも同時に重要だと考えていた。自然科学を詩的に、象徴的に捉え、神学的自然学にまで高めなければ本当の自然学が生まれないと考える。
ゲーテの延長線上にノヴァーリスはいた。ノヴァーリスやゲーテの時代は、科学的進展の足音がそれ以前よりも早まっている。電気、磁気、化学反応、生物電気など多様な領域に新たな発見がもたらされていた。大量の電気を蓄電できるライデン瓶が1745年ライデン大学でミュッセンブルークによって発明される。電気と磁気の関係の解明は1800年代前半にエルステッドが電流によって方位磁針が影響を受けることを発見したのが始まりだった。ノヴァーリスはフライベルクの鉱山学校で鉱山学の他、化学、数学などを学んでいるが、当時、最先端の専門教育機関だったと言われる。

ライデン瓶 テイラース博物館 オランダ
以前の博物学的なアプローチに対して、ノヴァーリスの時代には19世紀的な自然科学、様々な力を対象とする物理や化学を視野に入れなければならなかった。それらが自然を一つに繋げている力の表れだと考えれば、その延長にガイスト(精神=霊)との繋がりを考えることはノヴァーリスにとっては、そんなに難しいことではなかったのであろう。新たな自然学は、かつての神秘学が標榜していた「世界の意味」を回復しなければならない。それは「目に見えるもの」と「目に見えないもの」との間、つまり「中間地帯」を対象とし、それらが相互に変換するプロセスを追及するものだと言う (中井章子『ノヴァーリスと自然神秘思想』) 。
ゲーテの自然科学は、人間の感覚を締め出そうとする近代科学とは別の枠組みと言ってよかったが、あえて科学という枠から踏み出そうとはしなかった。ノヴァーリスは、そこを踏み越え、表だって霊的な領域との接点を見出そうとした。天文学は道徳的になるべきであるし、物理学は象徴的に取り扱うべきである。自然科学は森羅万象の宗教、あるいはポエジーになるべしと考えたのである。
象徴
ノヴァーリスにとって、かつての「しるし」=シグナトゥールは解読コードのない「暗号」になってしまっていた。水晶や雪の美しい結晶は、この世を超えた世界を指し示していたのにである (中井章子『ノヴァーリスと自然神秘思想』) 。だが、彼は、なおも言葉と自然の間にある繋がりを象徴 (シンボル) によって表現しようとする。存在が全て神を指し示す象徴 (シンボル) であった中世の時代は終わり、詩人は芸術家として新たな象徴 (シンボル) を創造していかなければならない時代になっていた。それを記号として考える時も、あくまで「象徴」として捉えているという。
中井さんは、ノヴァーリスが象徴 (シンボル) とアレゴリーを厳密に分けて使っておらずアレゴリーの方を多く用いていると言う。だが、18世紀の啓蒙主義にみられる論理的で修辞的なアレゴリーに戻るつもりはなかった。それは、別の言葉や概念、教訓などで言い換えられるような意味しか持たない。今や、アナロジー的なより広い意味を持つ象徴的表現を目指すようになる。それは言葉による「形象 (ビルド) 」、つまり「言葉による絵」であり、音楽のように特定の意味内容は持たないが超越的なものを指し示すものでなければならなかった。
ヴァルター・ベンヤミンはロマン派の天才のアレゴリーをこのように語る。「響きがよく、美辞麗句に富むばかりでなく、雑多な物からなる断片のように意味や脈絡は全く欠けている ―― せいぜいいくつかの詩節の意味がわかるにすぎない ―― ような詩。真の詩は、せいぜい全体として一つの寓意をもちうるにすぎず、また音楽のような間接的な効果を及ぼすに過ぎない。自然は純粋に詩的である、魔術師の部屋、自然学者の部屋、子供部屋、物置、貯蔵庫などもそうである」と述べ、そのような部屋の無秩序な堆積と寓意との類似は決して偶然ではないと続けて述べている (『ドイツ悲劇の根源』) 。さすがだ、これは決して詩の浅薄さを揶揄するものではない。この雑多性がアルス・コンビナトリアに繋がっていく。
ノヴァーリスのアレゴリーは、「生産的であり、自動詞的であり、有縁化であり、その内容は理性では捉えられず、言語に絶するもの」というゲーテの象徴にかなり近い。それが、反対物の融合を目指すロマン化へと導くのである。
ちなみにノヴァーリスが言祝いだバロックのアレゴリーを示すテクストの著者として、中井さんは次の三人を挙げている。医師にして気体=ガスを発見した科学者/錬金術師としてのヤン・ファン・ヘルモント (1579-1644) 、『化学の結婚』の著者ヨハン・ヴァレンティン・アンドレーエ (1586-1654) 、そしてヤコブ・ベーメ (1575-1624) である。

ヤン・ファン・ヘルモント像
ルイ・デラセンスリー 作 1889
アルス・コンビナトリア
ピュタゴラス以来、深奥の神秘は数の中にあった。ルクレティウスの字母結合術、ライムンドゥス・ルルスの「術」、ヤコブ・ベーメの自然言語、キルヒャーの「新普遍暗号術」、これらの発想には、数や記号、ある種の新言語によって奇蹟は発見可能だという信念がその基盤にあった。それは、森羅万象を統一的に整理する百科全書からソフトウェアへの夢へと発展していく。
ジョン・ノイバウアーは、近代結合術の祖ライプニッツから「書くことは常に計算を組み立てる感覚を伴う」と言ったヴァレリーとの間に初期ドイツ・ロマン派を置くことができると述べている (『アルス・コンビナトリア 象徴主義と記号論理学』) 。とりわけ、ノヴァーリスにおいてライプニッツの思想的遺産が範例的に受容され、ここに数学理論の詩学への変容が見られると言うのである。窓はないが全てを映し出すライプニッツのモナド論が新プラトン主義の流出説との関係を断ち切れていないというノイバウアーの呟きが面白い。
概念を一定数に限られた数の根本概念に解体して、記号化し、参照できる諸ジャンルに展開された百科全書を作ることは、ノヴァーリスにとって小説のための基本的素材を集めカタログにすること、そして対話体を文章の中に溢れさせることだった。そして、その記号を結合することは小説や詩をあたかも音楽化し、作品の中で修辞学的形式のシステマティックな探究に加えて作品の反省をも作品の中に入れてしまおうとすることだとノイバウアーは見ている。
ノヴァーリスは小説構想のための長大なカタログを作っていた。洞窟、海、玉座、旅、小屋など人間が置かれる34の状況リスト、滑稽、愚鈍、詩人、陰謀好き、賢明などの人間の40のタイプ、名誉心、復讐、宗教、強制、憎しみ、誇りなどと結合した34の愛のタイプなどの結合の可能性を一望のもとに収めようとする。それは、数多くの精神と諸人物といった全てのシステムを所有し、その内部に宇宙を、いわばモナドの一つひとつに反映させ、それを育て熟させようとする意図があった。諸ジャンルの百科全書を小説の枠内で実現しようとすれば、それは当然ながら表現の類型化、図式化を必要とする。ジャンルは、「エッセイ、報告書、証明書、論文、書評、モノローグ、対話の断片‥‥」などが手本にされた。初期ロマン派にとって百科全書の遺産は「無限の充溢」であったと言うのである。
数学と記号論に興味を持ったノヴァーリスは、1798年の後半にはフライベルクの鉱山アカデミーで、この方面の研究に没頭していた。この頃の『一般草稿』と呼ばれる備忘録は百科全書の準備作業として考えられていたようだ。
記号が重要なのは、現実にある理論を知覚可能な明晰な表象として記号に置き換えられるような場合であり、私たちが現実的な感覚によって解明できるとは限らない概念にとって、いずれにせよ必要であるとノヴァーリスは述べる (『記号学』) 。ノヴァーリスの多様な断章や小説構想のためのカタログにあるものは、全てを繋げて新たな展望へと導くためのカオティックな坩堝であり、この記号化のための準備作業だった。その中を覗く人間にとっては、都合の良いものを拾える魔法の壺であったかもしれないし、ノヴァーリスにたいする毀誉褒貶の理由もここらあたりにあるのかもしれないが、彼にとって、それは単に助走に過ぎなかった。
彼が目指したのは、あらゆる学問が一つの書物を作り上げることであり、この唯一の書物には「普遍宇宙の鍵」が見つからなければならなかったのである。


左 フライベルク、鉱物学研究所
右 フライベルク鉱山技術大学 機械・プロセス開発技術センター
言葉の錬金術
グスタフ・ルネ・ホッケは、ヨーロッパ的人間の特殊な精神史を扱うと言挙げした『文学におけるマニエリスム』の中で、この問題を扱うためのアリアドネの糸はノヴァーリスだと断言する。この本は、古代のファンタジアからローマ末期や中世末期の文学、シェークスピア、ハルスデルファー、シュレジア詩人派から初期ロマン派、1880年から今日に至る「反古典的」、「反田園詩的」抒情詩にまつわる全マニエリスムの確認の書といってよい。それを解く鍵はノヴァーリスにある。
17世紀ドイツにおいて、詩作は古典的な詩法とは異なる言葉の組み合わせによる美的活動となった。「力は無限なる母音、素材は子音 (ノヴァーリス) 」なら、意識的な文字と音響の組み合わせの操作によって「作る」詩作となっていった。曖昧、驚異的、謎めいたもの、不意打ち、新奇なもの、あらゆるものが反対物に反転・交換される。錯綜するものの探求。そして語の破砕。例えば、〈Onix〉縞瑪瑙という語から〈Oh, Nix/おお、雪よ〉が生まれ、ついで〈Oh, nix flamma mea/おお、雪よ、わが焔よ〉が出来し、〈雪〉=〈焔〉となり相反するものが語の結合によって生まれる。一つの穏喩が無数の隠喩を生むのである。この生成は驚異となる。アンドレ・ブルトンの言うように「驚異は美しい」のである。
17世紀のドイツ詩人たちは〈言葉の工房〉で〈音が描く秘文字〉を制作していた。知的遊戯と神聖な神秘主義の混淆は一丸となってグノーシス‐カバラ的思索世界へと花開いたとホッケは言う。このあたりの時代背景は、part1 やヤコブ・ベーメでご紹介しておいた。そこからロマン派の青い花が咲き、象徴主義が花開く。ランボーは「言葉の錬金術」を標榜し、マラルメは〈文字の魔術師〉たらんとした。こうして詩人はカオスに満たされたバベルの塔の住人となるのか‥‥ここでもホッケはノヴァーリスの言葉を引く。「詩人は事物や言葉をあたかも音鍵のように使う、文学全体が活動的観念連合、すなわち自律的な、意図的、理想主義的な偶然の産物である(種村季弘 訳)。」「意図的な偶然の産物」とは、〈絶対的偶然〉であり、隠された秩序の寓意画としての〈人工の反-秩序〉である。そう、ホッケは、こう締めくくる〈迷宮の神秘 ! 〉。
再びロマン化
ノヴァーリスにとって最後は全て「ポエジー」となる。自然の創造的形成力は詩人のそれと連動しなければならない、それによってこそ、あらゆるものは照応関係を再び取り戻し、理性による言葉の結合によって「世界は最後に心情になる」。こうして、世界のロマン化は達成しうるのである。全体を眺めてみると、何故、ノヴァーリスが、かくも重要で、同時にかくも危険であるのかが理解できる。そうなら、彼が28歳の若さで早世したことは如何にも惜しい。それを思う時、この言葉は深い感動を呼び起こすのである。
「友よ、大地は貧しい。ほんのわずかな収穫を得んがためにも、われわれはたくさんの種子を蒔かねばならぬ。(『花粉』)」

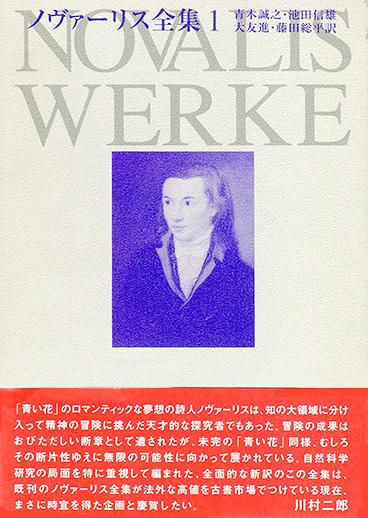
人生で経験する偶然はすべての材料であり、われわれはそれをもとにのぞみのものを作り出すことができる。精神の豊かな人は、人生から多くのものをつくりだす ―― 徹底的に精神的な人には、あらゆる出会い、あらゆる出来事が ―― 無限級数の第一項 ―― 無限に続く小説の発端となるだろう。
(「さまざまな覚書1797-98年」青木誠之 他 訳)

詩学
「厳密な意味での詩学は、造形芸術と音響芸術のほぼ中間に位置する芸術であるように思われる。(音楽。詩。描写詩。)拍子は形に――音色は色彩に対応するのではなかろうか。律動的な音楽と旋律的な音楽――彫刻と絵画。詩のさまざまな要素。
(『一般草稿』1798-99 47 青木誠之他 訳)より

『ザイスの弟子たち』には、「ヒヤシンスとバラのメルヘン」が挿入されている。ノヴァーリスのメルヘンはゲーテのそれに感化されたらしい。こんな話になっている。
遥か西方の比の沈む国にヒヤシンスという美少年がいた。樹や石に話しかけるもちゃんとした言葉でなかったために動物たちはそれを直してやろう気を揉んだが、少年は相変わらず気難しく深刻だった。彼は人形のように愛らしいバラという名の少女と相思相愛だった。隣同士の二人が窓辺に立っていると庭の草やトカゲたちが二人の愛を囃し立てた。
かわいい娘のバラちゃんは
突然めくらになりました
かあさまとヒヤシンスを間違えて
首に激しくしがみつき―
知らない顔だと気が付いたのに
どうでしょう、少しも騒がず驚かず
何も聞こえぬふりをして
ずっとキスしたままでした
(今泉文子 訳)
ある一人の異邦の老人がやって来ると、ヒヤシンスは好奇にかられて彼と話し込むようになり、老人は彼を伴って深い洞窟に降りて行った。そして、老人はヒヤシンスに誰にも読むことのできない小さな本を残していった。その時以来、彼はバラのことを省みないようになった。森の中でふしぎな老婆と出合い、健康になるようにとその本は燃やされてしまい、両親を祝福するようにと諭される。彼は、両親によその国に旅立つと言うと神秘の国を目指して急いだ。バラは部屋に閉じこもってさんざん泣くのである。聖なる女神イシスを訪ねる道のりは過酷な荒地や炎のような砂漠だったが、やがて空は暖かく、道は平坦になり、緑なす大地に変わった。彼は尚も尋ね尋ねて探し求めた神殿にたどり着いた。そこに足を踏み入れると甘やかな芳香に包まれ、微睡んで夢を見た。彼は天なる乙女の前に立っている。その軽やかなベールを掲げると、彼の胸にバラが身を投げて来た。はるか彼方から響いてくる音楽が、憧れの心に満たされた二人を包み込んだ‥‥

『花粉 16』
想像力は、死後の世界を天上に描くか、奈落に沈めるか、あるいは輪廻という形で地上にもたらす。宇宙遍歴の夢を見たりもするが、宇宙は我々の内部にあるのかもしれない。我々は精神の奥底を知らないが、内部へと神秘な道は通じている。永遠とその世界、過去と未来は、我々の内部にあるのでなければ、どこにあるだろう。外界は影の世界に過ぎない。我々の内部は暗く、寂幕としておぼろげだが、暗闇が過ぎ、影の物象が消え去ると、われわれの味わう喜びは以前の比ではない。これまで精神は、不自由を忍んできたのだから。

中井章子『ノヴァーリスと自然神秘思想』
本書の章立ては part1 にご紹介しておいた。ノヴァーリスの解説書としては、まず本書をお勧めしたい。

今泉文子『鏡の中のロマン主義』
ハイネはノヴァーリスを肺病やみの詩人と揶揄し、文学史家のブランデスは空想力の子と決めつけてロマン主義さえ感情や気分とか民族的伝統にのみ依拠する文学とアゲツラッたという。これに対してドイツ語圏ではホフマンスタールやムジール、ヘルマン・ブロッホ、ゴットフリート・ベンらが、あるいは、フランスでもネルヴァルやメーテルリンクらがノヴァーリスから影響を受けたという。ヘッセは、彼を物質文明の中の魂の救済者としているし、ト―マス・マンはノヴァーリスの現代性を指摘し民主主義の守護者と位置付けた。しかし、ナチズムの思想圏に取り込まれたことさえあるという。ルカーチは「ドイツ文学史の最もアクチュアルな任務はロマン主義批判である」としている。ノヴァーリスの研究者である今泉文子さんは『鏡の中のロマン主義』のなかで、この詩人への評価は、揺れ動く精神史を忠実に反映していて、時代や受け手の要請に奇妙に従ってきたと指摘している。
ノヴァーリスの遠心力を扱った本。

H.J.ナイトハルト『ドイツ・ロマン主義絵画』
ドイツ・ロマン主義絵画を扱う図書は意外に少ない。本書は、ルンゲやフリードリヒだけでなく、その周辺にあった画家たち、カール・グスタフ・カールス、ゲオルク・フリードリヒ・ケルスティング、ルートヴィッヒ・リヒターらが紹介されている。日本には馴染みのない作家たちと言ってよいと思う。

ジョン・ノイバウアー『アルス・コンビナトリア 象徴主義と記号論理学』
ライプニッツの思想にノヴァーリスが触れたのは医学史や思弁哲学の書物からだった。例えば、哲学史家のディートリヒ・ティーデマン (1745-1803) のこのような記述からである。『(ライプニッツの)これらの研究をうかがうに、彼の火のような、つまりいまだ冷静な理性によって充分に手綱を引き絞られていない想像力が、熱狂・エクスタシー・霊魂との交信といった知らぬまに忍び込む甘やかな毒素によって、汚染されてしまったように思われる。‥‥どう見ても流出論への彼の傾きもここに発しているのであって、最後期の思想すらなお、入念にシステムの被いがなされているにもかかわらず、この傾向が漏れでるときがある。これにはもしかすると、かの熱狂的なピュタゴラス派の数秘術信奉者ヴァイゲルもまた多々貢献していたのではないか。‥‥カバラの体系をライプニッツは、折々の発言からして、少なくとも大変正確に知っていたし、彼に近い神秘主義たちすら、そしてヤコブ・ベーメも彼の眼を逃れはしなかった (原研二 訳) 。』
新しい小説は「大量の会話」で満たされ、修辞学的話法の一種の便覧を生み出すように意図される。ロマン派の散文は高度にめまぐるしく、驚異的で異様な展開を、劇的で激しい飛躍を見せる。時に脈絡を失う。それは「喜劇的なものと最上のポエジーとの結婚」であり、「粗野で下卑たものと、高貴なもの、高みにあるもの、詩的なものとの混合」である。小説は、結合術と百科全書の構成原理をぎりぎりまで拡大することによって生まれるとノイバウアーは言う。

グスタフ・ルネ・ホッケ『文学におけるマニエリスム 言語錬金術ならびに秘教的組み合わせ術』
『迷宮としての世界』も名著でしたが、本書も素晴らしい著作です。
グスタフ・ルネ・ホッケ (1908-1985) はドイツ人の商人ヨーゼフ・ホッケとフランス系ベルギー宮廷画家ギュスターブ・ド・ネーヴの娘との間に生まれた。父方の祖先はドイツ系ボヘミアの出自を持つ。ベルリン大学で学んだ後、ボン大学でエルンスト・ローベルト・クルチウスのもとで学び、哲学博士号を取得した。卒業後、ケルン新聞で日曜版にある「現代の精神」を編集するようになる。
イギリス旅行を契機にシェークスピア、ジェイムス・ジョイス、T.S.エリオットの世界に惹かれる。1937年のイタリア旅行でエレア派とピュタゴラス派に興味を持ち、イタリアとギリシア文化研究に舵をきった。1940年からケルン新聞の通信員としてローマに派遣され、小説『踊る神』を執筆する。1949年にはドイツの新聞雑誌のドイツ・イタリア通信員となり、作家・ジャーナリストとして活動する。1950年からドイツ学士院言語文学部門の会員である (本書「著者紹介」より) 。邦訳のある著書として『迷宮としての世界』、『絶望と確信』『ヨーロッパの日記』がある。

ルートヴィッヒ・ティーク(1773-1853)
1797年頃、ティークはシュレーゲルと出合って1799-1800年はイェーナに滞在し、シュレーゲル兄弟、ブレンターノ、フィヒテ、シェリングらと交友し、ゲーテ、シラー、ノヴァーリスらとも会っている。ドイツ・ロマン主義を代表する詩人、作家の一人となっている。
H.J.ナイトハルト『ドイツ・ロマン主義絵画』から

オットー・ルンゲ『一日の四つの時』「夜」 1807
ティークの影響を受けて制作されたドレスデン時代のルンゲの作品。二人はたちまち友人となったといわれる。彼の意図は「総合的芸術作品」を創造することであり、音楽的、象徴的詩文として解されることを望んでいたという。『一日の四つの時』の「朝」とこの「夜」には音楽を奏する子供が描かれている。詩と絵画と音楽とがひとつになるというロマン的イデーだった。

カスパー・ダヴッド・フリードリッヒ
山上の十字架 (テッシェン祭壇画) 1808
ゴシック尖頭様式のロマン的変容を示す作品であり、ドレスデンの美術界に激しい拒絶と熱烈な賞賛をもたらしたと言われる。神の象徴である沈みゆく太陽は旧約の過ぎ去った世界を示し、その光は十字架上のキリストを照らし、暗い地上に反射する。岩は強固な信仰を、ゲルマン民族を象徴する緑のモミはキリストへの希望を示していると言われる。

カスパー・ダヴッド・フリードリッヒ
『海辺の修道僧』 1808-1810
『楢/樫の森の中の修道院』と対として制作された作品。当時の人々に多大な影響を与えることとなる。プッサンやクロード・ロランのように光景から前景へと層状に広がる舞台のような空間を否定している。ゲルマン精神を鼓舞する『ヘルマンの戦い』を書いた劇作家のハインリッヒ・フォン・クライストは、この単調で果てしない画面の前景には額縁しかない、この絵を眺める者は、あたかも瞼を切りとられるかのようだと述べたと言う。

カスパー・ダヴィッド・フリードリヒ『リューゲン島の白亜岩』 1818-1819
1806年のリューゲン島への旅行を契機に描かれた明るい作品だが、フリードリヒと妻のカロリーネ、弟のクリスチャンが描かれている。島の北端を訪れた楽しみに満ちた思い出であるが、枯れた灌木や険しい断崖を見る時、フリードリヒのこの言葉が思い出されるという。「画家は目に見えるものを描かねばならない。彼の内面に何も見えない時には、彼は眼前にあるものを描くのをやめなければならない」。



コメント