
今道友信(1922-2012)『ダンテ 神曲 講義』
クラシックって古典のことだろう、と当たり前に思っていたのですが、恥ずかしながらその語源について知ったのは、本書を通じてでした。クラシックとはラテン語の classis= 艦隊を意味する名詞から派生した形容詞であると言う。ラテン語辞典で調べるとなるほど海軍となっている。それはローマの国家的危機に際して一艘とかではなく、艦隊を寄付できるような国家に寄与できる富裕層を指した。古代ローマでは徴兵制はあったが、軍艦は税金ではなく寄付を募って造ったと言う。この国家の危機に自分の子供= proles しか差し出せないような貧しい層の人をプローレータリウスと言った。そこから貧困な労働階級を意味するドイツ語プロレタリアートが生まれたのである。この意外な展開に吃驚仰天したのは言うまでもない。転じて人間の心の危機において本当に精神に力を与えてくれるような書物、絵画、音楽、演劇などの偉大な芸術をクラシクスと呼ぶようになったというのである。これは古典と訳されたが、典は猫脚の机の上に巻物を大切に置く象形文字で、大切にして読むという意味です。けっして積読の意味ではありません。
ダンテの古典に学ぶというわけで今道さんの『ダンテ「神曲」講義』に拠りながら神曲の各歌を要約してご紹介している。今回はその最終回、「天国篇」をご紹介します。ダンテ研究はフマニスムス、つまり人文主義を学ぶことである。この言葉は1809年にフリードリヒ・ニータンマ―という人によって人間愛=フィラントロピスムスに対して作られたドイツ語である。それは古典研究を介して言語に習熟すること、言語に馴染み生きるということであった。ダンテの直後にイタリアでウマニスタと呼ばれる古典研究を中心とした人文主義のグループが現われる。その人々の運動こそが19世紀以来のヒューマニズムを先駆けるものであった。
筆者 今道友信さん
今道さんは1922年東京生まれ。父親は支店長も務める銀行員で、転勤もあり、山形、高知と転校した。いずれも当時は方言がきつく、それで英語が好きになったと冗談めかしておっしゃっている。1948年に東京大学文学部哲学科に入学、出隆(いで たかし)に学んだ。パリ大学やヴュルツブルク大学で非常勤講師を勤め、1958年から九州大学や東京大学などで教鞭を執るようになる。国際美学会副会長、東京大学名誉教授であられた。1982年に哲学美学比較国際センターを創設され、2010年まで所長をされる。2012年に89歳で亡くなっている。エコエティカ(生命倫理に基づく人間学、倫理学)を提唱した美学・哲学者として知られる。簡単ではあるが今道さんの経歴をご紹介した。
天国篇
煉獄篇では地獄篇と異なり、悲惨や絶望への哀訴はなく、教理の理解や政治論などを踏まえながら巡礼叙事詩の形をとって天国への接近が図られる。ダンテは、ここで前著の『帝政論』の行き過ぎを訂正しているという。改宗者スタティウスやベアトリーチェとの関係を想像させる女性マテルダらが加わり秘儀めいた雰囲気が演出され、ウェルギリウスが表舞台から退くと、聖体拝領を境とする信者のみが正式参加を許されるようなミサの雰囲気を醸し出しはじめる。宗教的な色彩を濃くするのだ。浄罪救済の叙事詩としての性格を煉獄篇は持っていた。これに対して天国篇は天国の至福の叙事詩とならなければならない。それは宗教的宇宙論と言ってもよく、極めて教導的である。そんなものは、たいてい詰らないものだというが、この神曲は面白い。何故だろうか。さて、天国篇に入ろう。
地上楽園から天界への上昇 第一歌から九歌

ジョヴァンニ・セルカンビ(1348-1424)画
ダンテ神曲より火星天の登場人物、15世紀
地上楽園から月光天、水星天、火星天へと上昇していく。
冒頭ダンテは予言の神アポロンに呼びかける。地獄篇でも煉獄篇でも冒頭に呼びかける対象は詩の神々ミューズであった。それはホメロスの「憤りを歌いたまえ詩のミューズよ」に始まり、ヴェルギリウスによって「ミューズの女神よ、私に事の由を思い起こさせたまえ」と受け継がれた伝統と言って良い。ここでダンテは「願わくは我を汝の徳の器とし」「汝の愛する桂(アルローロ)を受くるにふさわしき者たらしめよ」と願っている。ミューズは過去を歌う女神である。パウロが行ったとされる天国は、それ以外誰も行ったことがない。アポロンの予言力を借りなければ、とうてい表現不可能だというのである。(一歌)
ダンテはベアトリーチェと共に地上楽園から月光天へと上昇している。太陽さえ凝視できる力を備えるようになった。ベアトリーチェは、こう説明する。創造物には神が刻印したそれぞれの価値がある。その定めによりその根源に向けて傾斜していく。それが本能であり、火は月へ動き、下等生物には機動力となり、大地には凝固させる力となる。私たちは神の摂理の光によって原初動が全速回転する、しかも極めて静かな至高点へと向かっているのだと語る。
天国篇は難解であるから私を見失い、途方に暮れるかもしれないと小さな舟でついて来る人たち、つまり読者に警告が発せられる。話は哲学・科学・神学へと傾斜していくのだ。矢のような速さで月光天に着いた。ダンテはあの月の斑点を問い、彼女はそれに科学的に答える。そして、至高天は回転する力の中に全ての実在を持っていて、第八天である恒星天は、実在のそれぞれの本質に分かれている。七つの天球はそれぞれの性格に従って内部に各々の本質と種を持っていて、上の天の影響は下の天に伝えられる。様々な力が天体に応じて種々に結合し、天体を賦活する。それは魂の様々な能力が異なる五体に行き渡り生命が人間に結びつく仕方に似ているという。(二歌)

サンドロ・ボッティチェリ 『天国篇』 第二歌
「万物を動かすところの者」を神としたのはアリストテレスである(『形而上学』λ 巻)。形而上は易経にある言葉で形体あるものを越えて考えることを指している。それは神学でもある。今道さんは、アリストテレスの第一動者としての神の存在証明をトマス・アクィナスが受け継ぎ、その伝統がダンテにまで継承されているという。
月光天でダンテはフォレーゼ・ドナーティ(煉獄二十三、四歌)の妹、ピッカルダに会う。立てた誓願が軽んじられ、一部は破られたためにこの天界に割り当てられたという。しかし、何も望むこととはなく、神意のうちに留まっていることこそ幸福であると語る。そして、同じく尼となりながら還俗を余儀なくされた大王妃コンスタンツァを紹介する。(三歌)
プラトンの言う、死後に魂は星に帰るという疑問とピッカルダのように他人の暴力が何故自分の功徳を減らすのかという疑問にダンテは捉えられた。前者については自然が魂に肉体という形相を与えた時、魂がその星から別れたというプラトンの考えには一笑に付すことができない問題があるとベアトリーチェは答える。後者については、意志の弱さに起因することだという。(四歌)

ギュスタ―ヴ ・ドレ『天国篇』 第五歌
破られた誓願は他の善行によって償いうるものかという疑問にベアトリーチェが答える。天地創造に際して神が与えた最大の贈り物は意志の自由であった。誓願は意志の自由を犠牲にする。それ故高い価値を持っている。誓願の内容を勝手に変えることは出来ず、神との契約が果たされなければそれが取り消されることはないと語った。そして、二人は第二の天、水星天に駆け上がった。そこには、千余りの光明が近づいてきて、その中から声が聞こえた。(五歌)
皇帝ユスティニアヌスの魂が、鷲の旗の下にアエネアスから始まる代々のローマ皇帝の偉業を語る。そして、教皇党と皇帝党とがそれぞれの党利党略に走るのを嘆いた。生前、名誉のために善行を積んだ人々が集っているが、とりわけ、水星真珠天の光輝は、プロヴァンスの宰相ロミューであると語る。(六歌)
ダンテはベアトリーチェへの畏敬の念にかられ、「べ」とも「イーチェ」とも言えず眠りこむように頭を垂れるしかない。彼は、人間の贖罪に対する疑問に囚われる。生まれたことのない男性、つまりアダムの堕落以来、造物主から離反した人性はキリストという永遠の愛の働きによって再び神に結びつけられた。十字架によって課せられた罰はキリストが帯びていた人性を考えれば正当な罰であり、キリストの持つ神の位格にとっては、かつてなく不当な罰であった。一つの事から異なった結果が生じた。正義の復讐が、その後、正義の法廷によって報復を加えられたのだとベアトリーチェはいう。正義の復讐とはアダムの犯した罪がキリストの死によって贖われたことである。報復とはキリストの血を流させた民の都エルサレムを皇帝ティトゥスが破壊したことを指している。神が支配する世界で復讐は何故繰り返されるのか? こういったキリスト教的歴史観、歴史が神と救いの論理で解釈されるのはアウグスティヌスの『神国論』をもって始まる。ティトゥスについての解釈は、その弟子のオロシウスによると今道さんは述べている。(七歌)

ギュスタ―ヴ・ドレ『天国篇』 第八歌
第三の天、金星天へと二人は昇る。ダンテと旧知の間柄であったハンガリア王カルロ・マルテㇽロが喜悦の情によって一層輝いていた。自分が若死にしなければこれほど害悪が世に広がることはなかったろうと語る。そして甘い種から苦い実、つまり立派な親から不肖の子が生まれるのかを問うダンテに答えてやる。(八歌)
第九歌は地獄篇でも煉獄篇でもその門の内に入る場面に選ばれている。天国篇でも、ここから本当の天国に入っていくのだ。大地に立って手をかざすと、それが陽の光に投げかけられてできる影の先となる。同じように地球の影はこの金星天までのびて影の端を作る。そこから先は地球の影響は及ばない。真の天国となるのである。普通の人でも命がけで善行をなせばこの金星天までは行ける。そこから上は、聖人が登場するが、ダンテは自分の高祖父もこの天国に入れている。よほど家門の誉れだったのだろうか。ロマーノ家のクニッツァは多情ではあったが晩年改心して善行を積んだ。彼女はイタリア各地の惨状を語る。吟遊詩人であったフォルケは神の摂理を讃えて歓び笑う。そして、ヨシュアを助けた遊女ラハブがいた。たとえ、遊女であっても、たとえ、一度でも命がけで善行を行えば天国に迎えられるとダンテは考えていたのである。(九歌)
不可視のものが可視のものを統べる

プラトンの「線分の比」の教え 本書より
神が創ったものは滅びない。原質料がその一つである。それは背後にある。原質料から諸々の力により多くのものが形成された。形成されたものは滅びる。それは外に現われでる現象に過ぎない。質料と形相とは神によって作られた。何でも形成できるスーパー物質とその鋳型と言って良いのかもしれない。例えば、土は無から創られた原質料から土になる可能性を巡って運行する星の上に、神の内在せしめた形相に基づいて形成されると考える。
プラトンには外に現われ出る可視のものと、その背後にある不可視のものについて語られる「線分の比」という教えがある。ADは理性によってのみ把握しうる不可視の世界イデア=神の思い、DCは悟性によって把握できるエイドス(概念・法則)、ここまでが不可視の世界である。CEは、いささか現象学的に言えば経験世界における事物への確信の世界、BEは感覚によって得られる世界と言ってよいのではないかと思うけれど、プラトンの言う可視の世界である。この不可視のものが可視のものを統べるという考えは、アリストテレスを通じてトマス・アクィナスへと流れ込んだ。
火の花冠 神学者と聖人たちの天界 第十歌から二十二歌
第四天、すなわち太陽天ではトマス・アクィナス、そしてアリストテレスをキリスト教の基盤に据えたといわれるアルベルトゥス・マグヌスら多くの神学者や哲学者がいる。そこでダンテは「己の一切の愛を神に注いだ」といえるほど真剣に考えた。天国では、人は直観知の明証性を論理化することができる。多くの聖人の説教を聞き、ベアトリーチェ自らも理論を述べ、問答を通して知的会話が為され「歓喜は永遠となる」。
ダンテとベアトリーチェを中心に生き生きと輝く火が冠のように拡がり照り映えている。真実の愛は恩寵の光に火を発すると愛によって益々強まってゆき、君を高みに導くという声が聞こえてきた。トマス・アクィナスの声だった。その右にはケルンのアルベルトゥス、グラチアーノ、ソロモン、スペインの司祭オロシウスなど光の輪を構成する12人のキリスト教の智者たちが紹介されていく。すると甘味な清音のような合唱が聞こえてきた。(十歌)
彼女は、まだうら若い女であったために父の怒りを買った。この女に対しては死神同様、誰一人門戸を開かなかった。そいて、司教法廷、並びに父親の前で彼はその女と結婚し、それ以後その女を熱愛した。トマスはダンテにアッシジの聖フランチェスコとポヴェルタ、つまり清貧との逸話を語りはじめる。(十一歌)
第一の光の輪を取り囲んで第二の輪が廻りはじめる。第二の輪も12人の魂で輝いている。その中の一人ボナヴェントゥーラがトマスの所属したドミニコ会の創設者・ドミニコの逸話を語る。ボナヴェントゥーラ自身はフランチェスコ会士だった。そして、ユーグ・ド・サンヴィクトールら他の11名を紹介する。(十二歌)

ギュスターヴ・ドレ『天国篇』 第十二歌
あまりにたやすく事をきめつけ
野原の穂など熟せぬうちに
値踏みするような人にはなるな。
茨は冬こそ恐ろしげだが、
後その小枝に薔薇の花を
咲かせていたのを見たことがある。
遠い海原を舟足速く
はるかな舟路を渡った舟が
港に沈むのを見た。
一人が盗み他が寄付するを
見たとて世人よ神の審判が
定まると思うな、ありうることは
前者の更生後者の堕落(130-142 今道友信 訳)
神曲はトマス神学の詩的結晶と呼ばれる。ここでもう一度、トマスがダンテに語りかける。アリストテレスの『ニコマス倫理学』の実践理性をトマスがキリスト教的に展開した徳目についての解説になっている。自らの中に道徳的判断の基準となるどのような原理を持つかを問うているのだ。人生は計画どおりに機械的に進行しはしない。偶然と必然の間を揺れ動く、アリストテレスは理論理性(エピステーメー)に対して実践理性(ブロネーシス)を分立した。それが徳目プルデンティア(智慧)である。(十三歌)

ギュスタ―ヴ・ドレ『天国篇』 第十四歌
別の光明が現われると先ほどの二つの光の輪のまわりを煌めきながら舞いつつ回り始める。両の眼は眩み、もはや凝視に耐えなくなる。二人は火星天へと上昇した。天の川の星たちのように、赤い光明たちが居並ぶと円内で直交する二直径からなる尊い印を形づくり、十文字の光がキリストの姿を描いた。その光明の群れから身も心も恍惚とさせるような旋律が流れた。(十四歌)
晴れ渡り澄み切った夜空を火が突然よぎる。流れ星と異なるのは、星は消えずその光跡が消えることだった。そのように十字架の右手から一つの星が駆け下りてきた。ダンテを待ち焦がれていた高祖父のカッチャグイダの魂だった。彼は、ダンテに12世紀の平和で地味で貞潔だったフィレンツェを語り、コンラード皇帝旗下の騎士となって第二十次十字軍に従軍して回教徒と闘い、1147年に戦死して殉教者となったことを教える。(十五歌)
ダンテは、先祖やカッチャグイダの幼年時代のことを尋ねる。当時の有力な貴族や名門の名が語られ、アミデイ家がダンテたちの災いの元凶であり、ブォルデルモンテ家がそのアミデイ家との婚約を破棄し、その後の殺傷沙汰に至ったことが告げられた。(十六歌)

ギュスターヴ・ドレ『天国篇』 第十六歌
ダンテは、この先祖に対して自分の未来を問うた。高祖父はこう答える。
お前自ら経験しよう
どんなに苦いか他人のパンは、
他家の階段を降りるつらさも。(58-60 今道友信 訳)
そして、ダンテは自分の意志をこの言葉に凝結させる。
父上(一門の古老を指す)、時勢は私に迫り
拍車を加えて討とうとします、
士気を失えば図に乗るでしょう。
されば、先見で我が身を鎧(よろ)い、
たといふるさとが奪われたとて
我が詩の在り処は確保しましょう。
はてない苦難の世界に降り、
淑女が示した峰に向って
美しい山を経めぐり登り、
光、光と昇りつづけて
学びえたことをまた言うならば
酢を飲まされたと人は言います。
だがもし私が真理に対し
卑怯になるなら今を昔と
呼ぶ世代からは否定されます。(106‐120 今道友信 訳)
未来とは何か ? 動物と人間を分けるものは理性であるとトマスは言う。自然における形態の変化ではなく、生き方の変化としての歴史が人間の理性の内にしかないのなら、歴史形成の根拠は人間にある。歴史形成へ向けて理想が求められるなら、それは理性に求めなければならない。(十七歌)

フランチェスコ・スカラムザ(1803-1886)
『天国篇』 第十八歌 TERRAMのM字、
鷲が頭を沈めた形に見える。
火星天には下界で名を馳せた多くの勇者たちの魂が光明を放っていた。ヨシュア、マカベウス、シャルルマーニュ、ローランたちの名が呼ばれる。やがて、二人は、第六天である木星天の白い静光の中にいた。そこでは、光芒に包まれた魂たちが時に D、時に I、時に L の文字を組むのだった。DILIGITE IUSTITIAM(愛せよ正義を)、QUI IUDICATIS TERRAM(地を裁く者らよ)という文字が金で象嵌した銀のように輝いていた。無数の光明が火花のようにあたり一面に飛び散ると鮮明な光芒となって鷲の頭と首を形づくりはじめた。(十八歌)

ギュスターヴ・ドレ『天国篇』 第十八歌
鷲は多くの象徴的な意味を持っている。木星の神ユピテルは鷲に変身したし、ローマの旗印は鷲であり、正義の象徴、キリストの象徴と考える人たちもいる。光たちが集まって出来た鷲は、一つの魂であるかのように語る。正義感と慈悲心のおかげで私はこの栄光の高みまでやってこれたと。ヴェルギリウスに対する思いなのか、キリスト教を信仰していなかったものの救いはあるのかと問うと、永遠の裁きは人間には不可解だという答えが返ってきた。(十九歌)
第六の星では、光明の群れが合唱し、光彩陸離、宝石珠玉を鏤めて輝いていた。その鷲の形の中の最高位は、頭の位置にある六つの光だった。ダビデ、トラヤヌス、ヒゼキア、コンスタンティヌス、シチリア王グリエルモ、トロイア人リペウスの魂だがキリスト以前の人々もいる。天の王国は、熾烈な望みによって掟が破られることを許すことがあるのだとダンテは知らされる。(二十歌)
二人は第七の天、土星天に昇る。ベアトリーチェは言う。もし、私が笑えば、あなたは光輝くユピテルを見て灰と化したセメレーのようになるでしょう。ダンテは、まだその光輝に対する準備が出来ていない。この水晶宮の中に黄金のヤコブの梯子がはるか彼方まで延びている。オスティアの大司教ピエトロ・ダミーノの魂が君の聴力はその視力と同じく現世の人間のそれだ。ベアトリーチェが笑わないのと同じ理由でこの天の甘美な交響は止んでいるのだと教える。(二十一歌)
百余りの光明の中のひときわ大きく輝く魂がダンテの望みを叶えてくれる。彼はモンテ・カッシーノに西欧最大の僧院をつくった聖ベネディクトゥスだった。あなたの姿をはっきり見ることができるような恵みに与れるのかという問いに、君の望みは最高天で叶えられると答える。ベアトリーチェが梯子を昇るように目で合図する。ダンテは飛翔し瞬く間に金牛宮を過ぎ、その中に入っていった。(二十二歌)
天国とはどのように構想されたか

ウイリアム・ブレイク『天国篇』 天の九層
ダンテの描いた天国は単に眠りのような不活発な世界ではなく希望の渦巻くような世界である。天界は、上に行けば行くほど旋回運動が大きくなり、次第に広がっていく。荘子では逆に狭くなっていって一点に収束する。それは不思議な対照をなしているのである。そのような動的な天国をベアトリーチェは「嵐を待望している天国」という。下界の大転換が天にとっても必要だと述べているのだ。苦労なしに永眠のできる所というふうには描かれない。天国は、光における神との一致の中で世界を美しく、より良いものになるようにと望むものとして描かれている。第二十四・五歌では、聖ペトロや聖ヤコブがダンテに信仰について問う。これに対してダンテは「信は望まれたものの実体/まだ来ないものの証しなのです。/これが信仰でしょう」と答える。新約聖書のヘブル書に「信仰とは望まれしことの実体、見えざるものの証なり」という言葉が既にある。トマスの『神学大全』の注にも「信仰とは望まるべき事どもの実体である」という言葉が述べられていると今道さんは書いている。

ミケランジェロ・カエターニ(1804-1882)
『神曲』天界の秩序
天界の構造
第十天(至高天)
第九天(原動天 天使)
第八天(恒星天/神学的な徳――信仰・希望・愛)
―― ↑ ヤコブの梯子 ――
第七天(土星天/観想生活者 真の天の門)
第六天(木星天/正義の徳とその象徴=鷲)
第五天(火星天/殉教者の勇徳)
第四天(太陽天/キリスト教的賢明の徳)
――― ↑ 地球の影響の及ばない天界 ――
第三天(金星天/愛と節制の徳)
第二天(水星天/名誉のための積善)
第一天(月光天/誓願の不成就者)
地球 (地獄界 地上界 煉獄界)
基本的にプトレマイオスの宇宙観に従っているが、大まかに三層になっていて、天界は完全数の10に分割されている。
恒星天 ダンテへの試問 ― 信・望・愛(対神徳) 第二十三歌から二十七歌
二人は恒星天にいる。太陽がそこにさしかかると日脚がおそくみえる方角を一心に見つめるベアトリーチェは、天が明るくなるとほとんど同時に「さあ、キリストの凱旋の軍勢が来ました。天球の回転が取り集めた戦利品の数々とともにやってきます」と言った。その顔は一面に輝いて喜悦の情に満ち溢れた。その光輝にダンテは耐えられず彼女に助けを請うが、もう私の笑顔を見ることができるほどあなたの目は強くなったのですと励ました。キリストが至高天に昇った後、冠の形をした炬火(たいまつ)が降りてきて、一つの大きな星を取り巻きゆっくりと回った。わが子の後に従って冠をいただいたその焔が空を昇って行った。マリアの姿を直視するだけの力がダンテにはまだ無かった。(二十三歌)
彗星のように尾を曳きながら、中心は極めてゆっくりと周辺はさながら飛ぶように魂の群が回転している。その中でもひときわ幸(さきわ)う火がダンテに試問する。聖ペトロが問うのだ。「信仰とは何か ?」するとダンテは「まだ見ぬものの論証です」と答えた。そして、天上において見えるものは下界において隠されていてその姿は見えない。そうした事物の存在は信仰に由来し、その信仰の基盤は希望であり、それゆえ信仰は実体の性格を帯びるのだと補足した。そして、信仰の内容と由来について、自分は唯一にして永遠の神を信じていると述べ、この信仰を証しているのは物理や哲理だけでなく、福音書、詩編、預言書、聖人の著作がその真理を裏付けている。それゆえ自分は永遠の三位を信じますと語った。これが根源であり、火花なのだと。つまり、信こそが天国に入るための門なのである。(二十四歌)

ウイリアム・ブレイク『天国篇』
『聖ペテロ、聖ヤコブ、聖ヨハネとダンテ、ベアトリーチェ』
© The Trustees of the British Museum
ダンテは、もし、この『神曲』が世に出て政敵である邪な狼たちの無法を打ち破ることができるなら、フィレンツェに迎えられ、洗礼堂の泉の前で冠を戴く自分を夢に見る。聖ペトロに続いて聖ヤコブの光が現われる。そして「希望とは何か ?」を問う。 ダンテは、希望とは未来の栄光を疑うことなく待つことだと答える。これはペトロス・ロンバルデスの『命題論』から引かれている。ダンテのスコラ学の素養は並みのものではない。その期待は、神の恩寵と人のその時に到るまでの功徳に由来する。私の心にそれを注いだのは最高の指導者の最高の詩人だったと語る。ダビデである。聖ペテロと聖ヤコブの二つの光に聖ヨハネの光が加わる。焔の舞が止んで後をふり返ると、なんとベアトリーチェの姿が消えていた。(二十五歌)

ウイリアム・ブレイク 『天国篇』 聖ペテロと聖ヨハネ
聖ヨハネを見ようとして目がくらんだ。ヨハネはダンテを慰め、そして、問う。「愛とはなにか ? 」 ダンテは、アリストテレス流に、善は善として理解されると たちまちに愛に火を点す。愛が完全に近ければ近いほど大きい。神は至上善である。それゆえ神は最も愛されて然るべきであると答えて、目を癒してもらう。ダンテは、ベアトリーチェにあの第四の光は何かと尋ねる。それはアダムの魂だった。地上と辺獄での生活を経てキリストによって救われたが、追放の真の原因は限界を勝手に超えたことにあった。人間の好みは天体に左右され理性の産物が長続きしたことはないし、私が話した言葉は既に滅びている。人間が、どのように話そうが、その話し方は自然の裁量によって君たちに任されているが、至上善である神は、地上では I と呼ばれ、ついで EL(エル) と呼ばれた。こうした変化も人間の習俗から考えれば自然のなりゆきだろうと語った。(二十六歌)

ギュスタ―ヴ・ドレ『天国篇』 第二十七歌
第二十七歌、神の御子の御前で空席になっている私の地位を簒奪しているものたちが、私の墓を穢したと憤った聖ペテロの光明が白色から紅へと変わった。と、ベアトリーチェの顔色も変った。そして、第八天は夕焼けのような紅と化した。やがて、天の磨羯宮の角が太陽に触れると凍った水気は雪片となって地球に降るのとは逆に、恒星天の水気は雪片となって上天を指して精気の中を上に昇っていった。ダンテは彼女の勧めにしたがって眼下の地球を眺めた。彼女の笑顔を見た時、神々しい歓喜が彼に降り注いだ。その視線の力によって彼は全速力で回る天の中に押し上げられた。(二十七歌)
神を見ること 第二十八歌から三十三歌
ここはアリストテレスのいう不被動の動者(キヌーン・アキネートン)としての神の働きに与る場所である。凝視できないほどの光を放つ一点が見える。その周りを月とその暈くらいの間隔で円い輪が回転している。中心に近いほど速く、周辺になるほどゆっくりだった。やがて、火花が次々に飛んで火輪とともに回り、ホザナの頌歌を歌った。天使達だった。第一の位階は、熾天使、智天使、座天使であり、第二の位階は、統治の天使、権威の天使、権力の天使、第三の階級が主権の天使、大天使、天使である。これは著名なディオニシウス・アレオパギタの天使のヒエラキアとは少し異なっている。(二十八歌)
永遠の愛はこれ以上自分のために善を集めることができず、時間を越えた永遠の中でいっさいの分限を越えて思いのまま永遠の愛を新しい愛の中に広げた。形相と質料は、結合したものも含めてみな同時に出来上がって光を発した。その時、形相だけのものが天使、質料そのままのものが地球(原料)、二つが結合したものが各々の天となった(『神曲』平川祐弘訳注)。墜落の第一の原因は、あの地獄の底であらゆる重みで身動きできなくなった反逆の天使ルチフェルだった。そして天使たちは全ての事柄が映し出されている神の顔から目をそらすことが出来ずにいるため記憶がないのだとベアトリーチェはダンテに説明する。(二十九歌)

ギュスタ―ヴ・ドレ『天国篇』 第三十一歌
ダンテはベアトリーチェと共に第十天に入った。そこは、アリストテレスが信じる神を超える場所であった。自分が包むものに包まれたかと思えるあの点の周囲を舞っていた凱旋の光が消えてゆく。ベアトリーチェの美しさは人間の把握の域を超えていた。活光がダンテを廻り照らすと彼の視力は一層力に満ち、身体には新たな力が湧きあがった。神来の光の波の大河が円い湖のように広がる。天上に戻った人々がその光の周りで幾千という円い段状の列を作って上から見ている姿を映していた。それは永遠の生命の源である神を暗示する巨大な薔薇の花を思わせた。天国の市(まち)と皇帝となるべきアルリーゴ七世の座が示される。(三十歌)

『聖ベルナールの授乳』 作者未詳 1480-1485
第三十一歌、清らかな魂が真っ白な薔薇の形に並んで現われる。天使たちがその薔薇の花と神との間を飛び回っている。ベアトリーチェへと振り向くと優しげで慈父を思わせる老翁が一人いた。ベアトリーチェが自分を呼び出したのだ、最高段から三番目の円の中にある玉座に彼女が坐っているのが見えるだろうという。ダンテは遠くに彼女を見つめ心からの礼を述べた。彼女は微笑むとやがて永遠の和泉に向う。翁は聖ベルナール、観想の人、熱烈なマリア崇拝者だった。(三十一歌)
聖ベルナールは、マリアをじっと見つめ、その足もとにいるエバ、その下のラケル、ベアトリーチェの横に坐るサラ、リベカ、ユーディト、ダビデの曾祖母ㇽツがいることをダンテに教えた。ヘブライの女たちが壁となって円型を二つに分ける。キリストの到来を信じた人びとの反対側にはヨハネをはじめとした到来したキリストを信じた人びとがいる。ヨハネの他にフランチェスコ、ベネディクトゥス、アウグスティヌスらがいた。下の方には救われた幼児たちがいる。そのほか、アダム、ヨハネ、モーゼらがいることを教える。(三十二歌)

ウイリアム・ブレイク 『神曲』 天国篇 第三十二歌
最終歌、聖ベルナールはマリアを讃えると共にダンテに神の姿が見える恵みが授かるように祈る。祈りは聞き届けられた。光線の奥のさらに奥には言葉で及ばぬ言葉を越えた姿、記憶では及ばぬ記憶を越えた姿があった。善は意志の目的であり、善は全てこの光の中に集まっているから、そこから目をそむけることは出来ない。神人合一が成し遂げられる。至高の光の深く明るい実体の中に色の異なる同じ大きさの三つの輪が現われる。虹の二つの輪のように第一の輪が第二の輪に映って見え、そこには同じ色をした人間の姿があるように思える。第三の輪はその二つから同じく発する火のように見える。父から子に直接光が発する。それが産出であり、父と子双方から発する愛の息吹が精霊である。子なるキリストの内に人間の姿を見るとすれば受肉を暗示する。ダンテの中に稲妻のような閃きが走り、ついに三位一体とキリストにおける神性と人性との結びつきを直観するのである。人間は神の無限の愛の器として創られたのだという。ここはアウグスティヌスの神の光を彷彿とさせる場面である。(三十三歌)
ちなみに、グスタフ・ルネ・ホッケの『絶望と確信 20世紀末の芸術と文学のために』は、20世紀末の絶望と希望を考える書であったが、その中で、神曲と数学の関係についてこのように述べている。
ホメロス以降の神人同形同性説 (アントロポモルフィスムス) によれば、神殿は建築というよりも彫刻として考えられていて、柱の胴張、柱頭の先細り、その形態において人間の肉体の比例などの類似が指摘されている。階段の水平線は直線ではなく中心部が凹んでアーチ状になっており、柱は垂直にすると外側にかしいで見えるため少し内側に傾斜させている。そのため一つ一つの柱の太鼓石は、一方に傾いていて、その場所の太鼓石は他のものと取り換えがきかない。このため盛期ギリシア神殿は、エジプトやキリスト期以前の記念物と比べて軽やかで動性に富んでいるという。エンタシスといった技法もデルポイの神託の技術に影響を与えたピュタゴラス主義に遡る。その核心にある「不一致の一致」というヴィジョンをダンテは『神曲』の「天国篇」第33歌で数学的心理と悲劇的に動揺する人間的実存とを一つにするという。
「このヴィジョンこそは、幾何学 (地の測定/ゲオ・メトリー) と神-体験、人間的「主観性」とパルテノンの「美学」の超人間的客観性との合一の驚異にまことにふさわしい (種村季弘 訳) 」。
ダンテは言葉にどのような意味を重ねたか

サン・ヴィクトルのフーゴ(1096-1141)
聖書の言葉の多義性とダンテのことばに対する解釈について今道さんの説をご紹介する。十二世紀の修辞学者で文芸論や論理学に通じたユーグ・ド・サン・ヴィクトルは、サン・ヴィクトルのフーゴと呼ばれたが、聖書を読む時、その言葉に四つの層があることを知らなければならないと述べているという。その四層のうちどの意味が使われているかは分からないと言うのだ。例えば、ラテン語の domus は、言葉通りには建物や家を表わす。修辞的に転用すると魂の意味になる。我が家は我が魂になるのだ。寓意的には教会を指している。そして、センス・アナゴジクス(神秘的解釈)では、天の家、神の家、即ち天の栄光を意味する。一つの言葉がその文でどのように使われているかを理解して読まなければならない。それには想像力が必要だという。
辺獄において智者のマエストロと呼ばれる人は、アリストテレスを意味した。彼とトマスの路線はダンテにとって重要だった。それに加えてソクラテスの倫理学とプラトンの形而上学があった。この古代ギリシアの三人の智者たちは二つのフィリアすなわち、精神的愛で結ばれていた。一つは神的叡知ソフィアへの憧憬(フィリア)であり、もう一つは、師弟愛としての友情(フィリア)であった。ダンテが神曲という哲学詩を書いたのはベアトリーチェへの愛のためであるが、それはエロスを越えてフィリアに高まっていたと今道さんはいう。ダンテは、この作品においてフィリア=友愛をこそテーマにしたのである。ヴェルギリウスとダンテの友情は、ダンテとベアトリーチェにおいて神のアガペー(無償の愛)に補完されていく壮大な詩劇になっていくと言うのである。つまり、智者のマエストロとはアリストテレスであると同時にフィリアであるかもしれないのである。「読み」とはこのように深めることができる。今道さんは、言葉に対する幾重もの解釈とその学問である解釈学の重要性を強調する。
至福直観 神を見ることのメタファー
アリストテレスの哲学が人生において何を求めていたのか。それは幸福であった。真理の知的直観、神を眺めることの幸福な生活であったという。トマスは、この幸福をこの世において実現可能ものではなく、天国において神に直面することによって得られるとしている。それは、神によって天使と同じように天国で与えられることが約束されているものであった(『神学大全』)。トマスにおいて、神は光源であり反照の光としてのキリストと照応する。それらの光に迫っていくことが至福直観であった。美とは明快と調和とによってなる。そこには客観的な認識としての透明性があり、幾何学的、数学的な輝きの美しさだった。
一方、ダンテは「わたしの視力は見つつ強まり、唯一の姿が多様に見えた(天国篇 三十三歌)」と書いている。それは神秘の深まりとしての美的体験であると今道さんは言う。そこには美の認識の多様な深まりがある。無限者としての神に無限に近づこうとする努力が報われる場所が天国ではなかったか。ダンテは、光源としての神の中に呼びこまれ一つとなる。それは神秘的一致であり、天国における愛の完成である。これが、ダンテの考える途方もない企て「美の神学」であったと今道さんはいうのである。


『東洋の美学』
第6章「日本人の美意識―伝統と論理」から要約
「隠口 (こもりく) の 泊瀬 (はつせ) の山 青幡 (あおはた) の 忍坂 (おさか) の山は 走出 (はしりいで) の 宜 (よろ) しき山の 出立 (いでたち) の 妙 (くは) しき山ぞ あたらしき 山の 荒れまし惜しくも(『万葉集』巻十三)」
今道さんは、この歌の中の「妙しき=くわしき」が日本の美の表現の原型であろうと言う。農耕社会であった日本の古来からの思想として生命の清浄の美が草木の美しさから導き出され、男性的雄々しさや、崇高美としての丈高しという表現と繋がり、さび、しをり、ひえさびと言った言葉も秋から冬にかけての植物のたたずまいと関係しているのではないかという。日本の気候及び植生と文化の関係性、季節の文学としての日本文学を和辻哲郎の『風土』、久松真一の『日本文学の風土と思潮』にも見ることができる。美意識に接する道徳意識もまた植物と関係している。清らかさ、権勢の推移にこびない操を百木が色を変え落葉しても緑を失わない松に、寒さに耐え雪空に明るい花を馥郁と咲かせる梅に忍耐の後の成就を、青々と天に向かってまっすぐに伸びる竹に精神の素直さと向上心を見る、松竹梅である。不動の幹から生じる枝葉の変化は、発芽、繁茂、開花、落花、結実、紅葉といった自己を舞台とした変身の生の営みとその反復であり、それに倣うのが日本人の美意識であった。世阿弥は『花伝書』、『花鏡』、『至花道』、『却来華』など自らの著作の題に花を選んでいる。『九位』では芸風の上位三つを妙花風、深寵花風、閑花風と呼ぶ。妙花風は、「新羅 (しんら) 、夜半、日頭明らかなり」として夢想疎石の『夢中問答』にある夜半に現れる太陽といった禅的な妙境を指す。深寵花風は「雪千山を覆いて、孤峰如何が白 (しろ) からざる」として五燈会元の偈を引いている。高いには限界があり深さは測りがたいという意味がある。閑花風は、「銀垸裏に雪を積む」として白光清浄なる誠に柔和な姿と記している。清明な超越的な心としての白と芸術の象徴である花と結び合わされているのである。
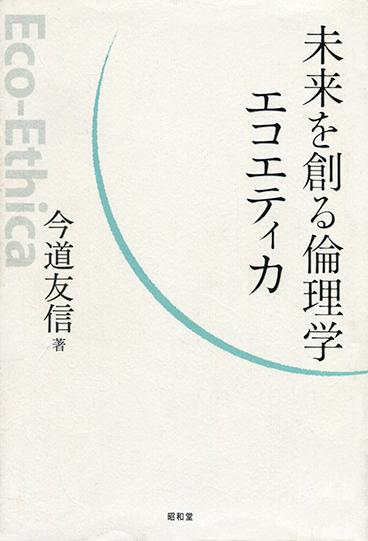
『未来を創る倫理学 エコエティカ』
「ウルバニカ (都市の哲学) の観点におけるエコエティカ」より要約
東洋では、昔は多くの至聖所、ギリシア風に言えばアデュトンがあった。それは限定された場における神聖な雰囲気に対する敬意であり、自然だけでなく家の中にもそのような神聖な場所があった。この空間の支配的力を重視する精神的態度は人々の空間をも支配し、東洋社会の集合的均一性を生み出した。そこには否定的な意味での利己主義はなく、肯定的な意味での個人主義はない。そこにあるのは否定的な意味でのノシズムという集団主義であった。ノシズムのノスはラテン語でエゴの複数形である。エゴイズムと個人主義は全体主義の敵対者であったが、個々のアイデンティティーの集合である「我々主義=シノニズム」はエゴイズムの口実となり、全体主義の口実にもなり得た。今道さんは最も悪意のある理念の一つになったと言う。空間に対するこの敬意は絶対者の永遠性に結びついておらず我々が体験できる空間は常に制限される。絶対者の空間イメージは「無限の空間」と呼ぶべき「無」という否定形で表現された。東洋における無の象徴は広大な自然であり、宇宙的な自然との調和へと導く倫理的な自然主義のはじまりと言っていい。一方、西洋における時間の概念は、我々の意識を個人的な生活へとフォーカスさせた。持続する時間は個人的な意識の流れを強調する。制限される否定的なイメージを伴う「無限の空間」に対して「無限の時間」は「永遠」という肯定的な言葉によって表現される。永遠性の秩序への志向は人間の行為を肯定的な方向へと導く。人間の行為の究極の目的は時間を永遠へと高めることではないだろうかと今道さんは考えている。

グスタフ・ルネ・ホッケ『絶望と確信』
『迷宮としての世界』、『文学におけるマニエリスム』と広義のマニエリスム芸術を扱ってきたルネ・ホッケが現代のネオ・マニエリスムを実存主義的状況から扱った問題作。訳者の種村さんによれば、なりふり構わぬペシミズムの表明であり、現代芸術の不可解な表現の思想的根拠とそのパラレルな作品を炙り出し、同時代の哲学、社会学、生物学の内にその原因を探っている。ブロッホ、カフカ、ブルトン、ハイデッガー、ダリ、ユングら多数の人々が俎上に上がっている。

平川祐弘『ダンテ「神曲」講義』
平川さんは天国篇は訳していてもつまらないと言う、訳している本人がつまらないのだから読者もつまらないに決まっているという分けである。それゆえ、この本の「天国篇」に関する紙数は少ない。筆者のダンテ自身が「天国篇は難解であるから私を見失い、途方に暮れるかもしれない」と小さな舟でついて来る人たち、つまり読者に警告を発している。トマス神学をベースに語れば、その理解は、そうは容易ではないでしょう。つまり、教導的であるから窮屈で、平川さんの言うように世俗的な身近さに欠け、詩的な要素に乏しくなると言われる。
しかし、ダンテにとっては「天国篇」は最も重要で、最も力を入れ、苦心惨憺した作品なのは確かである。僕が今道さんの『ダンテ「神曲」講義』を選んだのは、それらの事柄をちゃんと解説できる方だと思ったからである。この作品は神学へと傾斜していることは間違いない。哲学詩を説明できる人は少ないのである。

『天国篇』第三歌 ダンテとベアトリーチェ、ピッカルダ・ドナティ (ベールの女性) とコンスタンツァ・ダルタヴィラと出合う。
フランチェスコ・スカラムザ 画 19世紀
コンスタンツァはシチリア王国の王女。シュワーベン王朝の二代王エンリコ6世の妻であり三代の王フェデリーコ2世を生んだ王妃。

魔王ルチフェル 『地獄篇』より
フランチェスコ・スカラムザ 画

カルロ・マルテッロとハプスブルク家のクレメンツァ、カレル1世の墓のプレート サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂のファサード内 ナポリ
カルロ・マルテッロ (1271-1295) 1290年に叔父のラースロー4世が暗殺されると、自身の王位継承権を主張してハンガリー王を自称したが、23歳頃にペストで早世している。ダンテと仲が良かったと言われる。

『アエネアスとアンキセス』
(陥落したトロイアから父親アンキセスを助け出すアエネアス/アイネイアース)
ピエール・ルポートル 作 17世紀末~18世紀初頭
『アエネアス』は、ウェルギリウスがアウグストゥス帝からの委嘱で創作した英雄叙事詩の名でもある。

ペトルス・ロンバルドゥス (1100頃-1160)
カトリックの司教並びに神学者。教父たちの著述を注解した『命題集』で名高い。


コメント