
今道友信『ダンテ「神曲」講義』
ダンテはヨーロッパ近代文学の祖と言われている。圧倒的な人が哲学者ダンテを言祝ぎ、詩人ダンテを激賞した。詩人哲学者と言って良い。『ヨブ記』はパトスの文学であるが、ヨブ自身は信仰の人ではあっても哲学者ではなく、ゲーテの『ファウスト』も第一部は非常に哲学的であるが、第二部は飛躍が多く純粋に文学だと今道さんは言う。古今の詩人の中で、詩人哲学者と言えるのは、パルメニデス、荘子、ダンテとニーチェくらいだと言うのである。
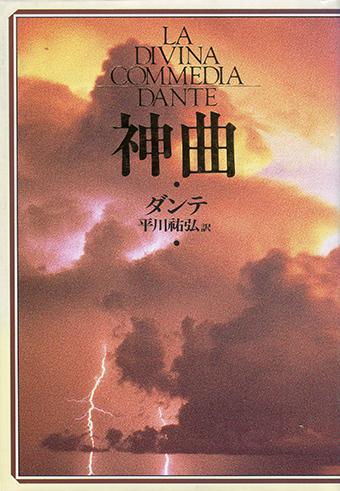
ダンテ・アリギエリ『神曲』平川祐弘 訳
今回の夜稿百話は、前回に続いて今道友信さんの『ダンテ「神曲」講義』をご紹介しています。地獄篇は比較的伝統的なイメージを生かせたのですが、煉獄は、当時かなり新しい概念でした。それで、ダンテは新たなイメージを作り出さなければならなかった。古典的な哲学とキリスト教信仰とを調和させようとしたトマス思想による影響が大きいといわれますが、ダンテには、詩人としての偉大な想像力があった。その想像力が、この「煉獄篇」を経て「天国篇」でクライマックスを迎えます。
「煉獄 purgatorio 」は12世紀に浄罪界として新たに提示された(ル・ゴフ『煉獄の誕生』)。ダンテは、それに関する文学的な先例を知らずホメロスのハデス(冥界)からイメージを借りるしかなかった。ホメロスが描いたハデス、そこは灰色の世界で人は影のように生きる。しかし、煉獄には魂が浄められるという希望があった。地獄の門の前では希望は置き去りにされる他ない。キリストの十字架上の死によって人は原罪から救われたが、自らの罪である自罪は、魂自身が自らを浄めなければならなかったのである。

『煉獄篇』第一歌 1390頃 ローレンシアン図書館
煉獄篇
私は歌おう第二の国を
ここで人間の霊が浄まり、
天に昇るのにふさわしくなる。
(第一歌 4-6 今道友信 訳)
残酷な海=地獄を後にして、今や南極の四つの星(智慧・勇気・節制・正義)を見上げる。すると、一人の翁がいた。かつて、清廉な共和政ローマの執政官だった煉獄の七つの圏の番人カトである。ウェルギリウスは、天の計らいでダンテを案内している、自由のためには命を惜しまぬ者だと説明した。カトは謙譲の象徴である藺草(いぐさ)を腰にまいて煉獄山を登るように忠告を与える。(一歌)

煉獄山 作者未詳 九層からなり七つの環道を持つ。
魂を乗せた舟から煉獄の門へ 第二歌から九歌
美しい曙の白くほの朱い頬が時とともに燃えたつ柑子色に変わっていく時、濃い靄の中で火星が赤く輝くように一条の光が海原の上を飛ぶ鳥を凌ぐ速さでやって来る。魂を乗せた船が天使に連れられて来るのだ。百余りの魂たちは「イスラエルの民エジプトを出でて」を歌い終わると艫に立った天使は彼らのために十字をきった。そして彼らは浜辺に降りた。彼らはダンテが息をしているのを知って蒼ざめる。その中に友のガゼㇽラがいた。彼の歌声に皆聞き惚れていたが、早く山へ駆け上がって汚れを落とせとカトに一喝されてしまう。(二歌)
煉獄には、はるかな眺望と海のゆらぎが見える。ブルクハルトは、自然美が人間の感情に強く訴えかけることが示されたのはダンテを以って開始されると述べた(『イタリアにおけるルネサンスの文化』)。

ギュスタ―ヴ・ドレ『煉獄篇』 第二歌
ダンテは、背後からの光に自らの影が前に落ちるのにウェルギリウスの影が無いことに狼狽し、見捨てられたのかと一瞬思う。急な上りで一群の魂たちに出会った。その中の一人が奸計を弄して皇帝の冠を戴いたマンフレーディだった。法王クレメンテ四世はフランスからシャルル四世を呼んで彼を討たせた。亡骸はヴェルデ川のほとりに投げ捨てられる。彼のように破門された者は、例え、末期に前非を悔いても生前の30倍の時を煉獄で過ごさなければならない。それで、娘のコンスタンツァにこのことを伝えてくれとダンテに頼むのである。現世の人の祈りは、この長い時間を短縮することができる。(三歌)
「葡萄が褐色に熟するころ、村の者はとげのある枝を掻き集めて、畑の口をしばしば囲うが、魂の群れが私たちを離れた後で、先達を先に、私を後ろに、二人きり登った径はその口の幅さえもなかった(平川祐弘 訳)。」このあたりの表現は先達ウェルギリウスの『農耕詩』を意識したものだろう。途中、膝頭を抱えて坐りこんでいる男に出会った。フィレンツェの楽器職人ベラックワだった。どうせ、生きた間だけここで待たされるのだ。急ぐ人はお先にどうぞと言う。(四歌)

ギュスタ―ヴ・ドレ『煉獄篇』 第五歌
山腹を横切って来るのは、非業の死を遂げたが臨終に前非を悔いたために地獄堕ちを免れた者たちだった。その中のカッセロがエステ家の手の者に殺された話を、またモンテフェルトロが、カンバルディーノの戦いで咽喉を刺されて絶命し、死体がアルノ川に流されたが、天使が悪魔から魂を救ってくれた顛末を語る。(五歌)
非業の最期を遂げた魂たちは、次々とダンテに現世の人々への言づけを頼むのだが、彼は祈りで天の決められたことが変えられることに疑問を抱く。ウェルギリウスは、やがてそれに答えて下さる人が現われるだろうと告げる。(六歌)
闇に覆われれば、誰も一歩たりとも上に登ることができない。夜の間は谷間で待つことになった。そこには、皇帝ルドルフ、ボヘミア王オットカル二世、アラゴンのペドロ三世、イギリス王ヘンリー三世らがいた。(七歌)
魂の一人が立ち上がって東方に目を据え「光消えざる先に」を歌い始めると他の魂たちもそれに和した。すると燃え盛る剣をかざした二人の天使が、蛇からこの谷を守るために舞い降りてきた。(八歌)

ギュスタ―ヴ・ドレ『煉獄篇』 第九歌
眠っていると黄金の鷲が火天まで自分をさらって行き、あまりの熱さに夢から覚めた。すると、聖女ルチアがダンテを抱き上げ煉獄の門まで運んでくれていた。ウェルギリウスもそれに従った。ルチアはラテン語の光を意味する。殉教したが、拷問によって目を抉られたものの物が見えたという奇跡を伝えている。それゆえ目の守護聖人でもある。ダンテは聖ルチアと縁が深かったと伝えられる。
高台に裂け目が見えた。時は、1300年の復活祭の月曜日である。その入口には三段の石段があり、一段目は滑らかな白の大理石、二段目は青紫より濃い焼石で縦横に縞が入った粗石である。三段目は鮮血のような赤い重みのある斑岩だった。これは後悔の三段階「心の悔悛」「口の告白」「行為の遂行」を表わしているという。

ウイリアム・ブレイク『煉獄篇』 第九歌
天使はダンテの額に剣の先で七つの大罪(peccatum)を意味する7つのPを刻み、ペトロから預かったと言う金と銀の鍵で煉獄の扉を慎重に開け、ダンテたちを中に通した。そして、振り向けば外に戻ることになると警告した。反省だけでは元に戻る。過去から救い出され、未来に向けた現在の勝利こそが必要とされるのである。(九歌)
神曲の詩型テㇽッアリマ
ダンテの詩の形式はテㇽッアリマと呼ばれる11音節つまり、一行に母音が11あり、三行から成る。これはすでに南仏プロヴァンスに盛んだったトルバトゥール(吟遊詩人)たちが使っていた形式だと言われる。各詩節の最後の母音はABA、BCB、CDC、DED‥‥といった形式の脚韻を踏む。イタリア語の最後の脚韻だけを示すとこのようになる。
われらの進んだ第一段は(io)
白大理石が磨かれひかり(o)
わが身を鏡のように映した(io)
二段目の石は紫蘇よりもこい(o)
焼けた色合いの荒れ石で(ia)
縦にも横にもひびわれがあり(o)
そこから登った三段目(ia)
堅い斑岩で赤く煌めく(e)
脈からあふれる血汐のようで(ia)
その石の上に両足をのせる(e)
神のみ使いは金剛石と(a)
覚しい敷居に腰かけている。(e)(煉獄篇 第九歌94-105 今道友信 訳)
消されてゆく額の罪の文字 第十歌から十八歌

ギュスタ―ヴ・ドレ『煉獄篇』 第十歌
岩間をよじ登ると第一の環道に出た。人の身長の三倍ほどの幅の道が煉獄山を取り巻いている。その道の山腹に面した側にはギリシァ彫刻を上回るほど優れた天使やマリアの像、聖なる櫃(はこ)を引く牛車、トラヤヌスなどのローマの君主たちが絵巻のように彫られている。その下を高慢の罪を償うために岩を背負った人々が泣きながら歩んでくる。(十歌)
「浮世の名聞はいわば風の一吹き、ある時はこちらへ、ある時はあちらへと吹く。風向きが変われば名も変わる。(平川祐弘 訳)」風の前の塵のような名声を鼻にかけた傲慢の災い。それをアルドブランデスコが、そして、細密画のオデリージが語る。(十一歌)
山肌や堅い敷石の上には聖書やギリシア神話から慢心を戒める彫像が並ぶ。明けの明星のように輝く天使がやってきて翼でダンテの額をはたき行路の安全を保障してくれた。美しい歌声を聴きながら石段を登ると、身体が軽やかなのに気がついた。額の罪を表わすPの字が一つ消えていた。(十二歌)
第二の環道に出た。岩と同じ色の外套を着た霊魂たちが岩に沿って坐りこんでいる。彼らの瞼は針金で縫いつけられ、その隙間から涙を流して羨望嫉妬の罪を浄めている。この圏では妬みの罪が鞭打たれる。粗織りの服をまとい、たがいに肩で身を支え、そして、みな崖にもたれている。祭りの日に集った物乞いたちが他人の同情をいち早く得ようと声を立て憐みをこう。そのような風景だった。その中のザービア・ダ・シエーナは嫉妬によってシエーナ軍の敗北を喜んだことを物語る。(十三歌)
その中のもう一人、グィド・デル・ドゥ―カが、アルノ川に面した緒都市やロマーニャ地方の悪徳をなじる。すると、空をつんざく雷のような声が、「我に遇うものは我を殺さん」「我は石と化したアグラウロスなり」と響く。ウェルギリウスはダンテに、これは人間を分限の内に限る堅い轡(くつわ)なのだという。天は人間の周りを巡って永遠の美を示すが彼らの目は地上にばかり注がれていると。(十四歌)

ギュスタ―ヴ・ドレ『煉獄篇』 第十五歌
天使の関所を通過した時、また一つ額につけられた罪のP字が消えた。そして、第三の環道に至った時、ペイシストラトスが娘に公然で接吻した若者を許すように妻に語り、聖ステパノが石もて打たれる時、かの者たちを許すように天に祈る場面をダンテは幻視する。「怒りの火を消す」平和の水に対しては必ず心を開けという訓えなのだとウェルギリウスは語る。(十五歌)
二人は苦い濁った空気の中を進む。地獄の闇もこれほどではなかった。すると、怒りの結び目を解いているという「アニュウス・デイ」に始まる平安と祈りの歌声が聞こえてくる。マルコ・ロンバルドが、世の中から徳が姿を消し悪意が巣食うのは何故かというダンテの質問に答える。それは世俗の権力と宗教の権力の分立が侵された結果だと彼は言う。(十六歌)
ダンテは濃霧の中で水面に浮かぶ泡沫(うたかた)のようにペルシア王アハシュロスと王妃エステル、アエネアスの婚約者となるラウィニアとその母アマタなどの幻影を見ている。すると天の霊が、ここを登れと告げる。第四の環道に登ると夜になった。ウェルギリウスは、ダンテにこう語る。自然愛はけっして誤らない、意識的愛は動機の不純や過不足で誤ることがある。愛が人間のあらゆる徳であり、罰に値する行為の種である。隣人を踏み台にして優越を狙う者、権力や名声を失うことを恐れて他人の不幸を愛する者、不正を蒙り血の復讐に飢える者、これらの者達はこの環道で前非を悔いた上、呵責に遭うのだと。(十七歌)
人間には生得の思考能力があり、善や悪を愛し、その愛を集めて選りだすことができる。理を究め、根本まで遡った人は生得の自由を認めて後世に道徳を残した。ベアトリーチェが貴い力というのはこの自由意志を指しているのだから、彼女に会う時には、そのことに留意しろと先達は注意を催す。環道沿いに走ってくる魂たちの声が聞こえた。善を行う心が生ぬるかったために今その償いをしている人々だ。その中のヴェローナのサン・ゼーノ寺の僧院長をしていたミラーノが自分たちの後についてくれば石段の所にでられるだろうと告げた。(十八歌)
清新体から神学詩へ

サンドロ・ボッティチェリ(1445頃-1510)
『ダンテの肖像』1495
ダンテは詩人として四段階の発展をみせているといわれる。当時、フィレンツェではブルネット・ラッティーニが文化的な中心人物であり、キケロに則った『発想論』という修辞学の著書を書き、まだ大学のなかったフィレンツェでは大きな影響を及ぼしていた。地獄篇第十五歌で「私がいかに先生に恩を感じているか‥‥」とダンテは書いている。詩の修得における目標の第一段階は清新体であった。父にもあたるというグィド・グィニツェㇽリ(煉獄篇二十六歌)と清新派であり、かつての友人でもあったグィド・カヴァルカンティに学んだ。
その特徴の一つは dolce(甘味な)。十二世紀、南仏プロヴァンスの吟遊詩人の詩を継承する宮廷恋愛詩の系統であり、高嶺の花の美女への讃歌である。それにもう一つは nuvo(新しい)。13世紀後半にパリから全欧に広まったアリストテレス的・イスラム文明的自然学の知識による愛の心理学・生理学を指す。そして、最後は公用語と言えるラテン語ではなく俗語のイタリア語で謳ったことである。それは母語でなければ思いのたけを述べられないとしたのは紀貫之と同じだった。それは、十三、四世紀にベギーヌ女子信心会の女性たちと同じく欧州における最初の母語文芸の試みの一つといえる。1290年代の前半まではダンテは清新体の詩人であった。
第二期は、ベアトリーチェを失い、その死によって単なる感傷的な恋愛詩から彼女を賛美し思慕することから生まれた新しい響きの詩が生まれたといわれる。つまり『新生』に代表される新しい詩の段階である。『神曲』の詩には及ばないといわれる新詩だがこんな詩句がある。「われを見しとき、わが名を呼びて いへり、わが意(こころ)に従ひて汝の心の ありし遠きところより我は来れりと(中山昌樹 訳)」このあたりまでの詩の特徴をアウエルバッハは、高貴な遊戯と秘教的性格だったと述べている(『世俗詩人 ダンテ』)。
第三段階は、宮廷恋愛詩とその倫理的変容といわれる象徴詩から脱却し、キケロの『友情論』やボエティウスの『哲学の慰め』などの影響による哲学詩の時期といわれる。途中で創作を止めてしまった『饗宴』という作品がある。とりわけ、キケロは後の時代にとっても重要な思想家だった。literatura = 文学という言葉が言語芸術を総括する言葉としてキケロによって作られた。彼がいなければヨーロッパの抽象名詞の多くは存在しなかったろうと言われている。

ダンテ『神曲』写本 14世紀
第四段階がこの神学詩といわれる『神曲』なのである。これらを踏まえた上で今道さんは、彼の文芸の特色を『新生』も『饗宴』も『神曲』もみな徹底した一人称文学であると言う。太宰や岩野泡鳴のような私小説家と同じだと言うのだ。夏目漱石もアンドレ・ジイドもハインリヒ・ベルもほとんど「私」を語っている。だが、ダンテには彼らと違う点がある。自己の欲望とその現象世界に、それらを越えた創造主の愛と摂理を描こうとした。それがボッカチオをして「この栄光に満ちた詩人」と言わしめた原因だろうと言う。「神の栄光に満たされた詩人」なのである。ちなみに、単に戯曲(Commedia)と題されたこの作品に神々しい(Divina)という文字を冠して『神曲』としたのは、このボッカチオだった。
夢の誘惑・地震と友情・天上楽園 第十九歌から二十九歌
夢の中にセイレーンが現われる。この声でオデュセウスを正道から誘き出したのだ。その者と語っていると聖らかな女性が現われ、この女は何者かと問う。ウェルギリウスはセイレーンをとらえると服を裂き、その前を開くと腹から立ち昇るあまりの臭気にダンテは目を覚ました。堅い岩と岩の間を進むよう天使が話しかけてくれる。見晴らしの良い第五の高台に出ると貧欲の罪を浄めるために人々がうつ伏せになっている。元法皇のアドリアーノ五世が、自分が法王に選ばれた時、嘘偽りの人生の正体を見破ったと語る。(十九歌)

ギュスタ―ヴ・ドレ『煉獄篇』 第二十歌
第二十歌、第五の環道では腹這いになった人々が涙を流して前非を悔いている。フランス王家の始祖ユーグ・カペ―は自分がキリスト教世界の全土に暗い影を落としている悪の樹の根元なのだという。プロヴァンスの伯爵領という持参金に目がくらむまで悪事は働かなったが、その時から暴力と欺瞞がはじまった。子孫ども、シャルルはイタリアに南下しクㇽラディーノを犠牲にし、別のシャルルは海賊が奴隷女を売りとばすように自分の娘をせり売りしている。あまつさえ、フィリップはボニファチオ八世を逮捕し、死なせたと言う。彼の話が終わり、そこを離れると崩れ落ちんばかりに大地が揺れた。地震が終わると同時に歌声も止んだ。(二十歌)
煉獄では誰かが自分の魂の浄化を自覚した時、振動が生じ、合唱が和する。それは人の自由な意志が魂に働きかけた時に起こるのだと詩人スタティウスの魂が語る。それとは知らず彼は、本人を前にウェルギリウスを賛美するのだった。スタティウスは途中まで彼らの道連れとなる。煉獄では友情も芽生えるのだ。(二十一歌)
環道を過ぎる度に額から罪の文字がまた一つ消える。第六の環道に登る途中ウェルギリウスはスタティウスに煉獄で魂を浄化しなければならなかった理由を聞いた。スタティウスは金を惜しむことの無意味さをウェルギリウスの詩句から悟り、逆に浪費僻となってしまったこと、そして異教を装って隠れキリスト者になっていたことを告白する。この生ぬるさのために第四圏を400年余りも巡っていたのだと言う。道の真ん中に馥郁と香るこの実をたたえた樹が立っている。近づくと食べてはならぬという声がした。(二十二歌)
敬虔だが、痩せ衰えた亡者の一群が通り過ぎる。その中に友人だったフォレーゼがいた。生前度を超して飲食した者は飢えと餓えによる浄化を受けなければならないと語る。そして、自分が償うべき時を短くしてくれたのは妻のネㇽラの涙のお蔭だというのだ。そして、胸もあらわに乳首を出して出歩くフィレンツェの女たちを予言して嘆く。(二十三歌)

ギュスタ―ヴ・ドレ『煉獄篇』 第二十四歌
もう一人のやつれた顔はルッカのボナジュンタだった。彼は、ルッカに生まれたジェントゥッカという一人の女性がダンテに好意を寄せてくれるだろうと語り、話は清新体に移った。連れとなっていたフォレーゼは、分かれ際に彼の兄でダンテの政敵・黒党の首領であったコルソ・ドナーティの悲惨な最期を予言する。すると、もう一本の樹が現われ、その下では人々が物をねだる子供のように手を差し伸べていたが、此処へ寄るなと声がして飽食の災いを語った。上にあがるにはこの道を曲がれと赤々と輝く玻璃のような光の姿が声を発すると風がダンテの額に吹き寄せ羽が動くのが感じられた。(二十四歌)
今は、復活祭の火曜日の午後二時を過ぎた。石段を登りながらダンテはウェルギリウスに肉体を捨てて養分を取る必要のないも者が何故やせ細るのだろうかと問うた。二十一歌で登場したスタティウスがそれに答える。血液が精化されてその能動力から魂が作られ、やがてクラゲのようなものが動きだし諸器官を形成し始める。こうして脳の組織が完成すると新たな霊魂が吹きこまれるが、生を終え、魂がきずなを脱しても記憶力、意志、知力は残る。魂は地獄か煉獄かに落ちて自己の道をゆくが、形成力は周辺に向って生きていた時と同じように魂が刻印する通りのかたちを大気の中に形成するという。やがて五官を作り出し視覚さえ備える。欲望や感情が魂に触れるとそれに応じて大気のような影の形も変るのだと言うのだ。最後の圏への道にたどり着いた時、山腹から焔が吹き出し亡者たちを焼いた。その間彼らは貞節を守った女や夫の名を呼び上げながら賛美歌を歌っていた。(二十五歌)
火の輝きに影を宿すものを見て魂たちは蒼ざめた、その中の一人はその理由を尋ねたがった。その人の名がグィド・グィニリツェㇽリだと知るとダンテはが感無量となった。詩人としての大先輩、父にもあたる人だと言う。僧院へ行くことがあったら「主の祈り」を一遍、この煉獄の者たちのために唱えてやってくれと頼むと魚が水に潜って水底に消えるように焔の中に姿を消した。(二十六歌)

ギュスタ―ヴ・ドレ『煉獄篇』 第二十八歌
今道さんによれば煉獄で浄罪の火で焼かれるという概念は、12世紀に突如起こったわけではなくアウグスティヌスの『死者のための供養について』『神国論』に「罪によって穢れた魂を焼く火」を肯定する文章があるという。ウェルギリウスは、この火を越えればベアトリーチェに会えるのだとダンテを勇気づけて火を潜らせる。陽が落ちて岩間の透間から見える星も明るく大きく見えた。夢の中に旧約聖書のレアとラケルで知られるレアが現われた。それぞれ活動性と観想性を象徴とする。陽が登るとウェルギリウスは、こう語って間もなく姿を消すことを暗示するのだった。「永遠の劫火と一時の劫火を、息子よ、おまえは見た。そして、おまえが着いた地はもはや私の力では分別のつかぬ処だ。私はここまでおまえを智と才でもって連れてきたが、これから先はおまえのよろこびを先達とするがよい(平川祐弘 訳)。」(二十七歌)
さわやかな緑濃い神の林だった。ここちよい柔らかな風が軽やかに額を打った。花々で覆われ彩られた小径を歌いながら花を一本一本選りながら一人歩いてくる夫人がいた。夫人はこの地は神が永遠の平安の保証として善を行う人間に与えたと告げる。地上楽園であった。こちら側では罪業の記憶を消すレテの川が、あちらでは善行の記憶を新たにするエウノエと呼ばれる川が流れていて、両方の水を飲まなければ効き目はないという。(二十八歌)

サンドロ・ボッティチェリ『煉獄篇』 第二十九歌
その夫人マテルダとダンテは川の両岸を上流に向って歩んでいく。稲妻のような光が走ると光芒は燦爛と輝き始め、嚠喨(りゅうりょう)の楽の音が走る。ダンテはエバに対する義憤が湧きあがるのを感じた。七基の燭台が静々と進んでくると、その後ろに白衣をまとった人々が続き、川を隔てて焔が前に進んでくると彩られた空気は絵筆を走らせたように尾を曳いた。7色の幟は、はるか彼方へと棚引いた。百合の花をかざした24名の長老が進み、四匹の霊獣に囲まれて二輪の凱旋車をグリフィンが曳いていた。頭と翼は黄金の鷲で他は朱と白の獅子の姿だった。右側の車輪の近くには、一人は赤く、一人は緑玉で一人は雪のように真っ白な三人の天女が歌に合わせて歩んでいた。左の車輪の近くでは葡萄色の服を着た四人の天女が、その中の一人である三つ目の天女に従って舞っている。行列の最後にヒポクラテスの流れを汲む厳かな医師のような翁が二人と質素な服装の四人の姿があった。最後尾は、気色鋭い老翁が微睡みながら歩んでくる。《これらの登場する霊獣や登場人物の寓意については巻末に『ボルヘスの「神曲」講義』から紹介しておいた。》(二十九歌)
ああ ! ベアトリーチェ 第三十歌から最終三十三歌

『ダンテとベアトリーチェ』 1850-1900頃
アリー・シェーファー (1795-1858) の絵画を
ナルシス・ルコントが撮影

『ベアトリーチェ』
サウル・ファンファーニ (1856-1919) 作
ダンテは1265年5月にフィレンツェの貴族アリギエーリ家に生まれた。彼の永遠の恋人と言われたベアトリーチェは翌年の6月に生まれている。ダンテは彼女に9歳の時に初めて出会い、その後行き来はあったかもしれないが、18歳の時、道で出会った時の彼女の挨拶に生涯忘れ得ぬ「魂がおののくような経験をした」。その後、彼女は有名なバルディ家に嫁いで、24歳の若さで亡くなってしまう。それ故と言って良いのかもしれないが、彼の心の中にベアトリーチェは生涯生き続けていたのである。
巨大な燭台とグリフィンの間を進んできた民の一人が「新妻よ、レバノンより来たれり」と歌いながら三度叫ぶと、その声に一斉に皆が和し、花々をあたり一面にまき散らした。それが雲のようにあたりを覆った時、白い面絹をかけ緑のマントに下に燃えたつような朱の衣を纏ったベアトリーチェがその車の上に凛々しい王女のように立ち上がった。

ウイリアム・ブレイク『煉獄篇』 第三十歌
彼女の神秘の力に動かされ、昔の愛の激情が甦る。狂おしく振り向くとウェルギリウスの姿はもはやなかった。涙が頬をつたって流れ落ちた。「泣いてはならぬ。お前は、ほかの剣になお泣かねばならない」とベアトリーチェは水兵を査閲する提督のように語った。
ベアトリーチェは、自分の言葉がダンテに罪に応じた悩みをいだかせるために発せられていると天使達にいう。私が天に昇った時、彼は私を愛さなくなり、善の虚像を追った。私は神に霊感を乞うたが受け入れられず彼は堕落に堕落を重ねた。救いの手段は破滅した者を見せる他なかったと言うのである。このベアトリーチェに同情した聖母マリアが聖ルチアを遣わせてウェルギリウスにダンテの案内を頼んだのである。(三十歌)
ダンテはベアトリーチェに詰問され、涙ながらに前非を悔いた。悔悛のイラクサがダンテを刺し、自分の罪に対する心痛のあまり失神した。眼を覚ますとマテルダ夫人が自分を曳き、小舟のように水上を進んだ。「汝我を清めたまえ」というあまりに優しい声で自分を水の中に浸した。ダンテを水から引き上げると4人の美しい天女が舞う中に連れて行った。ニンフである天女はベアトリーチェに清らかな眼をダンテに向けるようにもよおした。(三十一歌)

サンドロ・ボッティチェリ『煉獄篇』 第三十一歌 部分
10年ぶりにベアトリーチェの笑顔を見た。まぶしさに視力を失いかけたが、やがて回復する。グリフィンの曳く車が向きを変えて動き出した。マテルダ夫人にダンテとスタティウスがそれに従う。葉も花もない巨大な樹の一本の枝でその轅を繋いだ。ベアトリーチェはダンテにしばらくここで森の番人となり自分と共に永遠のローマの民となり、ここで目にしたものを現世に戻って書くようにと語った。大鷲が降りてくると車に一撃を与え、女狐が走り込んできた。女狐が逃げ去るとまた、鷲がやってきて車の中に羽を散らかし、去っていった。今度は龍が地面の割れ目から現れ車の底の一端を食いちぎって去った。角を生やした異形の頭があらわれ、娼婦が色目を使いダンテを見ると情夫の巨人が鞭で女を叩きのめした。(三十二歌)
ベアトリーチェは先ほどの事件に関係していると思われる種々の事件を謎めいた言葉で語ると、あの巨大な樹が智慧の樹だったことをほのめかす。そして、ダンテとスタティウスはマテルダ夫人の勧めるままにエウノエの川の水を飲むのだった。しかし、ここで第二篇のために用意された紙数は尽きる。復活祭の水曜日の正午頃であった。(三十三歌)

サンドロ・ボッティチェリ『煉獄篇』 第三十三歌 部分
煉獄山は、浜辺から山腹を登ると煉獄門(地獄門と同じく第9歌に登場する)に至る。ここから上に7つの環道がある。そこで、それぞれの罪を浄めるのであるが、下から順に第一(傲慢)、第二(嫉妬)、第三(怒り)、第四(怠惰)、第五(貪欲)、第六(大食)、第七(色欲)となっている。アリストテレス=トマスによる誤った愛に基づく悪徳の発生説からの分類である。そして、頂上にはかつてアダムとエバのいた地上楽園がある。したがって地獄と同じく、都合九層になっている。これが煉獄山の構成である。それは人が住まない南半球にあるとされた。
神曲の構成はというと、全部で百歌からなり、地獄篇は三十四歌だけれど第一歌は総序の意味があるので三十三歌と考えられている。煉獄篇は三十三歌、天国篇も同じく三十三歌となっている。三は三位一体から来る聖数であり、十は完全数である。ボルヘスがダンテの世界は、一と三と円環に支配されているというのは尤もなことなのだ。
これに関連して今道さんはミルコ・マンゴーリが指摘するダンテの数秘を紹介している。ベアトリーチェがダンテの前に姿を現わすのは煉獄篇の第三十歌であるが、それ以前に彼は六十三歌を費やしている。その後、三十六歌で『神曲』は完結する。彼女がダンテに名を告げるのは、その第三十歌の七十三行目であり、その後は七十二行ある。七十二は7+2=9となる。今道さんは、哲学にはソクラテスの言語のロゴスとピュタゴラスの秩序のロゴスの二つの系統があり、前者は人間の意識の展開が現象を支配する構造としてのイデアに迫るのに対して、後者は実在そのものが数を通して人間に理解可能なように自己を開示していることを観想することによって事象の本質に迫る思想だという。ダンテは、アリストテレス=トマス・アクィナス系統のスコラ哲学だけでなく、ピュタゴラスの数秘主義を別に発展させていた可能性もあるというのである。

エルヴィン・パノフスキー(1892-1963)
『ゴシック建築とスコラ哲学』
新プラトン主義の哲学的影響もあるとされるトマスだが、一般的にアリストテレスの哲学とキリスト教の信仰をいかに調和させるかが、トマス神学の課題だったと言われる。「聖なる教え(神学)は、信仰を証明するためではなく、この教えに示されているその他のすべてを明瞭にするために人間の理性を使うのである(トマス『神学大全』前川道郎 訳)」という。啓示や神の本質といったこと以外の自然学、倫理学、哲学に関する事柄に明確な証明を与えること。啓示については積極的な論証はできないにしても、ある種のアナロジーによってその神秘を「顕わにする(マニフェスト)」ことを目指した。もし、神曲とトマス神学との関係を問われるなら、このアナロジーによるマニフェストが最も重要な部分になるだろう。ともあれ、この「顕わにすること」=「明瞭にすること(クラリフィケイション)」はトマス神学の第一原理だとパノフスキーは言う(『ゴシック建築とスコラ学』)。
その明瞭化の手段として、1.全体性(十分な列挙)、2.相同な部分と部分の部分との一つの体系に従った配列(十分な分節化)、3.明確性と演繹的説得性(十分な相関性)をパノフスキーは挙げている。1.と2.については、例えば、見出しと数字と段落とによる紙面の視覚的分節化などがよい例となる。要するにある順序に従って配列することが「精神的習慣」となりつつあったのである。ダンテもまた、そのような雰囲気の中にあった。3.の演繹的説得性が神曲の場合重要なのだが、ダンテの表現する対象とその表現とは対象の具体性とその意義とに重なり合って、テクストの構成全体とテクストとの関係をより確かなものにしている。ダンテの新しさは、トマスのように対象を理論的に明確にすることよりも詩的イマジネーションによって顕にすることを目指したことであった。そのことは天国篇においてより一層明らかになる。ともあれ、私たちは、この緻密な構成と豊かな詩的表現に魅惑されて止むことが無い。次回天国篇でも、その哲学と詩的表現を探ってみたいと思っている。
付『ボルヘスの「神曲」講義』から 第二十九歌の霊獣・人物たちの寓意

ホルヘ・ルイス・ボルヘス(1889-1986)
『ボルヘスの「神曲」講義』
ボルヘスは、この本の八章「夢の中の出会い」において、第二十九歌に登場するものたちの寓意に関する諸説をこのように紹介している。興味のある方は、こちらも読まれるとよい。
24人の長老はヨハネ黙示録の冒頭にあるは、旧約聖書の全24巻(聖ヒエロニムス『弁明的序言』)を指す。
六つの翼の生えた獣は福音史家あるいは福音書を、また、空間の六つの方向への教理の伝搬を指している。
凱旋車は普遍教会であり、その二つの車輪については、複数の説がある。
旧約・新約二つの聖書、
活動的生活と観想的生活、
聖ドミニクスと聖フランチェスコ、
あるいは正義と憐憫であるという。
グリフィンはキリストないし教皇を
右手の女たちは対神徳(信仰・希望・愛)を、
左手の女たちは枢要徳(智慧・勇気・節制・正義)であり、三つ目の天女は智慧で過去・現在・未来を見通している。


『東洋の美学』
「荘子の形而上学的美学」よりご紹介します。
孔子と荘子との間には200年のタイムラグがある。荘周は紀元前370年頃から290 (310) 年頃まで生きた人である。荘周と孔子には決定的違いがあった。孔子の論理学は概念的な三段論法であり、究極的には定義に収斂していき、哲学的思索と専門科学の思索との間に本質的な差はなかった。荘周は孔子だけでなくそれ以後の思想家である老子の存在者の根拠としての無の教説と恵施のパラドックスの論理を取り入れた。これらの論理学は 荘子によって、その基盤が置かれたのである。
春秋の孔子の時代には、様々な乱れが生じつつあったが、伝統的制度や古典作品の権威がまだ生きていて、とりわけ周礼の存在は大きかった。しかし、荘周の時代は戦国の動乱の時代であり、いかなる権威も安定性も無い時代だった。したがって彼は、美しいもの、よきもの、永遠なるものを自己の内に創造しなければならなかったのである。時代は貧しかった。彼は、それぞれの思想家の破片化した思想を根源的思想に還元しようとする。その方法は渦動的であり、動的な契機のための象徴法と逆説を持つことになり、それを語る言語は世間一般の言語を超えて詩的だった。北冥の鯤は化して鵬となり幾千里を羽ばたくのである。
存在論、つまり「在る」は現実であり、その本質は、ある成果をもたらす作用である。それを支えるのは、老子のいう「無」であった。三十の輻の間の空間が車輪の用をなす。しかし、荘周は老子の無を超えてパルメニデスのように一者へと帰還しようとする。ここは、井筒俊彦さんとはニュアンスの異なる解釈になっている。それは螺旋的な上昇の思弁によってイメージ化される。この仄かな光のようなものを求める志向は、光の中での精神のエクスタンシス (忘我) として成就されるという。
音楽的魅惑が純粋なエクスタンシスをもたらすと考えられている孔子の美学を荘周は批判して音楽の音からは解放されるべきだと考える。そこには、存在者の根拠としての「無」があるが、光によって制限された無は未だ、絶対者ではない。暗い中に縛られた精神が光の地平にまで上昇する必要があるのである。ここには存在の上位に美を据える今道さんのカロノロジアの美学が共振している。
ミメーシスとしての再現は、東洋では決して芸術の理念とはならなかった。それは一者から遠く隔たっているからである。南北朝の謝赫の画論は唐の張彦遠によって深められ、同じく唐の王維は「画の多様な可能性の中で、私は水墨画を以て最も秀れたものとみなしている。水墨画は自然の気とともに始まり、造化の働きを以て終わる (『画学秘訣』) 」と述べる。事物は造形芸術の助けによって自己独自の使命を果たし、別の現実を出現させる。それゆえ、王維は絵画を芸術とは呼ばず「画学」とした。それは哲学の一種だったのである。
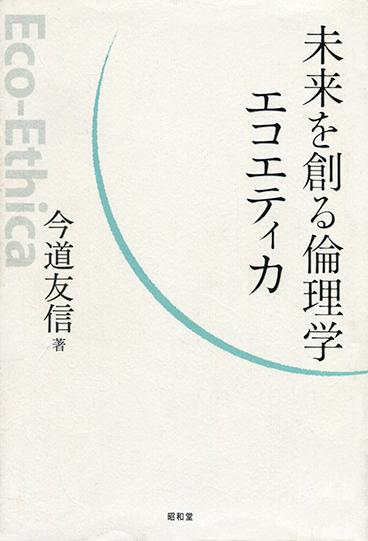
『未来を創る倫理学 エコティカ』
現在の社会において人間の行動指針は、もはや道徳原理ではなく、効果の加速や危険の回避といった技術的規則となっている。寺院や教会のもとではスピノザやデカルトは、人間の歴史における人間性や人間の理性という基盤の上に倫理体系を作り上げたいと願った。今は世界全体を構成する技術機械装置のもとで理性は具現化されている。そして、この新たな世界では、それぞれの個人に、ある方向の中で何かを行うべきこと要請していると思われる。自然のみがあった環境でも科学技術の社会となった今においても「環境としての世界は、人間の道徳性を管理する」という命題は有効である。人間文化のはじまりは、環境としての自然から独立した道徳性の確立であり、自然という無名の権威に対する人間性の勝利と言えた。現代のような環境の中では人間がむき出しの自然から発達させた古い伝統文化の良い面を維持するだけでは不十分と言わざるを得ない。私たちは都市化し、科学技術連関の中に吸収されてしまった道徳的主体性をとり戻さなければならないと今道さんは考えている。それが新たな文化の創造なのであると。

平川祐弘『ダンテ「神曲」講義』
第二十三回 「七つの環道」からご紹介します。
煉獄山は環状の道がついていて、道幅が5m半ほどである。その入り口の三段の階段の上には天使が腰かけていて、ダンテが門を開いてくれるよう頼むと剣の先で大罪を意味するペッカート/peccatoの頭文字のPを7つ額に刻み付けた。(第九歌) それから七つの環道を巡って罪を一つずつ浄めていくことになる。七つの大罪とは本文でも述べたが、以下のようなものである。
高慢(10-12話)
嫉妬(13・14話)
怒り(15・16話)
怠惰(17・18話)
貧欲(19・20話)
大食(22-24話)
好色(25-27話)
第27歌の終わりで罪を浄めたダンテは地上楽園に到達する。第29歌では、智と才はあっても信のないウェルギリウスは姿を消すことになり、ベアトリーチェが登場する。平川さんは「ダンテ、泣いてはなりません」という監督官のような厳しい口調のベアトリーチェに違和感を覚えているが、ここでの彼女は昔、憧れた天使のような女性ではなく厳格な裁く神の代理として描かれていること忘れてはならないでしょう。

アーウィン・パノフスキー『ゴシック建築とスコラ学』
盛期スコラ学は12世紀の変わり目に始まったと考えられるが、それはちょうど盛期ゴシックの体系がシャルトルとソワソンで大成功を収めた頃のことである。初期に対立する盛期におけるスコラ学の顕著な諸特徴と、同様に初期に対立する盛期におけるゴシック芸術のそれとは著しい類比/アナロガスをみせている。人間の霊魂は不死と考えられていたが、今や肉体から独立した実体としての物ではなく、肉体を構成する統一原理と考えられるようになる。もはや草木は、そのイデアの写しとして存在するのではなく草木はそれ自体として存在する。それぞれ個物の存在としての創造物が神を証明するものとなる。それらを網羅する盛期スコラ学「大全/スンマ」は厳格に構成された余す所のない体系となっていった。そして、1270年の聖王ルイの死後50年から60年は盛期ゴシックの緩やかな終局を奏でた。創造的衝動は中心から周辺へと拡散していく。パリから南フランスへ、イタリアへ、ドイツへ、イングランドへと。トマス・アクイナスにおける理性の至高の総合力に対する信頼が揺らぎ始め、前スコラ的なアウグスティヌス主義が復活し始め、万人向きの通俗化された論文が出ると思えば極限的にまで推敲され練り上げられたものが登場するようになる。同様に古典的な大聖堂の型は放棄され、縮小され単純化されるか洗練され複雑化するかした。哲学史において盛期スコラ学が後期スコラ学へと転換されるのは14盛期中葉になってからと言われる。スコラ学のエネルギーは詩へと、終局的にはグイド・カヴァルカンティ (ダンテの友人) とダンテとペトラルカを通して人文主義へとその道を開くか、マイスター・エックハルトとその後継者を通して、反合理主義的神秘主義へと通じていく。

ソワソン大聖堂 フランス

『ベアトリーチェ・ポルティナリ』
(ベアトリス “ビーチェ” ディ フォルコ ポルティナリ)
ダンテ記念碑 トレント
チェザーレ・ゾッチ (1851-1922) 作

ラファエロ・サンティ 『秘蹟論争』1510-1511 部分から「ダンテ・アリギエーリ」


コメント