
中田勇次郎 『文房清玩』 第三巻
二玄社 1962年刊 全三巻
袁宏道『瓶史』収載
春はあけぼの‥‥夏は夜‥‥秋は夕暮れ‥‥冬はつとめて(早朝)‥‥(清少納言) 春は白みかかった山の端。夏の月と蛍。秋の夕日と鴉、雁、風の音、虫の音、雨。冬の早朝、雪、霜、炭の黒。四季の趣きである。
春は花夏ほととぎす秋は月 冬雪きえですずしかりけり
(道元) 本来の面目とは雪・月・花とホトトギス。余計な解釈はいらない。
形見とて何かのこさむ春は花 山ほととぎす秋はもみぢ葉
(良寛) 裏をみせ 表をみせて散る紅葉 付け加わるものは紅葉、欠けるものは月と雪。花だけで表現すれば以下のようになるだろうか。
春は梅、海棠、夏は牡丹、芍薬、安石榴(ざくろ)、秋は木樨、蓮、菊、冬は蝋梅。(袁宏道/えん こうどう)

趙従吉(雪斎)『月梅図』 明 15世紀 東京国立博物館
次は花に関する中国の古典二題
‥‥室を水中に築き
之を葺きて荷もて蓋(おほ)ふ
蓀(そん)の壁 紫の壇
芳椒を播(しい)て堂を成す
桂の棟(むね) 蘭の橑(たるき)
辛夷(こぶし)の楣(まぐさ) 葯の房‥‥
(屈原『楚辞』九歌 湘夫人)抜粋
室を水中に設けよう。蓮の葉の屋根、アヤメの壁にムラサキの壇、山椒の堂、桂の棟、蘭のタルキ、コブシのまぐさ、よろい草の房‥‥そういえば、菖蒲と屈原と端午の節句があったが、これなど前衛生け花を彷彿とさせるものがある。
‥‥菊を采(と)る東籬(とうり)の下 悠然として南山を見る
山気、日夕(にっせき)に佳く 飛鳥相い与(とも)に還る
此の中に真意あり 弁ぜんと欲して已に言を忘る‥‥
(陶淵明) 『飲酒二十首』より抜粋
菊を取ろうとした視線の先に、南山を悠然として見る。晴耕雨読、隠棲生活の陶淵明。世俗を逃れた文士の生活を言祝いだ先駆の一人であった。そういえば、『桃花源記』もある。

徐熙(じょき/886年—975年)画 五代
山水花竹を愛することは、延 (ひ) いては自然を愛することと言ってよいだろう。雪・月・花は単にそのインデックスか抽斗ではなかろうか。『花伝書』など書名を多く花で飾ったことで知られる世阿弥は、『九位』において最上位の三つの芸風を妙花風、寵深花風、閑花風としている。閑花風への説明として「銀垸裏に雪を積む」とあり、白光清浄なる誠に柔和なる姿と記している。清明な心と生命の象徴としての白が芸術の象徴である花と結び合わされているのである。自然の懐で人間生活の意義を見いだし、俗世間から離脱することは、清風の閑たる人間の生活心情として言祝がれてきた歴史があった。それは、唐に兆し、宋以降確立した文房清玩の世界の中にも存在していた。文房 (書斎) における、「趣向の美学」である。これについては、喫茶の清風とも関係が深いが、その中には花や竹を愛でることもあったのである。今回はその花にスポットを当てたい。
袁宏道の『瓶史 (へいし) 』
明代の詩人であった袁宏道(えん こうどう)は、彼の著書『瓶史 (へいし) 』の中でこう書いている。ちなみに、瓶はビンともヘイとも読むけれど、ビンは唐音、ヘイは漢音らしく、この場合はヘイと読む。その序の中の一文を引用させていただく。仮名使いは、いささかだが現代風に改めた。
「‥さいわいにしてわが身は隠見のあいだに居り、世のなかのはしりあるき、あらそうべきともがらは、すでにいたらざれば、余はついに笠を高巌にかたむけ、纓(えい/冠の後に垂らす布)を流れに濯(あら)いし人ごとからんとおもいしに、またいやしきつかさのほだすところとなり、わずかに花をそだて竹をうつしううる一事をもて、みずからの楽しみとなす‥‥」。
今回の夜稿百話はこの袁宏道の著書『瓶史』をお送りしたい。名文である。中田勇次郎 さんの『文房清玩』シリーズの第三巻に掲載されている。訳された中田勇次郎さんの手腕もあるだろうが、もとの文がすばらしいことは間違いないと思われる。訳者によれば、「その内容の豊かさと字面の趣味のよさにおいて、まず、ならぶものがないといってよい。おそらく、明人の文房小品のなかにおいて、もっとも芸術的な香りの高いものであるといってよいであろう」という。べたほめだ。色々な人々の文章に感動するのだけれど、この人のは美文でいい。おおいに宣伝したい気持ちになった。

陳洪綬(ちんこうじゅ)『雅集図』 部分 明
袁三兄弟 左端が袁宏道(袁中郎)

『瓶史』明末 繡水周應麐刊本
袁宏道は、明の後期、1568年湖北の公安県に生まれた。 兄の宗道、弟の中道とともに三袁と呼ばれ、文学者として知られた人だった。人がもって生まれた心の働き、つまり性霊を率直に表現することを肝要とし、格調や形式にこだわるべきではないと表明した。その作風は公安派と呼ばれ、清新さを讃えられたという。28歳の時に呉県(蘇州)の知事となるが官吏には向かなかったのだろう、しばらく後に辞職。31歳の時に北京に移り教員となった。荘子を仏教から解釈した『広荘』と詩人・画家であった徐渭(じょい)の伝記『徐文長伝』を著している。袁宏道は徐渭を敬愛していた。文長は徐渭の字名である。この『瓶史』は万暦二十八年(1600)、33歳の時、同じく北京で書かれた。その後、酒の飲み方についての『觴政(しょうせい)』を書いている。39歳の時に礼楽・儀式・祀祭・科挙などをつかさどった官庁である礼部に復帰、詩作を続けながら万暦三十八年(1610年)42歳で亡くなっている。早逝だ。とりわけこの『瓶史』のような散文の小品に極めて優れたものがあるという。

徐渭(じょい/1521-1593)

徐渭(じょい/1521-1593)『四季花卉図巻』 部分 明
「仏には桜の花をたてまつれ 我が後の世を人とぶらはば。」昔の日本人は、こういう歌を詠んだのだ。中国では、竜門石窟に丸い壺に入れた蓮華の彫刻があり挿花を表現した最も古い例となっている。花によって仏を荘厳することがテーマになっているのである。仏教との関係がまず注目される。仏や菩薩に花を奉ったのは、池坊が良い例だろうが、華道のことには今回は触れない。日本の生け花の書物で古いものは仙伝抄や義政公御成式目などがあるが、いずれも技術書のようだ。中川幸夫さんの過激な華道をご紹介したいと思ってもいるのだが、著作権フリーの画像が手に入りそうにないので難しいかもしれない。
「瓶花」とは花を花瓶に生けること、つまり「いけばな」のことである。本書から「瓶花」の簡単な歴史と日本における『瓶史』との関わりをご紹介しよう。唐の時代になると花の鑑賞が進み、李白の『春夜宴桃李園序』や白居易の『牡丹芳』などの花詩の名作が生まれるようになる。宋になれば、一つの花に関して珍しい種類を列挙し、それらを競い比べ、栽培法などの解説を加えた花の譜が登場する。南宋の頃には花を活けて鑑賞する風はあったようだが、いけばなの記述が現われるのは明代になってからだ。
高濂(こうれん)の『遵生八牋(じゅんせいはっせん)』の一部に花木の解説があり、張謙徳の『瓶花譜』はあるものの、いずれも技術的な事柄が主で思想的なものはなかった。まとまった挿花の著作としては、この明の時代の『瓶史』をまたなければならない。袁宏道は、「瓶花の目(もく)と説を記すこと、陸羽の茶経のごとし」と自負している。この気概は見上げたものだ。ちなみに宏道は陸羽と同じ湖北の出身だった。「瓶花の道を一つの理念で貫き、それを一つの芸術として極めて完全な形式にまとめ上げた」とは中田さんの指摘である。

惲寿平(うん じゅへい/1633-1690)『出水芙蓉図』 17世紀 清
ついでに言っておくと六朝で好まれたのは芙蓉で、これは蓮を指している。唐では牡丹、宋では梅が愛された。陸游(りくゆう)は蝋梅が好みだったようだ。花の好みも時代の流行があった。中国では、桃は好まれても桜はあまり人気がないのだろうか。どうも日本のように綺麗に咲く種類が少ないのが原因のようだ。時に、爆発的な流行になることもあってオランダのチューリップや江戸時代の朝顔は、よく知られている。
この『瓶史』は、日本でもかなり早くから知られていた。特に、京都深草の瑞光寺にいた日政(通称元政げんせい/1623-1668)という僧が袁宏道の文集を所蔵して有名だったとある。江戸前期の人だ。生け花の方面でも取り上げられるようになる。望月梨雲斎(1722-1804)が挿花に瓶史があるのは、礼楽に春秋があるようなものであるとして、自身が挿花の流儀を創始し、宏道のあざ名である中郎を以って世に袁中郎流と呼ばれたという。


左 沈周『海棠』1500 右 文徴明『牡丹』1531
南京から上海あたりまでを含む長江下流域である江蘇省は、かつて呉と呼ばれ、文人画の伝統の根強い地域だった。沈周(しんしゅう/1427-1509)、文徴明(ぶんちょうめい/1470-1559)、董其昌(とうきしょう/1555-1636)、陳継儒(ちんけいじゅ/1558–1639)ら明代を代表する文人たちを輩出した。袁宏道も徐渭もこの呉の出身である。
その徐渭のことであるが、紹興に生まれた。庶子という不幸な出生を背負い、40歳を過ぎた頃から自殺未遂を重ね。ついに狂気から妻を殺害したか嫌疑をかけられたかで7年の獄中生活を送るという人である。剣術の名手で倭寇の討伐に加わったこともある。詩人でもあり、公安派の先駆と位置づけられている。袁宏道も公安派と呼ばれたことは先に述べた。徐渭の書いた茶書である『煎茶七類』も有名で、「煎茶は微なりといえども、清にして小雅」とある (大槻幹郎『煎茶文化考』) 。しかし、画、とりわけ花卉がいい。『雑花図巻』などに見られる、この狂気が萌すような筆勢、筆致にはちょっと息を飲んでしまうところがある。あまり、日本で知られていないのではないかと思うけれど、いつか、まとまった展覧会があるといい。前置きが長くなってしまった。

徐渭 『黄甲図軸』 部分 明
『瓶史』は、序、1.花目(はなのしな)、2.品第(しなさだめ)、3.器具(うつわ)、4.択水(みずをえらぶこと)、5.宜称(よろしきにかなふこと)、6.屏俗(いやしきをしりぞくること)、7.花祟(はなのたたり)、8.洗沐(うちみず)、9.使令(めしつかひ)、10.好事(すきこと)、11.清賞(はなをめずること)、12.監戒(いましめ)の12章からなっている。好事(すきこと)という言葉があるのだ。これは数寄に通じるのだろうか。この序と12章の中からいくつか抜粋してご紹介してみたい。
序より
序の最後にはこのような言葉がある。「‥‥邸ののちいとせまく、かつ、うきくさのさだめなき身なれば、せんかたなく、但瓶に花を生けて、をりをり挿しかえてはながむることとせり、‥‥めずらしき花は、一旦にしてついにわが案頭のものとなれり、たをり水すすぐくるしみなくして、ながめ、 うたよむたのしみあり、取るにむさぼらず、遇ふにあらそはず、これ述ぶべきなり、おもえば、これただかりそめのたのしみのみ、狃(な)れゆきてこれをつねとなし、山水の大きなるたのしみわするることなからん、石公(袁宏道の号)しるす、およそ瓶のなかのあらゆる品目はのちにかきつらねて、好事者にしてまづしき人々とともにすることとせん、袁宏道」。

『新鐫草本花詩譜』表紙と「朱蘭」 本書より
1章 「花目(はなのしな)」より
燕京(えんけい/北京の古称)は寒さがきびしく、南の珍しい花は手に入れがたい、貧しい儒者にはおよそ無理な話だ。それで手に入れやすいものをよるのだが、それは友を選ぶがごときものだ。山林に逃れた人は友とはしがたい、それで世の人々が名をあげ優れたるものとする花を、私もまた友としようと宏道は述べている。花は友に等しいのである。
3章 器具(うつわ)より
花を養う瓶も優れたものでなければならない。花觚(かこ)、銅觶(どうし)、尊、罍(らい)などの銅器や多種の形態をもつ窯器もみな形のささやかなものが清供に入るだろう。牡丹や芍薬、蓮華などは大きいのでその限りではない。古銅器や陶器で長年土に埋もれていたものは花の色は鮮やかになり、開くこと早く、散ること晩く、瓶にいれたままで実のつくこともあり、花を養うに適していると聞いたことがあるという。瓶の古きを宝とするのは玩(もてあそ)ぶだけのことではないのだが貧しいものには手にはいりにくい。宣、成などの官窯の磁瓶がおのおの一つあれば分限だろうと述べている。

白磁四耳壷 南宋-元 13世紀
東京国立博物館
中国を代表する陶磁器である青磁と白磁は実は、金属器を手本に制作されたものである。白磁は金・銀器の軽快・鋭利を青磁は重厚峻厳な古銅器がモデルでありそれらの焼き物の特質は手本の美質に関わっているという(矢部良明『中国陶磁の八千年』)。この明の時代、官窯は景徳鎮で、皇帝が一代で一つしか年号を使用しなくなったため、年号でその時代の作品を呼ぶようになった。宣、成とは宣徳、成化の時代の作品を指している。宋にはじまり明から清にかけての白磁には青花文と呼ばれた美しい青の絵付けや、五彩といって赤・青・黄・緑・紫などで色彩豊かに彩色されたものが作られるようになる。特に明の第三代皇帝である永楽帝の頃になると、とりわけ絵付けが盛んになった。国外では人気が髙かったが、当時の中国の文人には、染めつけられていない白磁が貴ばれたと言う人もいる。袁宏道がどの磁器を指して官窯の磁瓶と言っているか定かでないが、おそらく宣、成の頃は青花文磁器が主流となっていたことからそれらを指しているのではなかろうか。はっきりしない。

青花人物文瓶 景徳鎮窯 17世紀 明
東京国立博物館
5章 宜称(よろしきにかなふこと)より
ここが、いけ花に直接関わる部分になるだろう。花を挿す時には、繁り過ぎもよくないし痩せ過ぎたのもよくない。多くて二、三色で高くまた低く、まばらに繁く画に描かれたように配置するのがよい。二つの枝の対になること、一律になること、連なること、糸をもってつかねることを忌む。花の整えるとは、長い短いがとりどりにあって、子瞻(したん/蘇軾)の思いの趣くままの文のごとく、青蓮(李白)の対句の法に囚われない詩のごときものである。それは誠に整ったものと言えるとある。
生け花を単なる造形と思っているようではダメらしいのである。ここでまたちょっと寄り道して、唐の時代の白居易の詩である名作『牡丹芳』から一部を抜粋してご紹介したい。唐では、いかに牡丹が好まれたかがよく分かる詩である。

李迪(りてき)『紅白芙蓉図』 1197 南宋
東京国立博物館
白居易『牡丹芳』読み下し
牡丹芳 牡丹芳 黄金の蕊 (ずい) は紅玉の房に綻 (ほころ) び
千片の赤英 (せきえい) は霞のうちに爛爛 (らんらん) 百枝の絳点 (こうてん) に燈 (ひ) は煌煌 (こうこう)
地を照らして初めて開く錦繍 (きんしゅう) の段 まさに風は蘭麝 (らんじゃ) の嚢 (のう) を結ばざるべし
‥‥
衛公 (えいこう) の宅静かにして東院を閉ざし 西明 (さいみょう) 寺深くして北廊を開く
戯蝶 (ぎちょう)双舞して看る人久しく 残鴬 (ざんおう) 一声して春日長し
共に愁ふ 日照らして芳 (ほう) の住 (とど) め難きを 仍ち帷幕 (いばく) を張りて陰涼を垂 (た) る
花開き花落つ二十日 (にじゅうにち) 一城の人皆狂えるが若し‥‥
*
白居易『牡丹芳』 現代語訳
牡丹の芳しき花 牡丹の芳しき花 黄金の花しべは紅玉の花からそっとほころび。
千の赤い花房は霞の内に光り輝いて 百の枝に咲く赤い花はきらきらと燈に光る。
地を照らして錦の刺繍を施した織物のように開け初めて 風は蘭花・麝香 (じゃこう) の匂い袋のような花の口を閉じることがない。
‥‥
衛公の邸宅はひっそりとして東院を閉ざし、 牡丹の名所西明寺の境内は奥深い北の廊下を開け放す。
牡丹の花に戯れ舞う二蝶を人はいつまでも眺め 里に残る鶯の一声が聞こえる春の長きひねもす。
日が照りつけ牡丹の芳香を留めがたいのを人は共に嘆き それで垂れ幕を張って涼しい影を作る。
花が咲き花が散る、その二十日ばかり間 城中の人は皆、牡丹の花に狂うがごとくである。
‥‥
6章 屏俗(いやしきをしりぞくること)より
袁宏道の花にたいする愛情はここに極まっている。花を恋人と置き換えてもすばらしい文章であるだろう。花は日に一度水で濯(すす)がなければならない。「‥‥花によろこびといかりあり、いねたるとさめたるとあり、暁と夕あり、花に水うつに、そのときをうれば、めぐみの雨となるものぞかし、淡雲(うすぐも)、薄日(うすび)、夕のひざし、あかき月かげは花の暁ならむ、ふりすさぶながあめ、もゆる暑さ、きびしき寒さは花の夕ならむ、口紅の日にてりかがやき、うつくしきすがたの風にかくるるは花のよろこべるならむ、何となくこころしづみて、いろかもそこはかとなくおぼつかなきは、花のものおもへるならむ‥‥かくして花の性情(こころ)をよろこばしめ、その起居(たちい)に時をえしむるなり、暁に水うつは上の品なり、ねむれるときに水うつはこれに次ぐ、よろこびあるとき水うつは下の品なり、ものおもひに水うたば、これまことに花に刑(しおき)するのみ‥‥」花に対する愛情はひとかたならないものがあったのだ。
11章 清賞(はなをめずること)より

陳洪綬(ちんこうじゅ/1598-1652)喫茶図 部分
清初 喫茶の場に瓶花が設えられている。
茶を啜りながら花を眺める人は上品、物語しつつながむる人はこれに次ぐ、酒をくみつつながめる人は下の人らしい。花を愛でる「機」とはいったいどういうことかをこの『瓶史』からご紹介して終わろう。「あらゆるいやしくけがらはしきことばは、花神のふかくにくみ、いたくしりぞくるところなれば、むしろ口をつぐみて枯座すとも、花のなやめるに遭ふことのなきこそよけれ、それ花をながむるに、ときあり、ところあり、そのときをえざるに、すずろに客(ひと)を招くは、みなおもひのほかのここちす、寒きころの花は、初雪によろし、‥‥温かきころの花は、晴れたる日によろし、‥‥暑きころの花は、雨ののちによろし、‥‥涼しきころの花はあかき月夜によろし‥‥もし風日をこころかけず、佳きゐどころをえらばざれば、神気はまばらになりて、つひにつらなることなし‥‥」。
それは清少納言の感覚にも似ているのかもしれない‥‥春はあけぼの‥‥夏は夜‥‥秋は夕暮れ‥‥冬はつとめて(早朝)‥‥四季の趣きである。「趣き」とは何か、少し分かった気になったのだが‥‥ついでに言うと、感極まった時にいささかの哀歓を伴って発せられる「あはれ」とは異なる、ある種、おおらかな情趣美がある。
このように何か「ページをめくるようにとりどりにイメージする」ことに特別の意味があると思えるようになったのは最近のことである。それは、ひところ言われた表面を滑るネットサーフィンとか映像におけるカットアップのようにバラバラな画面を次々と見せられる時に生じるような感覚とは異なる。もっと別な次元と関わっているように思えるのだけれど、なんだろう? これまた、最近のことだがロベルト・カラッソというイタリアの作家で編集者の作品『カドモスとハルモニアの結婚』を読んでハタと思ったのである。これは心の深みに落ちていくための技法なのではなかろうか。これについてはこれからも色々と考えてみたいと思っている。ちょっと思わせぶりで恐縮だが、またの機会があればご紹介するつもりである。


宋代の林洪の『山家清事』、陳槱(ちんゆう)の『負喧野録』、趙希鵠の『洞天清祿集』が収載されている。
『山家清事』の「山家の備品」の章には、深い山中には嵐気があり、それに犯されると仙家の修行もできないので生姜を植えて毎朝、皮つきのまま細かく嚙み砕いて熟酒で飲むか、生姜湯を飲むのが良いと書いている。
『負喧野録』は主に書に関する記述で、古碑の文字、篆書、近世の書体、書の学び方などについて記述がある。
蘭亭序は鼠鬚筆を用い、烏絲欄 (縦横の界線を織り込んだ) のある繭紙 (絹帛を使った紙) に書いたもので、布屑で紙を作ることは今の蜀箋でもやっている。この紙は水にぬれると厚いので凹みができるが、薄いものは高級品と言っていい。蘇州・呉門の孫生は春膏紙を作るのが上手く、それで、こんな詩を作った。
しっとりと雨に濡れたようなつややかさのうちにも
竹紙で作られたせいかどことなく品のよいところがある
夜の砧に幾たびとなく打たれて
晴の机の上につやつやと飾られる
越の地方に産したものではあるが
呉へ来て立派なものとして褒め称えらせれた
名の知られることの遅かったのはともかくとして
これがあれば学問も盛んにすることができるであろう
(中田勇次郎 訳)
『洞天清祿集』
宋代に発展した文房清玩の最もまとまった書といわれる。古琴の鑑別、古硯の鑑別、古鐘鼎彝 (い) 器、怪石・名石、硯屏(硯の傍に立てる衝立)、筆、墨、古今の石刻、古画といった鑑別法が記されている。
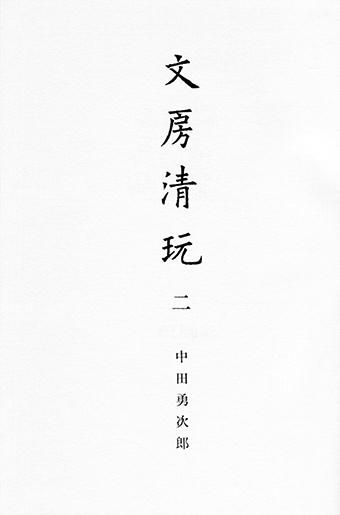
屠隆『考槃餘事』収録
明代の文房清玩のための概説書。屠隆は放縦な性格だったが、名士と交わり風流才子の誉高く、文章は闊達であったと言われる。内容は明の高濂 (こうれん)の養生集である遵生八牋(じゅんせいはっせん)と宋の趙希鵠の文房に関する洞天清祿集などを編纂した性格が強いと言われる。紙、硯、墨、琴、香、茶道具、盆花、瓶花、文房具などの記述がある。
この書が流布した頃は日本の桃山時代に千利休らによる茶の湯が盛んになった頃で、その風習が一方では書斎から、一方では茶室からというふうな差はあれ、類似した側面を持っている中田さんは指摘している。
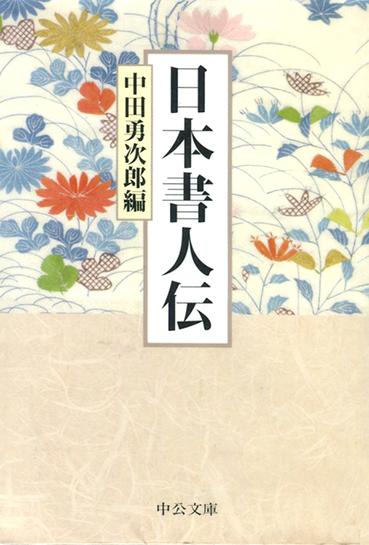
中田勇次郎さんが編集した『日本書人伝』
山本健吉「聖徳太子・聖武天皇・光明皇后」
司馬遼太郎「空海」
永井路子「最澄・嵯峨天皇・橘逸勢」
寺田透「小野道風・藤原佐里」
白洲正子「藤原行成」
中村真一郎「西行・藤原俊成・藤原定家」
唐木順三「大燈国師・一休宗純」
花田清輝「本阿弥光悦」
辻邦夫「池大雅」
良寛「水上勉」
中田勇次郎「貫名菘翁」
というラインナップになっている。池大雅が書家として名を馳せていることは知らなかった。彼の書の中で徐渭(じょい)の詩を彼の書体を真似て書いているのではないかと思われる作品があるので掲載しておく。

池大雅 書「徐渭 雪牡丹」の詩『日本書人伝』より転載

中田勇次郎さんが編集した『中国書人伝』
中国の名書家たちの作品に関する様々な人の著作を集めている。僕の知らなかった色々な名筆たちの紹介があり、有難い著作だ。
取り分け貝塚茂樹さんの「王義之・王献之」は王義之の素顔を垣間見せてくれる。加藤楸邨さんの「唐太宗」、井上靖さんの「顔真卿、柳公権」など興味深い内容がある。祝允明、文徴明、董其昌らの書もなかなか素晴らしい。

洛陽牡丹記 欧陽脩 宋
陳州牡丹記 張邦基 宋
天彭牡丹記 陸 游 宋
揚州芍薬記 王 観 宋
范村梅譜 范成大 宋
范村菊譜 范成大 宋
金漳蘭譜 趙時庚 宋
王氏蘭譜 王貴学 宋
瓶花譜 張謙徳 明
瓶史 袁宏道 明
学圃雑疏 王晴懋 明
花鏡 陳湨子 清
以上収載
園芸のノウハウものとしては『花鏡/課花十八法』が面白い。筆者の陳湨子 (ちん こうし) は明末の生まれで清の時代には官吏とならず田園に帰り、花草果木の栽培に従事した。『花鏡』を著したのは1688 (康熙27) 年と言われる。花の性情の識別法、植え付け、株分け、接ぎ木、植え替え、虫退治の方法などが述べられる。
その中から「花香耐久法/花の香を長持ちさせる方法」をご紹介する。
昔の人は「花つくりに一年、花を看るのはわずか10日」と言ったけれど、花の香りや色艶が長続きしないのは取り分け残念なことである。それで長続きさせる方法を紹介すると言う。基本的には蕾を漬物にするのだけれど、これは、ちょっとマジカルなやり方になっている。
梅は冬に竹の小刀で梅のちょうど開こうとしている蕾を切り取り、蝋に浸して尊や甕の中に投げ入れ、夏になったら杯の中に湯をいれて蝋に浸した蕾を入れてかき混ぜると蕾はほころびはじめ、香りも続く。ソヨゴ (冬青) の実を搗いて汁を取り、木犀 (桂) の半ば開いたものを入れて攪拌し、磁瓶に入れ厚紙で覆いをし、花のない時に部屋の中で水盤に活けると香を楽しむことができる。あるいは、木犀の花を塩水に浸して貯蔵しておくと、色・香は元のままである。菊、ハマナス (玫瑰/まいかい) 、ジャスミン (茉莉) 、金粟蘭 (ちゃらん/珍珠蘭) の半ば開いた蕾を摘んで四割の茶葉、一割の花の割合で茶葉と花を交互に缶や甕に一杯まで収める。紙と竹の皮で包んで茹で、冷えたものを取って別に紙に包み、火の上で炙って乾かして焙茶とするなどの記述がある。


ハマナス (玫瑰/まいかい) ピンクの花

金粟蘭 (ちゃらん)
花と地下茎から精油がとれ、薬として用いられこともある。香り付けに花や葉をお茶に入れたりする。












コメント