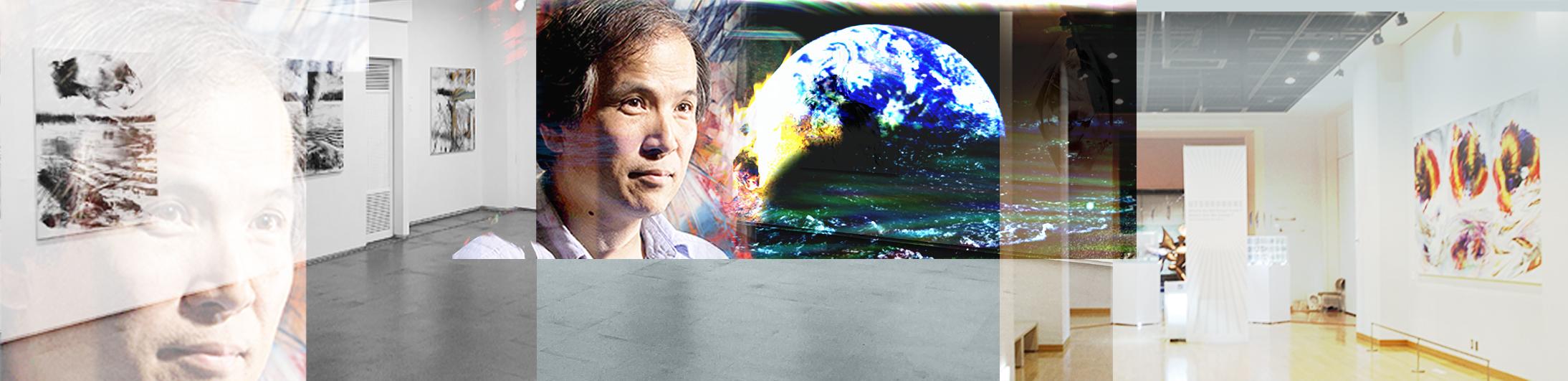Art of Combination

Op. 2 蜻蛉
2011 130cm×97cm
EV-2
購入について/Regarding Perchase

Op. 3 蝶
2011 130cm×97cm
EV-3
購入について/Regarding Perchase

Op.4 空蝉
2011 73cm×60.5cm
EV-4
購入について/Regarding Perchase

Op.5 蝶
2011 73cm×60.5cm
EV-5
購入について/Regarding Perchase

Op.7 石と昆虫
2011-12 194cm×392cm
EV-7
購入について/Regarding Perchase

Op. 6 蜻蛉
2011-12 65cm×53cm
EV-6
購入について/Regarding Perchase

Op. 8 蝶
2011-12 65cm×53cm
EV-8
購入について/Regarding Perchase

Op. 9 蝶
2011-2023 117cm×117cm
EV-9
購入について/Regarding Perchase
Production materials/制作素材
基底材 綿キャンバスに和紙 アクリル下地
* パネルに紙 アクリル下地
絵具 オリジナル絵具(天然樹脂、油、蜜蝋)油彩
Original paint (made from resin, oil and beewax), Oil, Acryl
Japanese paper on cotton
*Paper on panel
Empty Vessel/宇津保舟
2011-2012 神の乗る舟 ― 宇津保舟 ―
宇津保は、空洞を意味する言葉で、空の入れ物を宇津保舟と云いった。民族学・国文学の大学者である折口信夫(おりぐち しのぶ)さんは『霊魂の話』の中でこのように述べている。「日本の神々の話には、中には大きな神の出現する話もないではないが、其よりも小さい神の出現に就いて、説かれたものゝ方が多い。此らの神々は、大抵ものゝ中に這入つて来る。其容れ物がうつぼ舟である。ひさごのやうに、人工的につめをしたものでなく、中がうつろになったものである。此に蓋があると考へたのは、後世の事である。書物で見られるもので、此代表的な神は、すくなひこなである。此神は、適切にたまと言ふものを思はす。即、おほくにぬしの外来魂の名が、此すくなひこなの形で示されたのだとも見られる。此神は、かゞみの舟に乗つて来た。さゝぎの皮衣を着て来たともあり、ひとり虫の衣を着て来たともあり、鵝或は蛾の字が宛てられて居る。かゞみはぱんやの実だとも言はれるが、とにかく、中のうつろなものに乗つて来たのであらう。嘗て柳田国男先生は、波荒い海中を乗り切つて来た神であるから、恐らく潜航艇のやうなものを想像したのだらうと言れた。」

この宇津保舟は虚(うつろ)舟と記されるようになり江戸時代にはUFO伝説を思わせる奇談も伝わった。『兎園小説』(1825年刊行/江戸の文人や好事家の集まりの会で語られた奇談・怪談を、曲亭馬琴がまとめたもの)に『虚舟の蛮女』との題で図版とともに収録され今に知られている。昭和になって今度は、澁澤龍彦さんが同名の小説を書いた。今回、私はこの宇津保舟をテーマに選んだ。この中空の乗り物をテーマに小さな生き物たちや海に生きるものたちの表象を結合しながら霊的な乗り物のとしてのイメージを描いたのである。
『神は細部に宿り給う。』 図像学の泰斗 アビ・ヴァ-ルブルクの引用した言葉として知られているが、日本の古来には、神は、空虚なものに宿り給うと考えられていた。それが、かいこ(たまご)、ひさご、うつぼ舟であるのだが、さきの折口信夫さんの『霊魂の話』にそいながらこれらに関連したことを述べてみよう。
まず、日本の神は「たま」と呼ばれていた。それは、抽象的なもので、時あって姿を現すものと考えられていた。卵の古い言葉は、かひである。密封していて穴のあいてないものがよかった。その容れものにどこからか入ってくるものがある。たまである。その虚ろなものの中で或る期間過ごすと、そのかひを破って中に這入っていたものが出現する。すなわち「ある」(現れるの原形)状態を示す、「みあれ」=エピファニー(神の顕現)である。それが「なる」つまり、生まれることだと折口さんは、強調する。日本人は、ものの発生する姿には、原則三段階の順序を考えていた。外からやって来るものがあり、それが或る期間ものの中に這入っており、やがて出現してこの世の形をとるのである。かぐや姫は、竹の節と節の間から生まれ、桃太郎は桃から生まれ、聖徳太子に仕えた秦ノ河勝は、蓋のついた壺の中に這入って三輪川を下ってきた。しかし、植物、とりわけ日本人に最も馴染みのある稲のことを考えると、この三段階が分かりやすいかもしれない。この場合、よそから人知れず入って来るものは稲魂であろう。そして、なかに這入ってじっとしていることは、日本神道の中で最も大切にされていた「ものいみ」と深い関連があるのだという。神事に与るには、或る期間山に籠らなければならないし、天皇にとって重要な行事である大嘗会(だいじょうえ)は、真床覆衾(まとこおうふすま)、つまり蒲団のようなものを被ってじっとしていることである。ものが「なる」為には、じっとして居なければならぬ時期があるという考え方なのである。また、姿をなさない他界のものは、姿をなすまでの期間が必要なのだという意味合いもあるだろうと考えられた。
ところで、石にも「たま」は宿る。石に入ってやって来る。おまけにその石が旅行したり成長するという多くの伝承が残っているのである。どういう訳かは、折口さんにも分からいようであるが、石のような、中に空間のないものにも「たま」は籠るのである。その中で神は成長し、石が割れて「みあれ」すると考えられていた。石の中で成長する部分だけが強調されて石が大きくなるという伝承になったのだという。たまが神という言葉に翻訳された後は、神が石になると信じられた。
ヨーロッパでも石には、不思議な現象が起こることが色々記録されている。『幻想の中世』を書いたバルトルシャイティスは、『アベラシオン』(国書刊行会)の中で石の中の不思議な図像について紹介している(図1,2)。


上 左 J.カロによる版画 1691 右 A.キルヒャーの著作の挿絵 1664
下 A.-J.デザリエ・ダルジャンヴィルによる著作の挿絵 1755 石の中に現れた形象
石には、不思議な形が宿るのである。図2の上は、キリスト生誕の地ベツレヘムの洞窟にある聖ヒエロニムスの姿とある。何故このような形を石が生み出すのか?トマス・アクイナスの師であり同じドミニコ会士であったアルベルトゥス・マグヌスは、アリストテレスの『自然学』の注釈書でも知られ、普遍博士と呼ばれた人である。そのマグヌスが、13世紀に形態の生成に関する理論を残していた。その中で「場は何ものかであり、またそれはある一定の潜勢力(dynamis)を持つ」というアリストテレスの考えに基づいて、場を『産出の能動的原理』と名づけているのである。複雑系の科学で言われる「場所の論理」や標準理論で言われる「ヒッグス場の変質」などちょっとクセのある場について話題が、最近の科学ではけっこうあるが今はおいておこう。場は、形象、形態をそこに存在させるだけではなく、それらを形成する力、物を造り、それに作用し構成することのできる力を持つとマグヌスは結論づけた。物質の潜勢力、自らを形態として起てようとする物質の欲求が現れるのは場においてである。場や地には聖なるものの潜在的作用があるとした。石は、場によって働きかけられその形をつくりだすのである。場に働きかける力は天に由来する。このマグヌスと、時代は隔たるが同じドミニコ会士であったフラ・アンジェリコとの関係を述べた著作がG・ディディ・ユベルマンの『フラ・アンジェリコ 神秘神学と絵画表現』(平凡社)である。ユベルマンはマグヌスのこの考えとアンジェリコの受胎告知の絵画表現とを重ね合わせた。天ー場の形成力ー物質、この関係を、天の御言葉ー神の子の受容器としてのマリア ーキリストという関係に対比させたのである。ルカ福音書ではイエスの誕生の予告が、お告げの天使ガブリエルによってこう述べられている。「聖霊があなたに降り、いと高き方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。‥‥」天からの意図が、受容器としての場の力を起動し、意図されたものが生みだされる。
さて、たまは天なるものである。後に神と呼ばれる。それはある空虚な場所に宿り、籠る。そしてある時期を経て成長し、みあれする。誕生するのである。空虚な場所は、必ずしも空洞を意味しない。何故なら石のようなものにもたまは、宿るからである。そうすると、この空虚な場所は、たまや霊の籠れる場所としか言いようがない。石は霊の宿れる場所なのである。翡翠で作られた小さな曲がりをつけた石が勾玉と呼ばれるのもこの縁であるのかもしれない。石の中に入るのはたまだけではなく、人間も入る。山伏の行のなかにはそのようなものも残っているようである。『霊魂の話』の最後のあたりで折口さんは、若者になるためには(成人と云いかえてもよいと思うけれども)、石や石室につめたり、山の中に塗りこめたりする事が行われたという。山籠もりは禁欲生活を意味するだけでない。一度自然界のものの中に入ってこなければならなかった(自然のものは、たまや神の受容器であった)。それをしなければ、人にもなれなかったのだというのである。ひとは、人になるために自然に籠った。それは、魂が育つのと同じことであり、他界から来るたまを受けるのであって、そうすることによって村の聖なる為事にさずかる者の資格が与えられたのである。
最近、蝶や蜻蛉などの昆虫に注意が惹かれる。比較的自然の残っているところに住んでいるから少し気をつけているとすぐに目にできる。しかし、蜻蛉などはかつてのように群舞する姿はもう見られない。彼らの姿が愛おしいからとも云えるが、彼らの役割とは何なのだろうとよく思うのである。食物連鎖の一つなどという答えは論外である。福島の原発で汚染された地域にいても非難勧告は彼らにはだされない。でも今は環境破壊や汚染のバロメーターとしての役割のことではない。彼らのいわば霊的役割とでもいったらよいだろうか、それは何なのだろうかと考えるのである。蝶の羽は、鱗粉と呼ばれるキューティクルの鱗状の組織で覆われており、これは上皮細胞が強くキチン化(カニの甲羅のようになること)して死に、ソケット状の孔から容易に離脱できるようになったものである。いわば華麗なる微細な甲冑を経帷子として彼等は輪舞する。蜻蛉の翅も、キチン質でできている。背中の外骨格が薄く伸びたもので、膜状に広がった翅を支えるために、太くなったキチン質の筋が葉脈のように翅に広がる。これを翅脈と言う。翅脈は羽化する時、翅を伸ばすために体液を流すところでもあるという。蜻蛉は葉のように薄く引き伸ばした甲冑を眼に見えないほどに空に同化させて飛ぶ。蝶たちは身を守る道具を空への憧れのために捨てた。それほどまでに天に向かって彼らは何を携えようとするのだろうか?宇津保舟のような彼らがそこに乗せて運ぼうとしている魂とは何なのか?彼等の中で成長して、みあれする存在とはなんであろうか?もはや空に憧れない人間には、答えは得られず、彼等への嫉妬しか残らないのかもしれない。
青いとんぼ
青いとんぼの眼をみれば
緑の、銀の、エメロード。
青いとんぼの薄き翅
燈心草の穂に光る。
青いとんぼの飛びゆくは
魔法つかひの手練(てだれ)かな。
青いとんぼを捕ふれば
女役者の肌ざはり。
青いとんぼの綺麗さは
手に触(さわ)るすら恐ろしく、
青いとんぼの落つきは
眼にねたきまで憎々し。
青いとんぼをきりきりと
夏の雪駄で踏みつぶす
北原白秋 「思ひ出」より
2013年5月