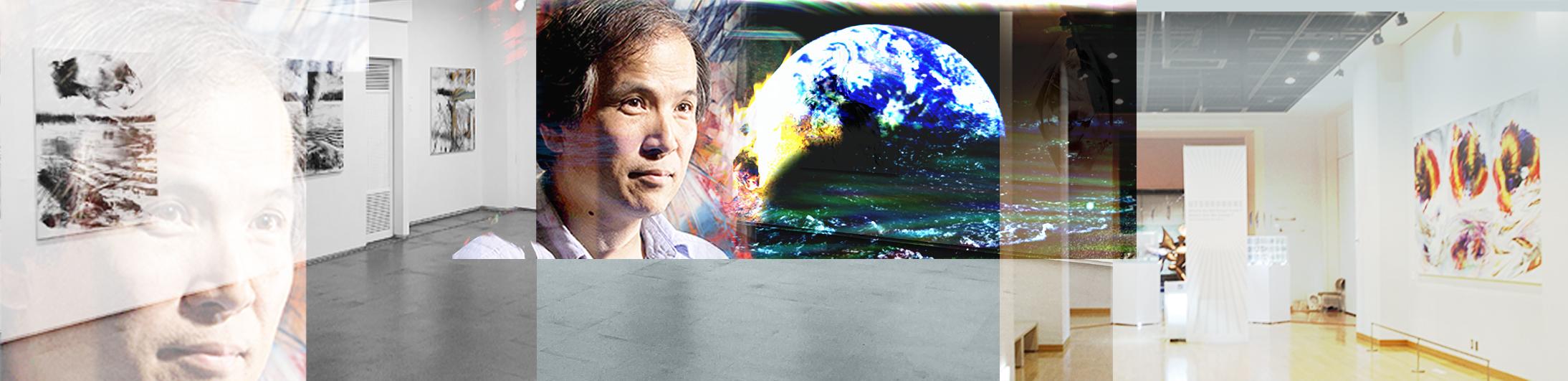Art of Combination

Op.1 The Moon
2010
117cm×117cm
IA-1
Private Collection

Op.2 The Moon
2010 130cm× 97cm
IA-2
購入について/Regarding Perchase

Op.3 The Moon
2010 65cm× 53cm
IA-3
購入について/Regarding Perchase

Op.4
2010 53cm× 45.5cm
IA-4
購入について/Regarding Perchase

Op.6
2010 65cm×53cm
AI-6
購入について/Regarding Perchase

Op.7 Little Boy, Little Girl
2010 -2011 194cm×392cm
AI-7
購入について/Regarding Perchase

Op.5
2010 65cm×53cm
AI-5
購入について/Regarding Perchase

Op.9 Fire
2010-2011 130cm×97cm
AI-9
購入について/Regarding Perchase

Op.12
2011-2018 73cm×51.5cm
AI-12
購入について/Regarding Perchase

Op.14 Dog
2011 53cm×45.5cm
AI-14
購入について/Regarding Perchase

Op.15
2011 51.5cm×36.5cm
AI-15
購入について/Regarding Perchase
Production materials/制作素材
基底材 綿キャンバスに和紙 アクリル下地
* パネルに紙 アクリル下地
絵具 オリジナル絵具(天然樹脂、油、蜜蝋)油彩
Original paint (made from resin, oil and beewax), Oil, Acryl
Japanese paper on cotton
*Paper on panel
岡本太郎生誕100年記念展 『虚舟 私たちは何処から来て、何処へ行くのか?』
岡本太郎美術館/川崎
“UTUROBUNE where do we comefrom? where are you going?
Taro Okamoto art museum/Kawasaki


Image and the Art of Combination/表象と結合術
2010-2011 表象は、鏡の中を泳ぐ。
モナドにはモナドには、窓がないとライプニッツは、書いたけれども、こう言い換えたほうがすっきりするのではないだろうか。モナドの全表面は、窓である。それは、絶えず襞を生成しながら宇宙を映し出す表象劇場である。一方、モナドは、身体を持つ。それは、絶えず流動するエレメントによって構成されるが、この宇宙流体の中では、現象は変転し、アナモルフォーズ(歪像)されて正確な表れ方をしない。それをリアルにつかむ視点を持つこと。一望に見渡すことのできるパースペクティブの中で見てとること。結合術は、言葉や数や絵を単に結びつけるのではなく、『一望に見て取る』ことに結合させるのである。
ホルスト・ブレーデカンプの著書『モナドの窓』を一部要約すると上のようになる。彼のような図像学者たちのご意見は、さて置くとして、今回は、表象と結合術とに焦点を当ててみた。モナドは、昨年からのテーマではあるが、今回それらがどのように結合されたかをご覧いただければと思っている。
シンメトリーという言葉があるが、形態学や形の科学などでは、よく取り上げられる。そのシンメトリーを形成する最もポピューラーな現象が鏡像である。例えば、正方形を描いた紙を左に置き、その右側に同じ正方形を描いた同じ紙を置けば、左右はシンメトリーな形体である。右の正方形と左の正方形とは、簡単に重ね合わせることができる。同じ紙を右に置かなくても左に置いた紙の隣に鏡を置くとシンメトリーな像ができる。説明するまでもないだろう。でも、正方形ならいいが、左右対称でない形体の場合(図版1)、左の図形は、右の図形に重ね合わせることができない。

もし、これが二次元上の出来事だと仮定すると(どんな薄い紙でも厚みは、あるのだから三次元だとフラーなら言いそうだが)この左の図形を右の図形に重ね合わせるには、いったん三次元の世界に出て裏表を逆にしなければ重ね合わせることは不可能になる。しかし、鏡を置くことができれば、簡単にシンメトリーを作ることができる。鏡は、次元を一つ超えてカイラリティーの反転をイメージさせる装置である。
ここで、これに関連した、ちょっと面白い指摘をご紹介しよう。ルドルフ・シュタイナーが『四次元』というタイトルの講義の中で語ったことである。三次元の物体である手袋について考えてみる。左手の手袋を左側に置き、右手の手袋を右側に置く。さて、左手の手袋を右手の手袋に重ね合わせるには、どうすればよいか?答えは、一度、四次元の世界に出て重ね合わせるのである。四次元で手袋の表裏が反転(インヴァージョン)するのだろう。ただの類推ではあるが、類推とは、実は人間にとって偉大な武器なのではないだろうか。シュタイナーは、さらに続けてこう述べている。右手の手袋と左の手袋を重ね合わせるのと同じような関係が、外的世界と私たちの印象の間にもあるのではないか。物体と鏡の像のように、これらを直接的連続的に一致させるためには、新しい次元が必要なのではないかというのである。私たちは、この鏡に写る像について海を漂うような意識の流れの中で表象しているが、心の中でそれらの像を記憶像と重ねあわせることができる。このことは、純粋に観念的ではあるが、何か三次元を超えた、それにもかかわらず現実性をもった何かへと私たちを至らしめるという。それからもう一つ。自然の中のねじれについて。例えば、太陽のまわりの地球の運動、そして地球のまわりの月の運動をとりあげてみよう。月は、地球の周囲を円運動しているといわれるが、実は地球の軌道にそってねじれた線、つまり螺旋として運動している。太陽自体も宇宙空間を高速で運動していることを考えれば、地球も月と同じように太陽の周囲を螺旋運動していることになる。天体は、空間の中を広がっている非常に複雑な線上を運動していることがお分かりいただけるだろう(図版2)。

バックミンスター・フラーによる図を模写
これを頭の中でイメージすることは、かなり困難なことである。このようなれじれの関係を考えるのに相応しいのが、メビウスの環なのだ。ただ単純に環にした帯を真ん中にそって切ると二つの環ができる。しかし、テープの帯の端を一度ねじって貼ったもの(裏と表が結合される)、つまりメビウスの環を同じように切ると一本のねじれた環になる。テープの端を二度ねじって貼った環を切ると二つのメビウスの環が鎖のようにつながったものができる。そして、三度ねじって貼ったものを切ると結び目のようなこぶができる(図版3)。このようなねじれた空間構造は、特別な力を持っているのだが、自然の中では天体の運動とおなじようにいたる所でねじれが生じている。四次元空間との関連で三次元空間の特質を考えるのに最適なケースが、この結び目のある環と二次元の帯との関係であるという。そして、このような複雑さは、三次元特有のもので、四次元空間では生じないと指摘しているが、このあたりは、ちょっと謎である。


モナドに窓があるのかないのか。これも謎である。ライプニッツ自身が、モナドロジーと銘うったテキストの中で「モナドには、窓がない。」とはっきり書いているのだから他人が、とやかく言う必要はなかろうと思うが、昔から色々論議があるようだ。『人間知性新論』は、ライプニッツの名を世に知らしめた著作で、すでに高名であったロックの思想を代弁するフィラレートと自らの主張を代弁するテオフィルとの対話形式で書れている。その第一章の中でもライプニッツは、テオフィルに魂に窓があるとか、書付板に似ているとか、蝋のようだという人たちは、魂を物体的なものにしてしまっていると語らせている。魂は、モナドが霊的に進化した知性ある存在である。しかし、同じテキストの12章で、知性は真っ暗な小部屋にかなり似ていて、その小部屋には外部の可視的な像が外から入れる小さな入り口があるだけだというフィラレートの説に付け加えるかたちで、その小部屋の暗室には形を受けとめる幕があって、その幕はたいらでなく、生得的知識を表わす襞によって変化がつけられているとテオフィルに語らせている。これがいけない。これは、明らかに窓の存在を前提にしていることになりはしないか?『襞』を書いたジル・ドゥルーズもこの前提に依拠してモナドは二階立てだと解釈したのではなかろうかと想像するのだが、いかがなものか(ドゥルーズのモナド論については「三声のモナド -佐藤慶次郎の思い出に-」をご覧ください)。ただ、モナドも純然たる霊的存在では、表象することは困難なのだから、このような比喩としてのイメージは、許されるのだろう。ここは、上述のブレーデカンプの意見にも耳をかそうではないか。
ライプニッツには、生涯興味を失うことなく飽くなき追求を続けていたことがいくつかある。その中の一つが、「自然と人工の劇場」である。めくるめく驚異が集結された部屋の実現こそ彼の意欲をつのらせるものだった。コレクションすることが、つなぐと組み合わせることであることに気づかせ、その過程で生じるアナロジーというメタファー思考があらゆる思考の中で最も優位に立つことをバーバラ・スタフォードに確信させたのがライプニッツの思想であったこともゆえないことではない。彼女は、あらゆる知識がバラバラに切り刻まれて破片だけの流れのようになってしまった現代の状況を憂い、新たな知の創発にビジュアルな手法が不可欠だと考える。その著書『ビジュアル・アナロジー』の中で、彼女は、ライプニッツの存在論は美学と合して、個と個を超えるものにハイパーリンクさせるところの、還元しないで繋げる一つの巨大プログラムを形成する力を持つと言わしめている。その存在論の基盤には、流体宇宙という考え方があることは、ここで指摘しておかなければならない。この宇宙では、すべてが繋がっているのである。
ライプニッツの考え方には、いたるところで「無限」が顔をだすようである。世界には、無数の事物が存在する。庭園の植物の間にある地面や空気、池の魚の間にある水には、我々には見えない微細な生き物で満ちている。そのように宇宙には、存在が無数にあって数え切れない。しかし、それらは、連続律によって統一的に把握される可能性を持つ。同じは、違わないのではなく、無限に小さい差異や変化であるという発想なのである。静止は、無限小の運動なのである。運動の変化率をみる微分やその逆演算である積分が生まれるゆえんである。すべては、連続するのだ。


さきほどの地球や月のように、宇宙に存在する物体を連続する運動の線と表象するなら、世界は、乱流のように見えてくる。このことは、「織り込まれる流れ運動」の中で述べておいたことだが、パースの宇宙論を紹介した「出現と運動」のなかでもふれておいた。この乱流のような世界を巧みに絵画にした図像を紹介しておく(図版4)。全てが四次元の中を泳いでいるのなら、世界はこのように見えはしないか。ルネサンス以来、発達を遂げた線遠近法は、このような図像を生み出す可能性をもたらした。17世紀には、四角な格子を扇形に変形して図中の点をプロットしていくことによって作図できる円筒形のアナモルフォーズも制作されるようになった(図版5)。

J.F.ニスロンの図像を模写
円筒形の鏡をその扇形の根元に置けば、四角な格子に描かれていたもとの正常な形態を映し出すことができる。直方体に色々の角度で光を当てれば、その根元には、様々に投影された形態が生まれる。側面投影を伴う遠近法的な影の形である。それに対して、歪みも変形もない平面図は、たった一つしかない。それと同じように、図4のような宇宙流体の中でアナモルフォーズされたイメージも正確に把握できるある一つの視点が存在するとライプニッツは考えていた。歪みなき神の遠近法の視点は、人間が視の科学をつうじて獲得しなければならないものだったのである。さて、最後にカラヴァジオのナルキッソスの絵を見ていただきたいと思う(図版6)。

ギリシア神話をテーマにこの絵画は、描かれている。暗い水面に映る自らの姿に見ほれているナルキッソスの様子は、けっしてナルシズムに浸って夢見るような姿で描かれているのではなく、何か定かでないものを魅入られたように見つめる姿に描かれている。違う世界にきっとある、今の自分ではない別の自分の姿。探しているのは、きっと一つ次元を超えて現れる自分の姿なのだ。目の前にあるのは、流体である水の表面であることは、忘れてはならない。その鏡のような水面は、少しでも表面に触れれば、たちまちアナモルフォーズされたカオスの世界に変幻してしまう危うさを秘めている。確かに水面に映った美しい人の姿は、流れるような記憶表象の中で、やはり確かに記憶像と結びつくのだ。現在では、脳の中でのこのような活動にカオス理論が重要な役割を果たしていることが明らかになりつつある。私と、異次元と、流れるような宇宙と記憶表象。ここにあるのは、異次元を見つめる視の探求者の姿なのかもしれない。
2011年 5月