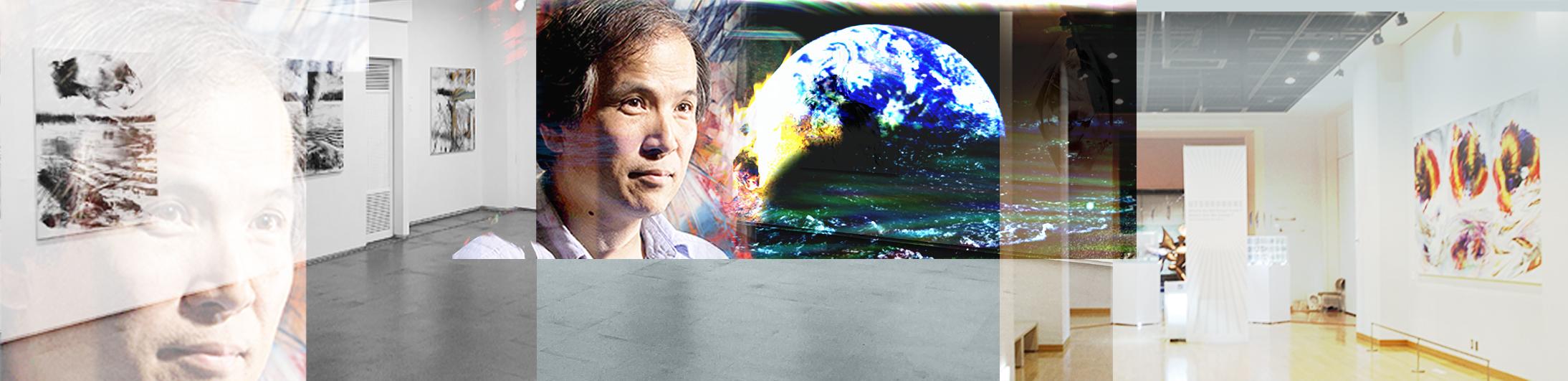Non-Linear Modern

Op.1*
2008 60cm×50cm
EM-1
購入について/Regarding Perchase

Op.2*
2008 73cm×51.5cm
EM-2
購入について/Regarding Perchase

Op.4
2008 194cm ×392cm
EM-4
購入について/Regarding Perchase

Op.5
2008 194cm ×392cm
EM–5
購入について/Regarding Perchase

Op.6*
2008 73cm×51.5cm
EM-6 Private Collection

Op.7
2008-2022 162cm×162cm
EM-7
購入について/Regarding Perchase

Op.8*
2008 73cm×51.5cm
EM-8
購入について/Regarding Perchase

Op.13*
2008 73cm×51.5cm
EM-13
購入について/Regarding Perchase

Op.9*
2008 73cm×51.5cm
EM-9
購入について/Regarding Perchase

Op.10*
2009 51.5cm×73cm
EM-10
購入について/Regarding Perchase

Op.11*
2009 73cm×51.5cm
EM-11
購入について/Regarding Perchase
Production materials/制作素材
基底材 綿キャンバスに和紙 アクリル下地
* パネルに紙 アクリル下地
絵具 オリジナル絵具(天然樹脂、油、蜜蝋)油彩
Original paint (made from resin, oil and beewax), Oil, Acryl
Japanese paper on cotton
*Paper on panel
Emergence and Movement/出現と運動
2008-2009 全ての事物は、連続体の中を泳いでいる。チャールズ・パースの宇宙論によせて。
チャールズ・パース(1839-1914)の宇宙論 ( 伊藤邦武著 岩波書店)を読んで驚いた。パースのことは、松岡正剛さんのサイト「千夜千冊」を読んで知っていたし、かなり強い印象も残っていたが、その先進性には脱帽である。パースによれば、世界は、三つのカテゴリーよりなる。この結論は、射影幾何学をもとに導きだされているのだが、この幾何学の祖ともいわれるデザルグの定理が発想のもとになっている。射影幾何学のことは乱流の結晶学で少し触れておいた。しかし、より重要なことは命題をグラフによって表すことによってその結合の仕方を調べたことだ。著者の伊藤邦武さんによれば●が命題の述語を表し、― が主語や目的語などを表す。結合の腕は、下の図1のようにいくつも出すことができる(図1)。例えば、左から 「Xは、赤い」が単項関係の命題、二番目は, 「Xは,Yを愛する」 という二項関係の命題を表すとする。三番目は、「Aは、BにCを与える」 となる。以下四、五‥‥項関係の命題を表す。


この時、三番目までの例では、文を二つに分けると命題をなさない文章ができてしまう。しかし、四項関係の命題では、「AがBにCをDの重さで売る」 というような命題になるのだが、「Aは、Bと取引をする」、これをEとすれば、Eは、「AがCをDの重さで売る」と 「BがCをDの重さで買う」 という二つの事実に分けることができる。一般に四項関係以上では、命題を分割することが可能である。これをグラフで示すと図2のようになり、空いた手同士は、自由に握手できる。この ―で表される他との繋がりのない空いた手を価数すなわちNと呼ぶが、一般に価数が四以上のとき(N―2)×3=Nという奇妙な式が成り立つ。ここから三つのカテゴリーが必要で、かつ充分であるという結論が生まれるという。ライプニッツが数で命題を表そうとしたのはよく知られているが、パースは、グラフも用いた。多様な可能性を追求しているのである。
パースの宇宙では、三つのカテゴリーの組み合わせで満ち満ちている。第一は、無限に多様な質の差異を持ち、強烈な意識のみが支配する全てがカオスの世界である。その無数の偶然的な生起は、確率統計的に一般化することができ、それにしたがって擬似的決定論的世界が現れ、新しい習慣や規則が形成される。それは、このような図で示す事ができるという(図3)。 無数の線がある形態のネガをつくりあげる。 これも射影幾何学である。

この第一の世界は、複数の異なった閃光から生じ、それらからの流れは、互いに共時性とか先後の継起性とかを持たない。つまり、多宇宙論なのである。そして、それらの多宇宙では、第一の世界から生じたこの習慣や規則が第二の世界を形成することになる。この第二の世界では、数学的な厳密さをもつ「連続性」によって除々に形成され、進化発展する。そこは、習慣の法則、観念連合の法則、一般化の法則が支配する世界であり、やがて全ての偶然性は駆逐され、精神性は追いやられて真の物質世界が形成されていくのだという。
パースにとって、この世の全てのものは、それぞれの仕方で、滑らかな連続性のなかを泳いでいる。彼は、この「連続性」が「哲学の秘密(アルカナ)」を解く鍵であるというのだ。例えば直線は、点の無数の連続的な繋がりとして考えられるが、その線を切ったときその切り口は点なのか?もし、点と点の間を切り離すことができるのなら隙間がすでに存在することになり、その直線は、有限個の点でできていることになる。ライプニッツも悩ませたこの問題は、深刻な「迷宮」だったのである。この問題を解決するためにパースは、アリストテレスの言う線を作る点は「線を連続させるとともに、これを限定区分しもする。点は、長さの部分の始めであるとともに、他の部分の終わりでもある。」という考え方をとる。この考え方からすると、点は自分の分身を作るらしい。なんだか忍者みたいだ。ルール違反のような気もするのだが、線の端っこは、魔法のようにいくつもの点が飛び出すことができ、それらの点は、分裂(破裂)の前には一点であったというのである。一つの点は、0と1の間の存在する無理数のようなものとして考えているのだ(超準解析の無限小の概念を思わせるといわれている)。線上の点は、切断によって複数の点にもなり、その点は、そのものの内に無限小の隔たりを持つ無数の部分点、つまりモナドを持つのである。反対に複数の点がその順序を保ちながら元の点に戻ると考える。直線上のそれぞれの点の集合は、もはや確定性をもたない一切の可能的な点を無尽蔵に包含した集合であり、互いに溶け合うように見える「可能性の全宇宙」なのである。でも、ちょっと謎ではある。

アンリ・ミショー(1899-1984) というフランスの詩人がいた。「みじめな奇蹟」という詩集が有名である。メスカリンなどの薬物を服用して自分の意識の変化の様子を克明に詩画集にしたことで一世を風靡した。でもそれは、惨めな奇蹟だったのである。通常の意識ではない意識の中では何が起こるのか?ちょっと甘い誘惑がそこにはある。だが、はっきり言っておきたいのだが、こういった意識は人間の意識を進化の方向には導かない。シャーマンのような先祖帰り的な意識をとりもどしたいのなら話は、別である。ともあれ、ミショーの絵の中で私達は、通常の意識が作用しない、意識のある部分を垣間見ることになる。そこでは、何か無数の点や線がうごめきながらスケーリングを伴って律動しているようである。このスケーリングを伴う律動については、「風を蒔いて旋風を刈る」で少し述べておいた。
2007年に東京国立近代美術館でミショーの展覧会が開かれた。その時カタログの替わりに 「アンリ・ミショー ひとのかたち」 (みすず書房)という本が出版されてちょっと嬉しかったのを憶えている。この本の帯には、このように書かれている。「すべては、ムーヴマンである。 ‥‥奔流となって流れ出すエネルギー、無垢なるイマージュ、そのなかからあらわれる怪物、亡霊、そして 『ひとのかたち』‥‥」 そのなかからあらわれるかたちにぞっこん魅入られたある有名な東京の画廊のオーナーを私は、知っている。ミショーは、書いている。「かたちの動きはわたしの動きになっていた。動きが多くなるほどわたしはより存在し、より多くの動きを求めた。そうすることで、わたしは、全くの他者となり、わたしの身体に侵入した。わたしは、ギャロップする馬に乗り、馬と一体化する時のようにわたしの身体と一体化していた。すばやくリズミカルにわたしのところにやって来たこれらのかたちに引っ張られて、わたしは動きに所有されていた。」 お気づきだろうか? 異様にわたしという言葉が多いのを。運動に同一化していく自分を見失うまいとしているようにさえ思える。イメージの奔流に流されまいとする自己、その流れが少しゆるまった時、ひとの顔が現れるのだと言う。しかし、今は、顔よりもこのイメージの奔流(図版1)のかたちに注目したい。繰り返される一連の流れ、沸き立つようなディテール。スケーリングを伴う相似形の律動とも、先のパースのいう無限に増殖する点で構成された線ともいえる形。きっと私たちの意識の隠れた部分では、なんらかのカオスアトラクターのようなものが存在しているのではないか。それらのダイナミズムが形態を次々と生み出すのではないだろうか?わたしは、そのように考えている。このことについては、是非「原形態」を読んでいただいて併せてお考えいただければと思う。
原初のカオスは、無数の感覚的「ゆらぎ」と変化し連続する流れであった。この連続する流れは、数学的な「連続性」という無尽蔵の本性を持ち、種々の法則を展開しながら多元的宇宙を生成する。そして、それぞれの宇宙は、目的論的性格をもつことによって完全で調和的な体系を実現すべく進化を続ける。チャールズ・パースの思弁的宇宙論は、かなり大雑把に言って、このようなものであった。この宇宙論には、連続する流れという観点からすればデヴィッド・ボームの「全体流動」を思わせるものがあるし、アレキサンダ-・ビレンキンの多宇宙論、確率論的に擬似決定的世界が現れるという観点からすれば、自己組織化や量子論的な宇宙論などを髣髴とさせる内容がある。そこからライプニッツのいう真の無限との関連や、あるいは、内容的には隔たりはあるものの重畳無尽の蓮華蔵世界を類推することさえ不可能ではない。変化し連続するこの世界の背後には、根源的なカオスアトラクターのような性格の運動があるのではないか?この連続体のそれぞれの点の背後には小さなアトラクターのようなものがあって世界を形作っていくのではないだろうか?このところ、よくそんなことを思うのである。上に述べたそれぞれの世界観や科学理論がパースの宇宙論の背後に透けて見えるのは、このアトラクターの軌跡の一部をそっと彼が撫でてみせてくれたからではないだろうか? あと少しでその姿を捕まえることができると思えることもあるが、たいていは、無限に遠いと気落ちしてしまう。明日はもう少し近くに行けるのかもしれない。でも、わからない。
2009年 6月