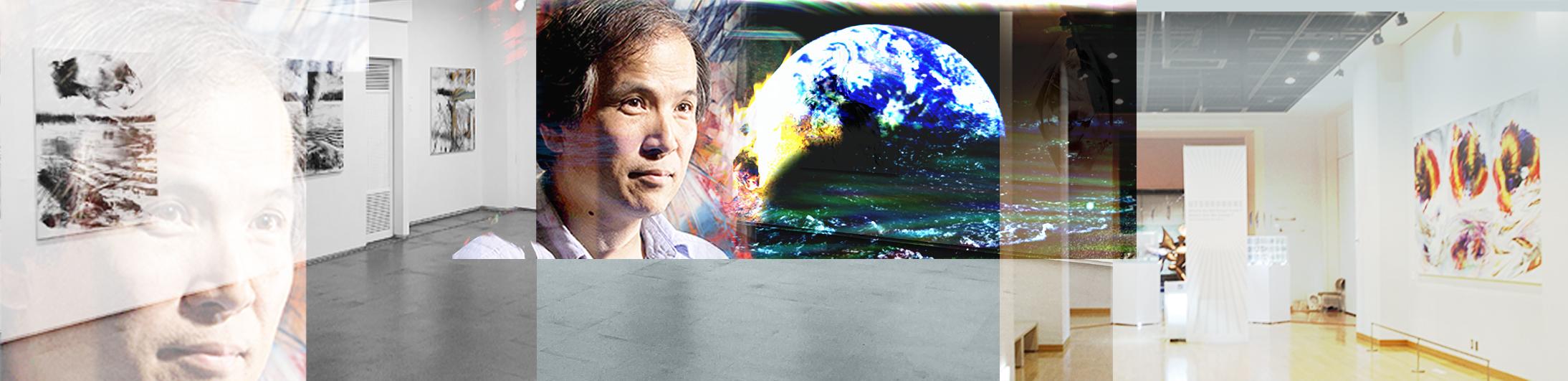Non-Linear Modern

Op.12*
1997 53cm×45.5cm
OP-12
購入について/Regarding Purchase

Op.3*
1997 73cm×51.5cm
OP-3
購入について/Regarding Purchase

Op.21*
1998 73cm×103cm
OP-21
購入について/Regarding Purchase

Op.1*
1997 73cm×51.5cm
OP-1
購入について/Regarding Purchase

Op.15
1997-1998 194cm×163cm
OP-15
購入について/Regarding Purchase

Op.11*
1997 73cm×51.5cm
OP-11
購入について/Regarding Purchase

Op.16
1997-2022 194cm×194cm
OP-16
購入について/Regarding Purchase

Op.5*
1997 73cm×51.5cm
OP-5
購入について/Regarding Purchase

Op.14
1997-1998 163cm×582cm
OP-14
購入について/Regarding Purchase

Op.4
1997-1998 162cm×162cm
OP-4
購入について/Regarding Purchase

small works Op.1*
1997 44cm×36.5cm
OPS-1
購入について/Regarding Purchase

small works Op.2*
1997 44cm×36.5cm
OPS-2
購入について/Regarding Purchase
Production materials/制作素材
基底材 綿キャンバスに和紙 アクリル下地
* パネルに紙 アクリル下地
絵具 オリジナル絵具(天然樹脂、油、蜜蝋)油彩
Original paint (made from resin, oil and beewax), Oil, Acryl
Japanese paper on cotton
*Paper on panel
Opsis-Physis/光輝と質料
1997-1998 色彩とは何か?
ひかりはたもち その電燈は失はれ‥
私の最初の画集『自己組織化するカオス 植田信隆作品集1996-1997』を出版するにあたってシュタイナーの研究者である佐藤公俊(さとう きみとし)さんに文章を書いてもらったことがある。その中に宮澤賢治の詩「春と修羅 第一集」の有名な冒頭が引用されてあった。それが晴れやかで嬉しかったのを憶えている。当時は、ゲーテの科学観に興味を持ちはじめた時期で、形態論(原形態を参照してください)やモナド論(三声のモナドを参照してください)など私にとって重要な思想を見つけていた時期だったように思う。その中に、ゲーテの色彩論があった。ゲーテは、勿論ながら詩人、小説家であったが、同時に形態学や、植物学、とりわけ色彩学を熱心に研究したことでも有名である。佐藤さんは、色彩論との関連で宮澤賢治の詩「春と修羅 第一集」の有名な冒頭を引用したのである。
わたしという現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる幽霊の複合体)
風景やみんなといっしょに
せわしくせわしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち その電燈は失はれ)
‥‥‥
この詩は、賢治の仏教的縁起についての解釈が込められているようで、私にとってはとても大切な箇所なのだが、この「光輝と質料」というシリーズを描いていた時にもこの詩が念頭にあったのである。
有機交流電燈、青い照明、明滅、因果交流電燈、このような光と色の世界に相応しい色彩論は、勿論ゲーテのそれであった。ゲーテは、ニュートンの色彩論に強く抗議した。彼にとって色彩は、光と闇による相互作用によって生じるのであって、ニュートンのいうような光の粒子という物質の振る舞いではなかった。要素と要素の間の関係性こそが重要であって、その関係性の中に変わることのない自然の姿が写し出された時、はじめてその普遍的な相を人間は理解する。ゲーテは、このような象徴的な自然の姿を根本現象といった。彼にとって感覚によって把握される現象の中にこそ真理があるのであって、現象の背後にある法則は単なる抽象的な概念に過ぎなかった。では、その根本現象(原現象)とは具体的にどのようなものだったのだろうか?
ゲーテは、長らく借りっ放しにして使わなかったプリズムを返さなければならなくなった時、軽い気持ちでそれを手に取って覗いた。しかし、ニュートンの言うように白い壁には、虹色なんて現れなかった。窓の暗い格子に色が現れているのみだった。ニュートンは、間違っている。そうゲーテは、確信したのであるが、それは、誤解だった。部屋は、暗室でもなかったし、小さな穴から光が注がれていたわけでもなかったからである。しかし、その誤った確信からこの美しい色彩論は、生まれたのである。この時、彼は、色彩は光と闇の相互作用から生じることを理解した。アリストテレスの立場に戻ったのである。私達は、晴れ上がった空に紺青を見、夕闇の背後の夕焼けに真紅を見る。その現象を、ゲーテのこの説明から納得することができる。「闇を背後にくもった媒質を通してものを見る時、その部分は、青く見える。くもったガラス板を何枚か重ねてそこに差し込む光を見ると、その板の枚数によって明るい黄色から深紅までを見ることができる(「色彩論」工作舎)。」
これが、根本現象である。ゲーテの色彩論を継承したルドルフ・シュタイナーの言い方では、もっと端的になる。光を通して見た闇は青く見え、闇を通して見た光は赤く見える。」 このことは、プリズムを使った実験で確認することが出来る。白地に黒の長方形をプリズムを通して見る。すると暗い境界が明るい地のほうへ進入して(図版1)、前方には幅の広い黄色の前縁が、前縁と境界の間に幅の狭い橙色の縁が現れる。

長方形の幅が狭いと最下段のように左右の色は、結合して、結合部に赤や緑が現れる。

光を反射する白地に闇である黒地の像が、かぶって黄から赤味を帯びるからである。逆に、黒地に白の長方形をプリズムで見ると、明るい境界が暗い地のほうに進入して(図版2)、前方に幅の広い紫の前縁が、その後ろに幅の狭い青色の縁が現れる。黒地の闇に白地の明るさを伴った媒質が、かぶって青みを帯びるのである。
このプリズムから現れた色の帯を繋げてみるともう一つの大切な事を見い出す。ゲーテの色相環(図版3)である。


黄色は、拡張する色であり、青は、後退する色である。この二色は、色彩の根源的な対立を示している。黄色から橙が高昇し、青から紫が高昇する。その高昇した対立が結合して真紅が出来上がる。ここにもゲーテの対立と高昇がみられる。この六角形の180°反対側同士の色は、補色になっている。ゲーテが、その色彩論の中で述べている生理的補色のみごとな関係がここに図示されている。強い黄色をしばらく眺めた後、白い壁に目を移すと紫の淡い色が見える。他の対になった色同士も同様である。 シュタイナーは、若い頃「ゲーテ自然科学論集」の編集にあたった。その中でゲーテの方法論を自分のものにした。しかし、ゲーテが自然の背後にある一般には、不可視のものをあえて語らなかったのに対して、シュタイナーは、積極的だった。
誤解しないでいただきたい、自然の背後にある不可視のものとは、科学のいう自然法則のことではない。自然を前にしてその感覚を研ぎ澄ませていく中で現れる通常の感覚をさえ越えて得られる認識のことである。それは、量的認識ではなく微妙な質的認識なのである。ゲーテは、感覚が誤るのでない、判断が誤るのだと言った。この言葉は、感覚器官が進化するものだという文脈の中で読み取られてこそ、大きな意味を発揮するのである。多くの芸術家たちが、シュタイナーの思想に影響を受けた。カンディンスキー、モンドリアン、クレー、ブル-ノ・ワルター、ヨーゼフ・ボイス、みんなそうだったのである。
そのシュタイナーの色彩論は、当然ながらゲーテの表現を踏み越えるものだった。ゲーテにとって、色彩は、光と闇が織り成す自然現象と人間の目との間で起こる。シュタイナーにとって、色彩は、精神と魂の映像だった(図版4)。

黒 死せるものの霊的
緑 生命の死せる像
淡紅色 魂の生ける像
白 精神の魂的な姿

そのような色彩が、重要だったのである。淡紅色は、桃の花のような活きいきとした生命的なものの像であり、その生命的なものは、死を通して緑を形成する。顔色が緑色になれば人間は、病気だと判断できるように。また、明るい光の中、白色の中で人間は自我感情を強める。その中で精神は、心魂的なものの中に現れでる。闇の暗さの中では、世界を疎遠なものとして感じる。黒は、死者の霊的な姿として感じられると言うのである。赤は、生命的なものの輝きであり、黄色は、精神の内的な働きかけを魂が受け入れた時に輝きだす色彩である。逆に魂が外の世界から離れ内部で完結する時、青は、輝きだす(「色彩の秘密」イザラ書房)。シュタイナーの色彩論では、色彩は内的なものの姿として描かれるのである。それは、自由に漂いだす色彩、物の表面の色ではなく、空の青のような、インクの色のようなティンクトゥールと呼ばれる物の表面から浮き上がった色彩である。
最後に、シュタイナーの壮大な光と闇のヴィジョンを紹介してこの論を閉じようと思う。ここで、私達は、より高次の色彩に思い至るかもしれない。シュタイナーは、こう語った。「宇宙は、光に貫かれており、この光の中に思考は、生きている。思考に貫かれた光の中で思考は、死にゆく。それゆえ光は、過去から輝いてくる思考のオーラである。一方、未来の萌芽は、物質の力の中に横たわる闇の中にある。物質とは、意志であり、その中で「出現しはじめる世界」が明らかになる。この過去から到来した思考という光と未来へ移行していく物質の意志としての闇が織り成す所、それが現在である。」と。
賢治が、人間を何故有機交流電燈や因果交流電燈に喩えたのか?そこに現れる光や色とは何であるのか? この光と闇の相克を踏まえることができた時、私達は、より深い理解に達することができはしないだろうか。宮澤賢治は、農民芸術論綱要の中で、「誰もみな芸術家たる感受をなせ」、「まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう」と朋友に呼びかける。そして、「われらに要るものは銀河を包む透明な意志 巨きな力と熱である」と言い、「われらの前途は輝きながら険峻である」としている。
賢治の場合、輝くもの、道を照らすものは諸法の光であったはずである。そこにあるべき「大きな力と熱を湛えた銀河を包む透明な意志」が輝くものに拮抗して交わらなければならない。我らは、諸縁によって現じた幽霊のような色身である。そこに未来を描くためには、透明な意志と巨大な力と熱とを必要とするのである。 しかし、何故、思考は、過去からやって来て、未来の萌芽は、物質の中にあるのか?それを知るためには、地球というシステムの過去を知る必要がある。今回は、ここまでにしておこう。
2009年 4月