「人類とは、我らが惑星の高次の感覚、この星を上なる世界に結びつける神経、地球が天を仰ぎ見る眼なのだ。」(ノヴァーリス『断章あるいは思考的課題』 202)
「私たちは至るところで制約なきものを探すが、見出すのはつねに物でしかない (『花粉』1) 」
失われてゆく超越的なもの、精神性、この状況を認識した時、ノヴァーリスは、この「ない」ではなく「あるべきだ」を要請した。失われた「世界の意味」を見出すために「世界はロマン化されなければならない」、そして、「万物と万物との関り合い」もまた回復されるべきである。ノヴァーリスは自らの課題をこのように心の中に打ち立てた。それは、「魔術という未来のシェーマ」を実現することだった。

ノヴァーリス(1772-1801)1799
ノヴァーリスは初期ドイツロマン主義の極めて重要な作家である。このロマン主義の「ロマン」とは、もともと、「ローマ帝国の(支配階級、知識階級ではなく)庶民の文化に端を発する」という意味であるらしい。ローマ帝国も末期になると文語として使われる古典ラテン語と口語としての俗ラテン語とは著しい違いが生じ始めていた。俗ラテン語は、ロマン語と呼ばれ、そのロマン語で書かれた庶民のための文学がロマンスだったのである。ノヴァ―リスの時代には異なる文脈の中で注目されたのである。
さて、今回の夜稿百話は、中井章子(なかい あやこ)さんの著書、『ノヴァーリスと自然神秘思想』を中心にご紹介する。この本も極めてよくできた本だ。中井さんは、シェリング、ヴァイゲル、ノヴァーリス、ベーメ、ゲーテなどの研究者であられるようだ。薔薇十字なども研究テーマであるらしい。魅力的だ。本書は、第一部「超越と自然」、第二部「自然学」、第三部「詩学」という三部構成になっている。章立ては欄外に書いておいた。本文中の特に注記のないノヴァーリスの引用は中井さんの訳である。

中井章子
『ノヴァーリスと自然神秘思想』
ノヴァーリス、本名はフリードリヒ・フォン・ハルデンベルク。ペンネームのノヴァーリスは、ラテン語では「新たな開墾地」を意味するらしいけれどドイツ語では小説ほどの意味のようだ。ザクセン選帝侯の貴族の家柄で、ドイツ中部から少し北東よりにあるザクセン州のオーバーヴィーダーシュテット村で生まれた。11人兄弟の長男、二番目の子だった。父親は、ボヘミアから迫害されて逃れてきた先鋭的なフス派を中心としたボヘミア兄弟団をドイツに受け入れた敬虔派のヘルンフート同胞団のメンバーだったと言われる (『日記・花粉』アウグスト・ツェレスティーン・ユスト「ノヴァーリス伝」) 。
ツィツェンドルフが主宰した、このヘルンフート同胞団は、ルター派の内的な心情に宗教の本質を見る厳格な敬虔主義であり、その家庭に育つことになる。このことは、ノヴァーリスの思想を形成する上で大きかったのではないかと思われる。彼の著作にツィツェンドルフとベーメの名が共に登場するのは偶然ではない。ちなみにメゾシスト運動を主催したジョン・ウェスレーは、アメリカ行きの船の中で、このボヘミア兄弟団の宣教師から大きな影響を受けたと言われる。


左 オーヴァーヴィーダーシュテットのドルフ教会
右 ノヴァリースの生家 オーバーヴィ―ダ―シュテット城
元は修道院として建てられた建物である。
ボヘミア兄弟団の元来の理想は、「霊感は始原的過去に汲みつつ、未来へのヴィジョンを提出する」もので、「現存の教会をとるか〈来るべき教会〉をとるかという一信仰箇条を超えた選択を迫る(R.J.W.エヴァンズ『魔術の帝国 ― ルドルフ二世とその世界 ― 』中野春夫 訳)」というものだった。ハルデンベルク (ノヴァーリス) が対決しようとしていたのは、現存の教会ではなく、柔軟な思考を失い硬直化した啓蒙主義であり、〈来るべき教会〉とは「ロマン化された世界」に置き換えられる。そのためには「心に働きかける魔法」、すなわち霊感が必要とされた。
「心に働きかける魔法」とは三十年戦争 (1618-1648) によって崩壊する前の神聖ローマ帝国、とりわけボヘミアやプファルツなどドイツ地方を中心に浸透していた薔薇十字、ヘルメス主義と錬金術、それに1570年から半世紀ほどの間に頂点に達したといわれているパラケルスス思想であり、その残照である。ノヴァーリスは、それを「熱狂」というプロテスタントの異端派を指す言葉に集約させていく (中井章子『ノヴァーリスと自然神秘思想』)。同時に、それはシュトルム・ウント・ドラングなどの文学運動に連動していくものだった。

(1772-1829) 1810

(1759-1805)
父方の伯父のもとで一年ほど過ごして、広い知識を持ち聡明で善良な人たちの知己を得た後、1790年にイェーナ大学で学ぶが、そこでは学生時代にノヴァーリスの父親から援助を受けていたフィヒテが、カント哲学を継承・発展させていた。イェーナはゲーテを中心とした文化都市で、ノヴァーリスが最も親しかったのはイェーナ大学の歴史教授のシラーだったといわれる。ロマン派は概してシラーと不仲だったと言うが、彼は例外だった。「つねに全体の中心に身を置いて、自らの個体を類的存在に高めること(『人間の美的教育について』書簡2 )」が芸術的使命として提唱されている。それはノヴァーリスの課題ともなったのである。
この地は、やがてドイツロマン主義の一大センターになる。翌年、ライプツッヒ大学に移った際に生涯の友となるフリードリヒ・シュレーゲルと出合っている。法律を学ぶためにウィッテンベルク大学へと移り1794年に大学を終了した。

現在のドイツと関連都市
ロマン主義
18世紀には情念のロマン主義が興るといわれるが、ここでノヴァーリスの「ロマン化」についてもう少し詳しく述べておこう。ノヴァーリスのいうロマン化は二段階ある。第一段は自己の高次化である。「自我」の反省の運動、すなわち「有限的自我」が「絶対的自我」の自己定立をめざしていく無限の運動であり、相乗級数のように自らを高めることだった。私の意識を捉え、対象化するためには一段高い意識が必要とされ、その高い意識を捉えるためには、もっと高い意識が必要とされるのである。それをフィヒテは、主体としての自己は自己を対象として自覚するのではなく「知的直観」によって直接的に自覚するとした。いささか苦しい説明になっている。ノヴァーリスは「自己の知的直観を神的なものの直接的体験」としてフィヒテの哲学を拡大解釈し、直接体験できるのはガイスト (精神) の働きによるとする。それはノヴァーリスにとって愛の行為と等しかった。
第二段階は、「ありふれたものに神秘的な外面を与える」という「表現」行為である。複雑で不規則なものを単純で規則的なものに還元する対数化と言ってよい。この道の先達としてゲーテが考えられていて、人間の感覚を損なわない形で行われる自然の観察と認識に基づくプレグナントな表現と言ったらよいだろう。フィヒテの観念論を相補するものとしてのゲーテの自然哲学があった。
自己を高め、対象を神秘化できる表現を与えること。このようにして平凡なものと高貴なもの、有限と無限、ありふれたものと神秘なもの、既知と未知、此岸と彼岸、物と精神は結びつけられる。対立的なものを融合・昇華させること、これが「ロマン化」である。例えば、詩人となってありふれた世界を言葉で神秘化するということはロマン化の実践となる。ポエジー化するとはすなわち、その語源ポイエインが示す通り創造行為となるのである。
ゾフィーの死
ウィッテンベルク大学で法律の勉学を終えたノヴァーリスは、ウィッテンベルクで法律の実務を学ぶことになる。その出張旅行の途中でゾフィー・フォン・キューンという名の13歳の少女に出会った。そして、ザクセンの製塩所が修練期の場所となりイェーナにほど近いランゲンザルツァの著名な化学者であるウィークレープに製塩学を学んでいる。ノヴァーリスは愛する女性を神聖視し、恋愛を宗教的なものと考える傾向があった。恋愛は「熱狂」の一形態であったのだ。しかし、両親にも好意を持たれたゾフィーも儚く早世してしまう。この頃、最愛の弟エラスムスも重篤で、やがて亡くなった。
「彼女は死んだ――だから、僕も死ぬ――世界は寂漠としている。哲学の研究でさえも、もはや僕を妨げることがあってはならない。深い、あかるい静けさのなかで、僕は僕を呼ぶ最後の瞬間を待とう (『日記』1797年6月13日 前田敬作 訳 ) 。
身も世もない様子だった。
「彼女を現世から解放した見えない手が、僕をも解きはなってくれるのだ。僕たちの婚礼は、この世のために結ばれたのではなかった (『日記』1797年6月14日 同上) 。」
ある日、苦い涙にくれ、望みも苦悩に溶けはて、悲惨さそのものとなってゾフィーの塚のまえ佇んでいた。その時、光の枷という臍の緒が一瞬にして断たれ、憂愁と夜の恍惚がこの新たな世界に、注ぎ込まれた。あたり一帯が、そっと持ち上がり、新たな霊が解き放たれ、塚は塵の雲となり、そこを透かして恋人の浄化された姿が見える。目に永遠を宿したその人の手を取った‥‥
1897年5月13日ノヴァーリスは、ゾフィーの墓の前で名状しがたい喜悦に襲われ、彼女接近がまざまざと感じられたと日記に書き残している。これが、いわゆるエクスターゼ/エクスタシス (脱自) 体験であったかどうかは分からない。しかし、それが上に要約した『夜の賛歌』の第三歌となったと言われる。

ゾフィー・フォン・キューンの記念銘板
グリュニンゲン 詩人の花嫁と銘うたれている
ノヴァーリスにとって、これらの不幸は「本来的な自己」取り戻す契機となる。「僕は全てに喜んで耐えなくてはならない」と述べ、スピノザとツィツェンドルフは愛の無限のイデーを探求し、花の雄蕊にとまって愛のために自己を実現する方法を予感していたが、フィヒテには、それがないと思う。人間は孤絶した存在ではなく、他者と出合い、「愛」において繋がり「他者」との相互的な関係の中で自己を実現する。個人は全体に包まれた存在だというのである。
魔術的自然
『‥‥彼は服を脱いで池にはいった。あたかも、一片の夕焼雲が彼を包んで流れているかのような気持ちだった。彼は天にも昇る心地に満ち溢れた。数知れぬ思いが、快楽にうずきながら彼の中で混ざり合おうとしていた。新しい、見たこともない像が生じてきて、それらも互いにひとつに溶け合い、目に見えるものの姿となって彼を取り巻いた。そして、快い水の一波一波は、まるで乙女の胸のように、優しく彼にまつわった。豊かに溢れる池水は優美な乙女たちの溶液で、それが若者の体に触れると、刹那に元の乙女の体に戻るかと思われた。』(ノヴァーリス 『青い花』 薗田宗人+今泉文子 訳)
これがノヴァーリスのいう魔術的自然についての描写ではないだろうか。この波は、オウィディウスの『変身物語』に登場するヘルマフロディトゥスに絡むニンフのサルマキスの様を彷彿とさせる。彼にとって身体は機械のような固体ではなく連合体ないし連続体である。夕焼雲は水に、溶液のような波は乙女の胸になり、様々な像がひとつに融けあう。人間に限らず「すべてのものは鎖の環」のひとつひとつであった。液体や気体のようなガイスト(霊=精神)もまた連続体である。この連続体の環の一つが変化すればその変化は他の環を変化させる。ガイストは、本来風が思いのまま吹くように、何処から来て何処へ行くか分からない何ものかであった (ヨハネ福音書三・八) 。思考はガイスト (精神) の働きであり、ガイストから発展する観念論とは、様々な力ないし気体の論理であるという (中井章子『ノヴァーリスと自然神秘思想』) 。
このような記述もある。『世界は、凝結させられた思考である。何かが固められると、思考が解放され――何かが溶解すると思考が凝結する。』 思考と世界は相互に交換する二つの極だった。そして、『空間は滞る時間であり、時間は流れ去る空間である。』時空でさえ相互に変化する。これが、魔術的自然である。

講壇に立つヨハン・ゴットリィープ・フィヒテ
(1762-1814)
フィヒテの哲学の影響を受けて、ノヴァーリスは「世界はガイストの顕れである」とみ、『世界は精神の宇宙的比喩―その象徴である』と述べる(『テプリッツ断章』82)。しかし、近世の精神は、物の中から追い出され、硬直した「精神」となってしまったと彼は考えた。それに、ノヴァーリスにとってプラトンの云う「存在の大いなる連鎖」は既にちぎれていたのである。それでは、何故全ては繋がっていて、その鎖はちぎれてしまったのだろう? それを知るためには世界の成り立ちを考えなければならない。
新プラトン主義とベーメ
ベーメは「無としての神」の自己を掴みたいとする意志、それが、ガイストだと述べた。ガイストなくして世界は顕れないのである。そうノヴァーリスも考えている。ところが、ノヴァーリスにとっての神のイメージは根源的なところでベーメのそれとは異なっていた。すでに、ルネサンス以来、ヨーロッパにおいて重要な思想となっていたヘルメス主義と新プラトン主義に彼は影響された。ボードレール、ランボー、マラルメ、ジョイス、ブルトンらに影響を及ぼしたエリファス・レヴィ (1810-1875) は、「目に見えるものは、目にみえないものの発現である。あるいは、表現を変えれば、完全な言は目に見えるし、感知もしえない物事と正確につり合って存在している」と述べているという (今泉文子『鏡の中のロマン主義』) 。
ヘルメス学は、古代エジプトのオシリス神の書記にして言葉と文字の発明者トート神が伝えたとされる至高の学であり、世界万有の本質とその根源を解き明かし、全宇宙の始原から発する運命を秩序づけ表現しようとするものであった。それは、生気論・化生論的世界観を持つと同時にミクロコスモス=マクロコスモスとは照応しているとし、特に天体の作用力とその操作が可能だとする主張に特色がある。
新プラトン主義では、世界は神的なもの、つまり「一者から流出する」。したがって、すべては連続している。まず、「一なるもの」の周りに同心円状の層があらわれる。第一層としての「第一の知性」がある。第二層は「英知的な世界霊魂」という精神界、第三層は「天の魂」と呼ばれる星辰世界、この三つの実在する世界に対して、それらが質料をまとった仮象としての第四層が「月より下の感覚的世界の魂」、つまり元素界である。それぞれの層は上位の層の写像であり、鏡のように互いを映しあっていて、それを脱自の中の観照から体得するとされる。ここにも高次の世界と低次の世界との照応がある。

『統合する自然 芸術的イメージの鏡像』
ロバート・フラッドによる世界霊魂 1617
一方、ベーメにとって、無としての神は「永遠の自然」を自己から生み出すが、それは神自身から独立した存在であった。そして、神の意志は、なおも世界の完成に向かって今も働き続けていて、世界創造は現在もなお進行中である。新プラトン主義では存在の連鎖を辿ることによって本源に回帰することができる。ベーメには時間の矢があり、ノヴァーリスには時間の矢がない。ドイツロマン主義を代表する画家、カスパー・ダヴィッド・フリードリヒが好んで後向きの人物を描くのは象徴的である。射影幾何学のように過去は未来へと反転するのである。


カスパー・ダヴィッド・フリードリヒ(1774-1840)
ベーメの影響が多大だったのは自然の中に見られるガイストのしるし(シグナトゥール)という考え方の方だった。「神が人間になりうるのであるならば、石や植物や動物やエレメント(地水火風の四大)にもなることができる。そして、このように救済が続けられているのかもしれない」とノヴァーリスはいう。自然には神のしるしが刻印されているはずだし、また、そうなってないはずはなかった。自然は道徳的になるべきであり、そのためには神との絆が不可欠だった。それを作り出せるのは人間だったのであり、それを作り出すことを魔術と呼んだ。
すでにパラケルススやベーメは「神に従う自然学者」としての人間をマグス(魔術師)と等しいものと考えていた。ヘレニズム時代のアレキサンドリアで栄えたヘルメス自然哲学は中世ヨーロッパを地下水のように潜行し、ルネサンスの時代に再び思想史の表舞台に登場する。その後に登場したヘルメス的自然学者の中でノヴァーリスが最も興味をかき立てられた人物がパラケルススである。

パラケルスス (1493-1541)
一者からの流出は神的な第一層の次に「天上的知性界」「星辰界」「元素界」という三つの次元があることは既にみた。元素というのは、地・水・火・風の四大元素のことである。彼は心身二元論の代わりに、この三つの次元に対応する「霊的」、「星辰的」、「元素的」体を想定した。とりわけ重要なのは「星辰的」体であった。心身の病は人間の「星のからだ」に働きかけることによっても癒すことができる。流出説で述べたように上位の次元は下位の次元の写像である。したがって「天上的知性、星のからだ」は、あらゆる物体に痕跡と記号を刻印していると考えられた。この記号が、パラケルススの言う「シグナトゥール(しるし)」である。例えば、「植物は全て地の星」であり、その具体的な形や色は、味、香り、薬草としての効力なども含めて、このしるしの顕われであった。
バラの花の赤色に火星の働きを見、ヒマワリの黄色に木星の影響を見る。太陽の力を補助するものは木星であり、花の中に白色と黄色を生み出す。チコリの花の青さは、土星の作用がある。植物の花や緑の葉には太陽の宇宙的力がはたらいていることは言うまでもない。遠い惑星 ― 火星、木星、土星は土中の珪酸質に働きかけ、植物を大きく太くすると言う。太陽、水星、金星、月の働きとは異なる働きがあると言うのである 。ピーター・トムブキンズとクリストファー・バードは『土壌の神秘』という著作の「惑星の力」という章でこのように紹介しているが、この部分はルドルフ・シュタイナーの著述から引いている。そしてこのように締めくくる。地球や宇宙ばかりでなく、それらを構成しているあらゆる物質元素も、ある程度は、生命と知覚力を持っている。

ロバート・フラッド『ありふれた音楽』1617
「四元素」上から火、風、水、地
伝統的な魔術では、全てのものが元は一つのものに由来しており、万物は互いの「共感」や「万物照応」に基づいて成立すると考えられた。しかし、ノヴァーリスにあっては、この関系は、今は存在していないという。人類の長い歴史の中で聖なるものは退潮していったのであり、ノヴァーリスの時代は、それが極まった時代だと彼は考えていた。「世界の意味は失われた」、それを回復するためには黄金時代が取り戻されなければならなかった。ベーメ流にいえばアダムの転落以前の世界を、そして、同時に乙女ソフィアを回復しなければならないのである。それがノヴァーリスの言う「魔術は未来のシェーマ」となるということなのである。この未来は「現在」の中の穴をくぐりぬけて顕われるような未来であった。
ノヴァーリスの学の学
今回はノヴァーリスの「ロマン化」とは何かを、宗教的憧憬、とりわけ神智学や魔術を中心とした神秘主義に関わる事柄を中心にご紹介した。このような背景のもとに18世紀の合理主義や啓蒙主義を批判し、その対抗概念としての「魔術的観念論」を標榜したのである。これによって「学の学」、ひいては「至高の学」を打ち立てようとした。一方で、当時の科学的思考を摂取し、ゲーテ的な象徴によって言葉の錬金術を構成し、同時にライプニッツの結合術についての影響も存在したという。次回 part2 は、それらの事柄をご紹介する予定です。

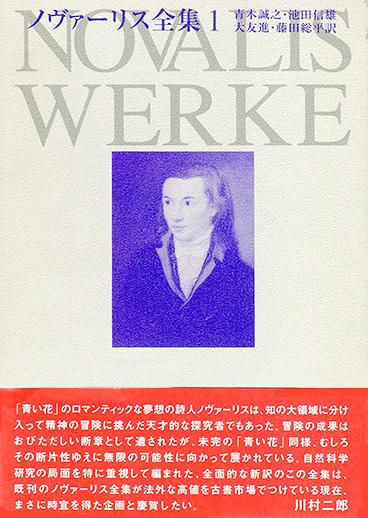
ノヴァーリス全集Ⅰ
青木誠之 池田信雄 大友進 藤田総平 訳
初期詩篇(1788-93年)
ゾフィー詩篇(1794-95年)
フライベルク詩篇(1798-99年)
後期詩篇(1799-1800年)
夜の賛歌(1799-1800年)
讃美歌 (1799-1800年)
さまざまな覚書(1797-1798年)
信仰と愛または王と王妃(1798年)
対話と独白(1798年)
キリスト教またはヨーロッパ(1799年)

ノヴァーリス全集Ⅱ
青木誠之 池田信雄 大友進 藤田総平 訳
断章と研究 (1797年まで)
断章と研究 (1798年)
フライベルク自然科学研究 (1798-99年)
一般草稿集(1798-99年)
断章と研究 (1799-1800年)

『ノヴァ―リス 青い花 ザイスの弟子たち』
薗田宗人+今泉文子 訳
青い花
青い花への遺稿
ザイスの弟子たち
雑録集

『日記・花粉』 前田敬作 訳
日記
遠乗りの記
覚書一
クラリッセ
覚書二
メモ日記への書入れ
断想
ゾフィーの死後の日記
エラスムスによせて
覚書三
覚書四
カロリーネ姉の婚礼の日に
日誌
より高き生活術の修行時代 心情形成の研究
花粉
ノヴァーリス伝

中井章子『ノヴァーリスと自然神秘思想』
中井章子(なかい あやこ)さんの著書、『ノヴァーリスと自然神秘思想』。この本も極めてよくできた本である。中井さんは、シェリング、ヴァイゲル、ノヴァーリス、ベーメ、ゲーテなどの研究者であられるようだ。薔薇十字なども研究テーマであるらしい。魅力的だ。本書は、第一部「超越と自然」、第二部「自然学」、第三部「詩学」という三部構成になっている。章立てをご紹介しておく。
第一部 超越と自然
第一章「ノヴァーリスの誕生」
1「熱狂の擁護」
2 体験と哲学
第二章 ガイストの顕現としてのこの世界
1 「制約なきもの」と「物」
2 エクスターゼと知的直観
3 「ガイスト」の運動
4 神性への媒介者 ―― 宗教
5 表象 ―― 哲学
6 森羅万象の相互表象説と新プラトン主義的な世界像 ―― 自然学
第三章 世界の意味の喪失と回復
1 世界の意味の喪失
2 黄金時代
3 回復の方法 ―― ロマン化
4 伝統との関わり
第二部 自然学
第四章 マクロコスモスとミクロコスモス ―― 自然と人間 ――
1 マクロコスモスとミクロコスモス
2 自然と人間
3 自然の救い
4 自然とわざの愛の関係
5 魔術師としての人間
第五章 魔術
1 魔術師への興味
2 魔術と観念論哲学の重ね合わせ
3 「未来へのシェーマ」としての魔術
第六章 万物の共感の学
1 伝統のなかの共感の学
2 カルヴァニズム、電気、磁気
3 ブラウン医学
4 動物磁気
5 「ラヴォワジェの革命をこえるもの」
第七章 しるしの学――しるし・記号・象徴――
1 自然神秘思想の伝統における「シグナトゥール」
2 近世の記号の学
3 自然の文献学としての自然学
4 しるしとその意味――「外なるもの」と「内なるもの」
第三部 詩学
第八章 心情の表現としてのポエジー
1 自然と人間の内的空間としての心情
2 心情のあり方
3 心情とポエジー
第九章 高次の自然学としてのポエジー
1 自然哲学との関連と相違
2 ゲーテの自然学とノヴァーリス
3 自然の精神のアナロジー
4 光の問題
第十章 文学の理論としての詩学
1 ロマン的ポエジー
2 芸術とポエジー
3 自然とポエジー
第十一章
1 シンボル
2 アレゴリー

ツヴェタン・トドロフ『象徴の理論』
ロマン派の理念は、モーリッツによって確立されていた。そこには、芸術が自然の模倣から逃れ、それとは独立した存在であることが言祝がれ、作品は部分と全体との調和の内に成り立つという古典主義的な美の理論が再確認される。そして、対立物の調和・反対物の融合というもう一つの原理は、ロマン主義美学を特徴づけるものとなった。しかし、ノヴァーリスやシュレーゲルらのロマン派の理論は当時の状況より一歩も二歩も前進していた。そこには、現代にまで通じる積極的な意味が隠されていた。

オウィディウス『変身物語』(上)
「サルマキス」より
‥‥少年 (ヘルマフロディトゥス) のほうは、当然ながら、草原にはもう誰もいず、人に見られてはいないというつもりで、あちらこちらへ歩を運び、やがて、ひたひたと寄せる泉の水のなかへの爪先を、それから足を踝 (くるぶし) まで浸すのでした。とおもうと、猶予もおかず、こころよい水の冷たさに心を奪われて、たおやかなからだから衣服を脱ぎ捨てます。するとどうでしょう、何と好ましい姿 ! サルマキスは、その裸身に焦がれて、燃え立ったのです。‥‥
少年は、手のひらで体を叩くと、さっと水にとび込みました。抜き手を切って泳いでいますが、澄んだ水のなかで体が光っているのが見えるのです ―― まるで、透明なガラスの箱にいれられた象牙の彫像か、白百合の花ででもあるかのようです。『わたしの勝ちよ ! とうとう手に入れたわ』水の精はそう叫びます。そして、衣服をすっかりかなぐり捨てると、ざぶんと水中に飛び込みました。あらがう相手をつかまえ、無理じいに接吻を奪うと、手を下へ回して、強引に胸にさわり‥‥ (中村善也 訳)。

ピーター・トムキンズ、クリストファー・バード『土壌の神秘』
バイオダイナミック農法を実践する著者たちが、いかに土壌の健康が植物を健やかにするかを語っている。化学肥料が土壌をコチコチにし、微生物の適正な環境を排除し、根を窒息状態にすることによって、不味くて栄養の乏しい農産物にするかを指摘し、それに加えて農薬が昆虫たちの耐薬剤能力を加速させ、農薬の強化とのイタチごっこになり、薬に耐える品種であるスターリンクを生み出し、健全な小麦と交配していくことを指摘している。それに加えて、種苗会社が、栄養価の高い品種より発芽率の高い品種を優先して売り、優秀な種が市場に出回らくなり、ひいては、その土地特有の植物たちが絶えていくことの悲劇を語りつくす。農業と食の関係を考え直させる著書。

フリードリヒ・シェリング(1775-1854)
シェリングの父親もノヴァーリスの父親同様、敬虔主義者だったと言われる。1790年に20歳で入学できる規定のテュービンゲンの神学校に15歳で入学した。その時、5歳年上だったが同級のヘルダーリンとヘーゲルと寮で同室となる。この頃、フィヒテとスピノザに傾倒した。1796年にライプチッヒ大学で自然学の講義を始め、ライプニッツへの傾倒が見られる。2年後の著書『世界霊について』がゲーテに認められ、イェーナ大学に招かれ、やがてフィヒテの後任となった。シュレーゲルの妻であるカロリーネと恋愛関係になり、カロリーネはシュレーゲルと協議離婚の後シェリングと結婚する。1809年にはヤコブ・ベーメの影響を受けた『人間的自由の本質』を著している。後期の哲学は「神話の哲学」「啓示の哲学」へと傾斜していった。

エリファス・レヴィ (1810-1875)
1874
フランスの象徴派の詩人であり、穏秘学の研究者・思想家として知られる。
聖職者を志していたアルフォンス・ルイ・コンスタン (本名) は、1839年に信仰への回心からソレームのベネディクト派修道院に滞在し、ギュイヨン夫人の静寂主義や、クリューデネル夫人の敬虔主義の著作などに触れ、処女作となるマリア崇拝の伝説集『五月の薔薇の樹』を出版した。しかし、1841年に出版した『自由の聖書』が、聖書を社会主義的な観点から著していたために聖書を訛伝したとして投獄されるという憂き目にあう。
1853年にエリファス・レヴィと名を変え、ユゼフ・マリア・ハーネー=ウロンスキーの義弟モンフェリエと隠秘学の雑誌『進歩的評論』を刊行する。社会主義的な思想から穏秘学へと移行した。
主著『高等魔術の教理と儀式』は、隠秘学の原理が象徴主義に結びついてユゴー、ボードレール、マラルメ、イエイツ、ジャリなどの象徴派詩人に深い影響を与えたし、後代のジェイムズ・ジョイス、アンドレ・ブルトンなどの作家にも影響を及ぼすこととなる。 その他に隠秘学に関する膨大な著作である『秘教哲学全集』があり、その一端に、ランボーやヘンリー・ミラーが心酔したと言われる。


コメント