
ロバート・ジェイ・リフトン『ヒロシマを生き抜く』上・下
今年も8月6日がやってきましたね。8月9日を軽視するわけではありませんが、広島に生まれて、そこに住んでいる者には、やはり8月6日は重要な日といわざるを得ません。今は、核廃絶と地球温暖化はかなり難しい局面を迎え始めています。この厳しい状況は残念ながら続きそうです。今回の夜稿百話は、核が人間に何をもたらすのか、人間はどうして、そこから目をそむけるのか、核に直面した人々が如何にして再び立ち上がったかを心理的な側面から実地に調査したアメリカの心理学者であるロバート・リフトン博士の著作『ヒロシマを生き抜く』をご紹介します。
ロバート・ジェイ・リフトン博士は、1926年ニューヨークに生まれた。ニューヨーク医科大学で、学位を取得している。1951年から1953年にかけてアメリカ空軍の精神科医として日本と韓国に派遣された。1956年から1961年にはハーヴァード大学東アジア研究センター研究員となり、中国における思想改造や日本の学生運動の研究を行っている。1962年広島での原爆被爆者の調査の後、イェール大学医学部に着任し、ハーヴァード大学、ニューヨーク市立大学で教鞭を執った。ニューヨーク市立大学の名誉教授であられる。若い頃はフロイトに影響されるが次第に独自の心理学を構築し始める。博士は「社会的責任を果たすための医師団/PSR」「核戦争防止国際医師会議/IPPNW」という二つの運動に参加している。このうちIPPNWは1985年にノーベル平和賞を受けた。

IPPNWバナー 2011 ベルリン
本書は1968年にアメリカで出版され、翌年科学部門の全米図書賞を受賞した。その授賞式で博士は「ヒロシマは、なんらの賞も許さないのです。ヒロシマが要求しているのは、ひるむことなく真のヒロシマの意味を認めることなのです (桝井迪夫他 訳)」と述べている。
邦訳された著書に『終わりなき現代史の課題―死と不死のシンボル体験』『思想改造の心理―中国における洗脳の研究』『終末と救済の幻想―オウム真理教とは何か』『誰が生き残るか プロテウス的人間』などがある。『現代(いま)、死にふれて生きる―精神分析から自己形成パラダイムへ』では「創造者としての生存者」という章で第二次大戦を生き残った三人の作家、アルベール・カミュ―、カート・ヴォネガット、ギュンター・グラスを取り上げた。
広島での調査
原爆が投下されて17年の歳月が過ぎていた。だが、個人の学者にせよ、団体にせよ、組織的、具体的に被爆者に対する心の影響の調査は、なされていなかった。何故、遅れたり、無視されたのかについて、リフトン博士は研究者が選択的に自身の心を麻痺させた結果ではないかと考えている。ある意味、調査には、そのような麻痺、つまり心の閉め出しが必要とされたという。およそ、死に対処するあらゆる仕事に必要なものだけれど、とりわけ被爆のような恐ろしい現実に一体化することは、研究者自身に精神的な麻痺を引き起こす「治療の逆作用」を生み出す危険があったというのである。
しかし、同様に核兵器の開発・実験や製造に携わる人たちにもそれと同じ状態に陥っては、いないかと危惧している。核兵器のもたらす結果を感情面で締め出してしまっているというのだ。現代の物質的繁栄とテクノロジーの進化に伴って進行している事態に共通している問題と言えるのかもしれない。それは、リフトン博士が言う「際限を知らない技術がもたらす暴力と不条理な死」を招くのである。
被爆者への面接調査は二つのグループに分けられていた。一つは広島大学原爆放射能医学研究所によって無作為に選ばれた被爆者31名、もう一つは主として学者、作家、医師、政治指導者から成り立つ42名の被爆者だった。博士は多少日本語を話すことが出来、倫理的使命感をもって取り組んでいること、そして、組織的研究が必要であることを面接者に説明した。それに、平和象徴に関する博士の論文の日本語訳が『朝日ジャーナル』に掲載されたことが追い風になった。少なくともアメリカ政府のための情報収集ではないことが理解されたようだ。
本書は、この面接での内容がかなり詳しく書かれている。今回、僕は、その纏めと言える最終章「生存者」に限定して詳しくご紹介しようと思っている。
生存者に残される心理的脅威と精神的再形成
1.死の刻印
生存者体験の鍵となるものは死との対面である。ヒロシマの被爆者たちの過酷な体験は、三つの側面から語ることが出来る。白昼に巨大な稲妻に襲われたように突然全ての人々が死に侵されたこと。放射能の後遺症と結びつく死の恐怖に脅かされ続けること、核による絶滅という世界的な恐怖に集合的に触れ合ってきたことである。これらの死のイメージは正に圧倒的だった。

原爆投下後のヒロシマ 1945年 ウェイン・ミラー中尉撮影
その死は、至る所に存在しただけでなく、異様にグロテスクな奇怪で不自然なものであり、考えられ得ないほど不適切で不条理なものだった。一瞬にして、とてつもなく変わり果てた人間の姿は、恐らく14世紀にヨーロッパを襲った「黒死」を思い起こさせるとリフトン博士は言う。黒死病、つまりペストである。ペストの様々な症状は、壊疽 (えそ) 性炎症、胸部の激痛、嘔吐と吐血、患者の体や息から発散する「ペスト臭」といったものだった。
このような死に曝された人々は、死そのものだけでなく、そのグロテスクな様相をも自分の一部になってしまい、自身と分離できないものになってしまうというのである。
ヒロシマの生存者たちは、原爆によって生じた恐ろしい症状とそれへの恐怖を口々に語った。血便を伴う激しい下痢、脱毛、体中の穴からの出血、皮膚に現れる紫斑、それに長く続く極度の倦怠感がある。死は2年後、3年後、いつ訪れるかもしれなかった。ペストは一度それから回復すれば、再発は無いが、原爆症は、一度回復したと見えても、ずっと後になっても同様な死に侵される不安にさいなまれることになる。原爆投下直後の数年間に白血病が多発し、その後は甲状腺癌、胃癌、肺癌、子宮頸癌などが多発する。放射能は何世代にもわたって遺伝的影響を残す可能性があることが知らされると、奇形児を産むことへの強い恐怖が広がった。
2.もろさの意識
もろさという点で被爆者には相反する二つの側面が見られる。人は通常でも、危険に立ち至った場合、自分は頑健だと思いがちだが、生存者は、死を極めて衝撃的な形で意識させられることによって、この幻想を徹底的に打ち砕かれるために、自分のもろさを強く意識するようになるという。
もう一つは、ある生存者たちが死に直面しながらも、それを征服し、一層頑健になったと意識するようになることである。その人たちは平和運動などにおいて、ある種のカリスマ的な存在となる場合もある。それは、死との遭遇という「試練の道」を経て生き延びて帰還し、死を克服する特殊な英知を人々に伝えるという英雄神話と心理学的にパラレルな様相を帯びた。
しかし、そのように感じている人も、けっして死の不安を免れてはいないとリフトン博士は言う。それは、希望的観測である場合が多いという。彼らは、死と荒廃の光景に一生呪縛される。それほどの強度で、この体験は意識に刻み込まれるのである。

ガス室への移送 1940-1945の間 Archiv Post Bellum
ホロコーストの生存者は、現代における死の不安と直接的に結びつくことは少ないが、長く尾を引く屈辱と恐怖に付きまとわれる。詰め込まれた輸送車の中での窒息、恒常的な飢え、拷問、強制労働、伝染病、人体実験といった精神的、肉体的打撃は癒しがたい損傷となった。
時に、自分の働いているオフィスの壁が消え去り、アウシュビッツかブッヒェンバルトの荒涼とした眺めに取って代わられる。その細部は異様に強烈で生々しいのである。その思い出は、何度も何度も自分が生き延びたということ自体を思い出させる。しかし、被爆者と同様に、そこには死者のイメージによる圧倒的な支配、自分だけが生き残ったという罪悪感、加害者への敵意、身体的障害に対する様々な心的反応があり、同時に通常の行動様式の崩壊が見られることもあるという。
3.心理的閉め出し

ナガサキにおける被爆者 1945年 8月10日撮影
死者に対して、生き残った者が、生き残り得たという、いわば優位に立った感覚は罪悪感に変わる場合が多い。我が子に先立たれた親の罪悪感は殊のほか強い。このような罪悪感と死への不安から身を守るための反応として大きな力を持つのは感情の機能停止だった。ヒロシマでの実態調査で明らかになったのは、この反応が急性の場合が「心理的閉め出し」と呼ぶものであり、慢性の場合には「感情麻痺」というべきものになることであった。
心理的閉め出しは、被爆のような異常事態に対して順応するために極めて大きな役割を果たす。何も感じなければ死などないと感じられるのである。死者と一体化しがちな心の働きを弱め、完全な無力感を弱めたりもする。それは、象徴的死と言いうるものかもしれないリフトン博士は考えている。
しかし、生死を巡る象徴体系が完全に崩れて、内部の統合、統一、運動 (活動) に関わるイメージが失われ、人間の心の関係性/連続性と言うべきものが完全に失われる場合がある、強制収容ではムッセルマンと呼ばれる状態があるという。他者と自己を一切断ち切ってしまい、後戻りできない精神的死を示す状態である。環境に全くの支配を許し、死への本能的願望に飲み込まれる。あるユダヤ人は「生死の中間世界をさまよっている呪われた魂」と表現している。精神的麻痺は、有害な刺激を防ごうとするある種の肉体的営みだが、恐ろしい病理学的力に変質し、結局は生体組織のうちに死のイメージを氾濫させるという。原爆症に関わる心理的ダメージとはこのようなものかも知れない。
精神的麻痺が昂じた場合でも人間の認識能力は、保持されうる。失われるのは、認識した事柄や感情を行動に結びつける象徴的統合能力だという。「歩く屍」「生ける屍」「自分の屍の影を踏む者」、被害者たちのこういった言葉に託して語られている事柄は、死の洗礼を受けた当時だけではなく、現在においてもある程度、そう感じられるような自分の姿なのだというのだ。
3.生存者が失ったもの

被爆によって石段に刻印された人影 旧住友銀行広島支店
生存者たちが悼むのは家族と近親者の死である。そして、家や財産、慣れ親しんだ生活様式、自己の信念、そして自分との絆を持つ諸々の象徴である。過去の自分、死への直面とそれとの葛藤がやって来る前の自分を悼み、弔う。彼らが奪われたものは、死のけがれを知らない無垢な状態に他ならない。それは「仲睦まじい家族の懐に抱かれて過ごした牧歌的子供時代」のイメージに繋がるのである。そこでは、死んだ人たちが理想化された状態で存在する。生存者は決してこの失われた黄金の時間を取り戻せないために、死に縛り付けられ、自らの悲しみに縛り付けられるという。
ヒロシマにおいては、生存者は急激で絶対的な転換を強いられたあの最後の瞬間を終生同化することが出来ない。ホロコーストにおいても、十分な弔いを成就し得なかった後に精神障害を起こすケースが多いと言われる。両者において、問題となるのは「死者が行方不明」であるケースだという。彼らは寄る辺ない死者であり、それを弔えない生存者は無意識に罪悪感を持つ。一方で、死の不安や穢れの観念に駆られて家族の死体さえ拒否する生存者もいたという。心の悲しみが解決されなければ、精神的・肉体的な一連の障害を被ることになる。しかし、病気は悲しみそのものによるのではなく、それがゆがめられることによるのだというのである。
4.喪失・別離・終末のイメージ
別離にもいろいろな死の不安が忍び寄る。幼児の死は母親にとって自分への死の脅威となることも多い。長くつらい闘病生活を送る近親者にたいして安楽死させてやりたいと思うこともあり得る。医師にとっても患者の死が、以前の自分の喪失体験の記憶を蘇らせることだってあるだろう。
死と喪失と離別とは、人が成年になっても心理的に相当程度相互に置き換えられるという。喪失も別離も、死との遭遇体験を象徴的に蘇らせるのである。精神病の患者の場合、世界に対する関係は根元的に損傷され「精神的死」という感覚が、その損傷した関係に投影されて「世界終末」のイメージが現れる。しかし、被爆者の場合、圧倒的な絶滅という事件が外から押し付けられるのである。被爆やホロコーストにおける乱脈な死は、単なる死ではない死であり、その死への不安は恐るべきものだった。あり得ない大量の死、余命のない老人から生まれたばかりの嬰児まで、なんら筋の通る死は無かったのである。この喪失と離別の記憶は、ジョー・オダネルが1945年のナガサキにおける『焼き場に立つ少年』の写真に見事に捉えられている。あの嚙み締めた少年の唇と真っすぐな視線が忘れられない。
このような体験によって、致命的な死の苦しみにさいなまれるだけでなく、永生の可能性を否定的に見てしまうことだってある。キリスト教的な表現であれ、象徴的な言葉であれ、死と復活の究極的な力に対する自己の関係は、重大な危機に曝されるとリフトン博士は述べている。
5.罪悪感との戦い
平和な家庭の長老が天寿を全うし、安らかに迎える死は郷愁をさそう理想的イメージだが、ほとんど神話的なもので、多くは実現されない理想であり、逆説的に大きな力を持つ。そのことによって、生存者の罪悪感が掻き立てられるのである。自分がより長生きしたいという願望と、親の長寿を願う気持ちには矛盾があり、根源的に直接・間接に死と生に関わる矛盾した感情の内に生きているのである。
被爆者の場合、近親者が行方不明の自分を被爆地で探し回ったあげくに自分より早く亡くなったとすると、一生その罪悪感を背負うことになる。20世紀最大の詩人の一人と言われたパウル・ツェランは逃げることを説得できなかった両親を残して家を出たが、両親が強制収容所で亡くなったことを一生後悔し続けていた。

アウシュビッツ 1945
ホロコースト内においても悲惨だった。誰が今日死ぬかは、ゲームのようなものであり、自分がどの列に立つか、労働に耐えられると思ってもらえるような外見をどうつくろうかは、他者を出し抜いて生き延びることに直接関係していた。それは、「永遠の汚辱」と言うべきものとなって心の底に居つくようになる。例えば、鏡を見る時に「一つの死体がじっとこちらを見返している」といった体験に結びついた。目の象徴的イメージは、はるかな普遍性を持っている。死者からの凝視は、生存者が、同じ人間として「自分の非を責める目の所有者」と一体化していくことにあるという。
死者との一体化について、広島での研究で印象的な事柄があるという。死者が欲したと思われるように、自分も考え、感じ、行動しようとするというのだ。それができなければ、他者の身になりきれない自分を厳しく責め始めるというのである。自分が生き残ったのとは裏腹に死んでいった人々に対してしたこと、あるいはしなかったことに関する罪の意識は死者との一体化を催し、「存在の秩序の傷」というべきものを生み出すというのである。死と生存の問題は、けっして個人的な事柄ではない。死をめぐるイメージは誰が生き残るかという内心の疑惑と結びついているという。
6.罪悪感の放射
このような罪悪感による一体化は、死者から生存者へ、生存者からそれ以外の日本人へ、日本人から世界の人々へと放射的に広がっていき、自分よりもより苦しみの中心に近い集団への心理的同化を催すという。外国にいると広島から来たというだけで、色々な同情的な言葉をかけられることにもなる。この死者と罪意識の関係は、他者との一体化という人間の心理に対する究極の象徴的連関を考える上で重要な基礎となるという。被爆という圧倒的な暴力がもたらした異常事態によって、無残な死を遂げた人々がいる。そのような犠牲の上に自分たちは生きているという罪悪感は放射現象というべきものを生み、それは正常な一体化という人間相互の絆が一時的にせよ破壊されることによって生じる。それ故に一層重大なものになるとリフトン博士は強調する。
一方で、大量の死者に近ければ近い人ほど、死の洗礼に耐えるための全面的防衛が必要とされ、心を鎖すための精神的活動が要求される。しかし、そこから遠い人々にとって心理的締め出しに対する要求はさほどなく、より容易に被爆やホロコーストの惨状にたいして心を閉ざしてしまえることにもなる。この精神的麻痺状態は同心円状の連続体であって、その周縁にいる人々に対しても死の洗礼に敏感に感応する潜在能力は存在し続けているという。
福島の原発事故で、被害者たちが差別されたことの原因はここにあるのではないかと僕は考えるようになった。被爆という見えない脅威による死の不安は、ヒロシマの死によるこの罪悪感の放射という構造に自分をより接近させる結果となる。それを心理的に閉めだそうとした時、生じたのは自分たちより死の放射に近い人々を締め出そうとする現象となって現出したのではなかったろうか。ここは学ぶに値することだと思える。
7.精神的麻痺と核兵器

浦上天主堂跡における慰霊祭 1945年11月23日 ナガサキ

1948年 広島平和祭
現代社会では、死の悲しみからおこる病理的反応が増大しつつあるらしい。有意義な弔いの儀式が存在しなくなりつつあることを指摘する心理学者もいる。死が締め出される所には生命の意義に対する感覚が失われた状態があり、「不完全な生」というべきものになっている可能性もあるのである。
自殺に対する企ては、精神的麻痺を脱して、自己の無力化を克服しようとする絶望的な試みともなり得るという。自ら死の主人となり、それを支配する道でもあり、魔術的に見えるにせよ象徴的に人間の完全な姿と自己の不滅性の感覚を回復したいという企てではないかとリフトン博士は言う。しかし、それは悲惨だ。一方で、統合失調症のような患者の空想や妄想には、自己万能感が現れることがある。万能な人間は不滅だと思うのだ。
リフトン博士は、精神疾患の患者が自己の万能性と不滅性に対する原始的空想に及ぶのは、実人生における諸関係が壊れているために不滅性の象徴が根元的に損傷しているためだと考えている。死の不安は精神的麻痺を引き起こす根本的な原因だが、それを締め出したいと感じるのは、ただ死だけが原因なのではなく、むしろ死が生命の象徴に対して持つ関係のゆえなのだというのである。
精神的麻痺は我々の時代における大きな問題となってかなりな時間が経つ。死一般に対して、とりわけ核兵器による絶滅死に対して世界中の人々が精神的な麻痺に陥っている現在、ヒロシマ、ナガサキの体験に対する死の不安と罪悪感を分かち持つことは、それを打破するために価値のあるものだと理解してほしいリフトン博士は述べている。
8.犠牲とパラノイア

レストハウスの地下 ヒロシマ平和公園内
死の体験を乗り越えて新たな精神形成を進めていくうえで、愛、保護、調和といった、かつての深い感情を自分の心に蘇らせることが、生存者の意識を支える大きな要素となる。単純で澄み切った幸福を味わった「黄金時代」は必然的に子供時代のものである。「秩序ある世界での遊びから湧き上がる喜び」といったものに関わる感情。それが生存者に最も必要とされているものなのである。
そうした昔の感情を平和都市を構築するとかユダヤ国家を建設するとか有意義な目的に結び付けることが大きな意義を持つことにはなる。それでも、何らかの形で死者からの象徴的なメッセージに由来するものでなくてはならないという。
被害者意識が極端に強くなると、人間というトータルな概念から離れて、全てを被害者と加害者としてだけで意識してしまうような硬化した精神状態になってしまうケースがある。生存者パラノイアと呼ばれる状態である。周囲の敵に攻撃を集中し、投影という心理的なメカニズムを利用して自分が未だに被害を被っているという感情を表現する手段にしてしまうのである。
有罪者を処罰し道徳的秩序を回復する、いわば「正義を収集する」努力の中で、復讐の観念はつねにあり、かつての親衛隊だったアイヒマン裁判は良い例となる。しかし、現代技術の暴力といった原爆の場合、その兵器の性質上、復讐することは事実上不可能なことである。日本が戦争に加担していた以上、誰にも責任は無いという考えに傾いていったことは理解しやすい。
9.見せかけの保護と伝染への恐怖
見せかけの保護に対する不信感というのは自分を脅かす者への一体化と関係している。保護を強く求める願望と自分のもろさ想起させるものに対する過敏な反応とが絡み合い、自立に対する激しい葛藤が起こる。精神的麻痺が自立を一層難しいものにする場合もある。提供される援助が生存者に自分の弱さを確信させるばかりか、その活力を根本的に奪ってしまうというのだ。日本が原爆でアメリカを攻撃したというデマで瀕死の患者が突然活力を取り戻したという例をある医師は書き残している (蜂谷道彦『ヒロシマ日記』)。力は一般的に死を支配する力であり、攻撃者への一体化は生存者にとって自分を脅かしている力を共有しようという企てであるという。
原爆によって犠牲を強いられたという意識は集団意識となって連帯感を生み出す。それには原爆症が伝染するという誤った認識から生まれる他者の恐怖も原因しているかもしれない。マイノリティにされたという感情はあっただろう。その連帯意識は死をもたらした当の力と隠微な関係を結び、終生一体化してしまう可能性をもたらすという。それは結局、自分の生活がまやかしであるという意識を強め、保護に対して見せかけだとする拒否反応を生み出すことになるというのである。
10.精神的再形成への道

原爆ドーム © UEDA Nobutaka
リフトン博士は、死の体験は誕生時に既に人間に備わっていると考えていて、それが後年の死のイメージの原型ともなるという。「離別と結合」における離別には、幼児の親からの分離不安が大きな要素を占める。そして、この離別には分裂と静止 (停止) が伴っている。これに対して結合、象徴的統一、活動が対極にある。
人間は生命を肯定する根拠が脅かされる度に、生存を強く体験付けられると同時にその体験の内に内外の世界を再構成する必要に迫られる。このような中で死の体験は以前からの死のイメージを活性化し、常に新たな広がりをつけ加える。死の洗礼が持つ感情的な力は、新しさの衝撃と再認の衝撃との結合にあるという。
過酷な体験を可成りな程度まで克服できると、生存者は自分の過去から生命肯定の要素を呼び出すことが出来、「能動的な緊張」と「はつらつとした現実感覚」を取り戻すことが出来るようになる。そして、驚くべきことだが、無抵抗な態度が最も有効な力を発揮する場合があると言う。他方で「生存者の使命」と呼ばれる社会的な活動があり、生存者が精神的麻痺に陥ることを助けるというのだ。両者ともに永生の観念を復興することを含めて、広く人間の精神に象徴的統一性を与えるものだというのである。
死と人間にとってのシンボリズム
僕が今回、この『ヒロシマを生き抜く』を取り上げたのには二つ理由があった。一つは、最近日本でも頻繁に起こっている大災害に対して、自分が感覚的に鈍いのではないかとずっと思っていたことに対する回答が得られたように感じられたこと。そして、ヒロシマやホロコーストのような極限的な状態から脱出して精神的再形成をする上で象徴が極めて大きな役割を担うことを教えてもらったからである。
最初に述べた「感覚的な鈍さ」が心理的閉め出しと呼ぶものに由来していているというのは、全くその通りなのではないかと思えたのである。多分、それは幼い頃からの傾向ではなかったのか。そういうことを気づかせてもらった。死に対する不安や分離不安は、僕の心のどこかに潜んでいたのだと思う。
もう一つの「死と象徴」の問題は、この本を読んでいた時に、同時にミルチャ・エリアーデの『宗教学概論』について色々考えていたことと恐ろしいほどに共振しはじめたことと関係している。例えば、水や月は死の象徴であり、再始と再生の象徴ともなっている。この象徴は、人間の分断されない全体的意識から直接与えられるものだとエリアーデは言う。それは合理的、論理的操作から生まれるものではなく、知性や魂を含めた人間全体に啓示されるというのだ。それが与えられれば、自分を人間として発見し、宇宙における自分の位置を自覚できるようになる。それは、月や水を客観的に眺めることによって生じるものではなく、神話的寓話化や不合理な宗教経験の産物でもない。
言葉は部分しか示せない、象徴は全てを示せる。しかし、それには概念が必要だと松山俊太郎さんは、述べている。象徴は巨大な扉の鍵穴だが、それを開けるには概念という鍵が必要なのである。
人は、それぞれに様々な象徴を持ちあわせているだろう。人間にとっての原初的な発見というべき象徴が、世界と極めて有機的に結びついているかぎり、同じシンボリズムが精神生活の最も高貴な部分にも意識下の活動にも、共に働くというのだ。人間にとって、この象徴的統一や統合が、その危機にあって如何に重要なものとなるかをリフトン博士もまた教えてくれているのである。これらの統合が、世界の極限的な崩壊と終末のイメージの中に溺れようとする人間に如何に有効に働くものであるかを彼は数多くの被爆者の証言を土台として指し示してくれているのである。
2021年 8月に投稿した文書を再録しました。

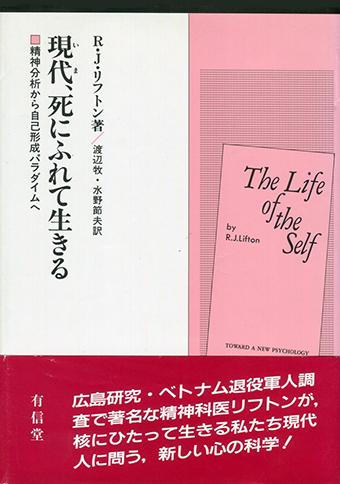
『現代、死にふれて生きる』
死と生との連続性の組織化、心理的形成と象徴を原則とする心理学のパラダイムシフトが示される。
本書でリフトン博士はこう述べている。「こうして問題は、世界の終わりという〈イメージ〉を呼び起こすと言うことにとどまらない。その〈イメージ〉にある程度打ち勝ち、われわれの美的・道徳的想像力のなかにその場を確保すること、これもまた問題なのである。広島とアウシュビッツの様々なイメージを人間の意識から払いのけようと、世界の非常に多くの人が試みているが、これは無益だというだけではない。そのような企てをするということは、われわれから我々自身の歴史を奪い取り、われわれに現にそうであるところのものを奪い取ることである。我々は、自分たちに備わっている想像力を妨げることで、新たに諸形態を創造すると言う、われわれが非常に必要としている能力をそこなっているのだ。われわれは、広島とアウシュビッツを必要としているのだ。‥‥ それは、それらがわれわれにもたらす戦慄にもかかわらず、その戦慄もたらさざるをえない飛躍へと想像力を深化させ、解き放つために、である。ロートケ (セオドア・ロスケ/アメリカの詩人のことか ?) の言葉を借りれば、『眼は、暗い時にこそ見え始めるものなのだから。』死のビジョンが、生をもたらすのである。全体的な死滅というビジョンを持つことによって、死滅のもとで、そして、その呪いを超えて生きるということを、想像できるようになるのである。」

蜂谷道彦『ヒロシマ日記』
広島逓信病院長であった著者が被爆後の56日間の体験を綴った日記。被爆体験の貴重な資料の一つとなっている。

ジョン・ハーシー『ヒロシマ』
1946年従軍記者として来日した著者が谷本清牧師、クラインゾルゲ・イエズス会神父、佐々木輝文医師らの原爆体験綴ったドキュメント。その年のニューヨーカー誌に一括連載され全米を震撼させた。戦時中のシチリアを舞台にした『アダノの鐘』でピュリッツァ賞を受賞している。
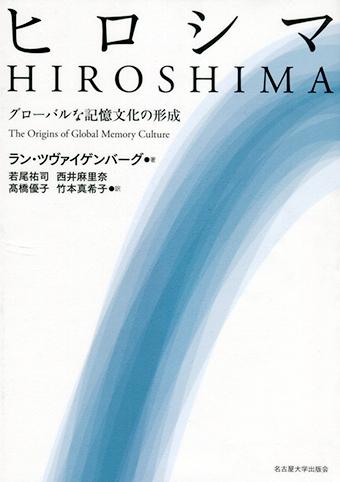
ラン・ツヴァイゲンバーグ『ヒロシマ グローバルな記憶文化の形成』2020年刊
被爆後のヒロシマで戦災者たちへの支援と街の復興は政治的なバイアスの中でどのように成し遂げられていったのか。第二次大戦における大量虐殺の犠牲者たちは、語り得なかった過去をある時期から語り始める。それは何故か。被爆者たちの PTSD がクローズアップされるのは、比較的最近になってからだった。何故そのように遅かったのか。あの語り得ぬ出来事をアウシュビッツとヒロシマの人々は、どのように結びつけていこうとしたのか。本書では、このような事柄を通してヒロシマという特異な体験を経た街と人にまつわる記憶文化がどのように形成され、変化していったのかが語られる。

ミルチャ・エリアーデ『豊穣と再生』 宗教学概論 2
第四章 月と月の神秘学
第五章 水と水のシンボル
第六章 聖なる石
第七章 大地、女性、豊穣
第八章 植物

ミルチャ・エリアーデ『イメージとシンボル』
第一章《中心》のシンボリズム
第二章 時間と永遠のインド的シンボリズム
第三章《縛める神》と結び目のシンボリズム
第四章 貝殻のシンボリズムについての考察
第五章 シンボリズムの歴史
エリアーデは宗教学概論3『聖なる空間と時間』の最終章「象徴の構造」の中でこのように述べている。少し纏めてみよう。
あるシンボルは、例えば「生成する力」とその「形態」を統合すると言う。真珠のような象徴は単独で生命・女性・豊穣といった神的示現を具現すると当時に、月や水といったシンボルを一つにまとめる。水や月のシンボルは、生命=死であり得るような矛盾したものの象徴となり得る (第五章 水と水のシンボル)。このようなシンボルは、あるレベルから別のレベルへの移行や循環を可能にし、それによってあらゆる面を統合するが、決してそれらを融合することはないと言うのである。それは結びつける力であり、溶かし合わせる力ではないのである。
リグ・ヴェーダに登場する蛇の怪物ヴリトラは、いわば、縛ることによって水をせき止める。死神が死者の魂を網で捕らえるように「縛られ」「鎖につながれる」といった事柄に関連するシンボリズムは、もつれた系の「結びを目解く」シンボリズムを経て、常に唯一の象徴複合にたどり着くとエリアーデは強調する。「縛ること」+「結び目を解くこと」の象徴複合は他のどんなヒエロファニーによっても啓示し得ない特別な状況を開示し得る。人間に宇宙における自分の状況を自覚させ、それを首尾一貫した仕方で表現しうるようにさせるのは、この「絆のシンボリズム」のみだと言うのである。








コメント