
ソコルル・メフメト・パシャ橋/トルコ名
メフメド・パシャ・ソコロヴィッチ橋/ボスニア名
通称ドリナの橋
トルコの建築家ミマール・スィナンの設計によって1571年から1577年にかけて建設された。ミマールは建築家を意味する言葉。全長179.5m、2007年に世界遺産になっている。
ボスニアとセルビアの国境をなすドリナ川、そのボスニア側にあるヴィシェグラードには、その川に架かっている世界遺産となった美しい橋がある。オスマン・トルコ帝国の新設部隊イエニチェリが東南欧のキリスト教国から10~15歳くらいの少年を拉致して常備軍の兵士に仕立て上げていた。奴隷の身分ながら多くの特権があり、中には政治の中枢で活躍する者もあった。その者たちの一人だったソコルル・メフメト・パシャは、この帝国の名宰相として知られる人物だった。パシャはトルコ高官への敬称である。

イヴォ・アンドリッチ『ドリナの橋』
ソコルル・メフメトはヴィシェグラードの山波の背後にある小村ソコロヴィチで生まれた。1516年のある朝、生きた税金としてイエニチェリの部隊によって連れ去られた。その途上、当時は橋のなかったヴィシェグラードの渡しに差し掛かかる。カラスの鳴き交わす岩だらけの秋深い岸辺は、少年にとって絶望の深い淵へと続いていた。その思い出は、黒い刃物のように長く心をえぐったという。しかし、そこは、ドリナの上流から中流にかけての唯一安全な渡河地点であり、ボスニアとセルビアとを結び、ひいてはイスタンブールに到るための不可欠な要の地点だった。宰相となった彼は、そこに壮麗な石橋を架けるように命じたのである。
双子の嬰児の人柱伝説、見たものは死ぬという中央橋脚の穴に住む黒い男の話、橋近くの崖にある対になった丸い窪みの連なりと巨人伝説、工事を邪魔する不死身のラディサダを絹糸で絞殺する話、セイク・トゥルハニヤという殉死した回教僧に関わる天からの光といった数々の伝承が、この橋を巡って生まれた。この物語はソコルル・メフメト・パシャ橋を中心にヴィシェグラードの町とボスニアを巡る悠揚な歴史物語として展開されていく。
今回は、イヴォ・アンドリッチの代表作の一つ『ドリナの橋』をプロットしてご紹介したい。ボスニア語表記のいくつかは、現在一般に使われているものに直している。歴史を踏まえてはいるけれど小説であるということはお含みください。
著者 イヴォ・アンドリッチ

イヴォ・アンドリッチ(1892-1975)
作者のイヴォ・アンドリッチは1892年、オスマン帝国からオーストリア・ハンガリー帝国の施政地となったボスニアの古都トラヴニクの近郊にあるドラツで生まれた。サラエボの出身で、カトリックであった父はコーヒー挽きなどを製作する金属細工師だったが彼が2歳の時に亡くなっている。母親は幼い彼をヴィシェグラードに住む夫の姉に托して、サラエボで働くことになる。ドリナの橋を見つめながら育った彼は小学校を卒業すると、サラエボのギムナジウムに進学しドイツ語を学び、フランス語を独学した。
ザグレブ大学、ウィーン大学、クラクフ大学で学んでいるが、第一次大戦が勃発。この大戦の引き金が、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボでのオーストリア皇太子フランツ・フェルディナンド暗殺であったことは、ご存じのことだろう。アンドリッチは、大戦直後に故国に戻ったが、南スラヴ民族独立運動の青年組織に加わった廉でオーストリアの官憲によって逮捕され、いくつかの牢獄で過ごした。新皇帝カール1世 (ハンガリー王国カーロイ4世) 即位の恩赦で1917年に釈放される。大戦終結後にオーストリアのグラーツ大学に学び、論文「トルコ支配の影響下におけるボスニアの精神生活の発展」で哲学博士の学位を得た。故国は、セルビア王国主導のもとにセルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国となったが、通称はユーゴスラビアであった。
アンドリッチは、完全に独立を果たせていない祖国のために外交官となることを決意し、ローマ、ブカレスト、トリエステ、マドリード、ジュネーヴ、パリ、ブリュッセルで大使館員や一等書記官として過ごし、最後はユーゴスラビア特命大使としてベルリンに駐在した。その間に作家活動も行い、ゴヤやペトラルカについて執筆、19世紀にボスニアに赴いたランス領事ピエール・ダヴィッドの資料を集めるなどしている。1941年に引退し、祖国に帰った数時間後にドイツ軍によるベオグラードの空襲を経験している。50歳の時である。

ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国とその後 2006年にモンテネグロとセルビアの連合国からモンテネグロが独立し、ユーゴスラビア連邦は消滅する。2008年にコソボはセルビアから一方的に独立したが、ヴォイヴォディナはセルビアの自治州に留まっている。
苦難の第二次大戦中、執筆活動を続けていた彼は、戦後三つの代表作を刊行した。この『ドリナの橋』、トルコ支配のもとにあり、ナポレオンのフランスとオーストリアとの政治的な駆け引に揺れる19世紀初頭のトラヴニクに暮らす人々の『ボスニア物語』、サラエボ出身の若い娘が拝金主義の老婆と変わっていく閉ざされた女の一生を描く『お嬢さん』 (邦題はサラエボの女) である。1954年にはイスタンブールを舞台とした『呪われた中庭』を完成させ、1961年にノーベル文学賞を受賞している。
第二次大戦後のユーゴスラビア
第二次大戦中は、ドイツの侵攻によって分割統治されていたユーゴスラビアは、1945年にチトーの主導のもとに共産主義国家としてユーゴスラビア連邦人民共和国となった。この連邦の一つにボスニア・ヘルツェゴビナ共和国が成立する。およそ北部がボスニア地域、南部がヘルツェゴビナ地域と考えていただければ良い。1990年に共産党独裁が終焉し、それに伴ってスロベニア、マケドニア、クロアチアが独立した。しかし、クロアチアやスロベニアなどが、ほぼ民族ごとの国家であったの対して、翌年独立するボスニア・ヘルツェゴビナは、約5割のイスラム教徒を抱えた多民族国家であった。
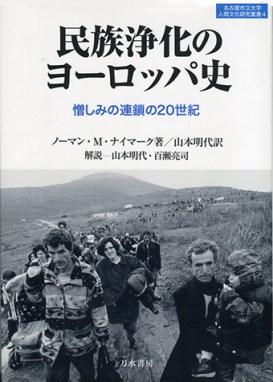
ノーマン・M・ナイマーク
『民族浄化のヨーロッパ史』
イスラム教徒主体のボシュニャク人とローマ・カトリック主体のクロアチア人は独立国家を望んだが、正教徒主体のセルビア人はセルビアと同様にユーゴスラビア連邦に留まることを望んで三つ巴の紛争が生じ始める。これが1992年から始まるボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の端緒だった。それは、凄惨なエスニック・クレンジング (民族浄化) を伴ったことで知られるようになる。女性と子供を標的にした民族浄化は惨鼻を極めた。このことについては、ノーマン・ナイマーク氏の『民族浄化のヨーロッパ史』をごらんになると良い。
1995年、国連の調停によるデイトン合意と呼ばれる平和調停によってボスニア・ヘルツェゴビナはボシュニャク人とクロアチア人主体のボスニア・ヘルツェゴビナ連邦と、セルビア人主体のスルプスカ共和国(セルビア人共和国)という不安定な連合国家となったが火種は燻っている。既に鬼籍の内にあるアンドリッチには思いもよらない展開だったろう。
オスマン帝国の衰退とセルビアの独立
第一次大戦を挟んだ1882年から1918年にかけてセルビアは王国として存在した。それ以前の1804年から1813年にかけて第一次セルビア人蜂起があり、オスマン帝国の支配に対してセルビアで反乱が起きていた。カラジョルジェ (黒いジョルジェ/1762-1817) が反乱の将であり、後にその家系からセルビア王家の祖が誕生する。さらに1815年から1817年にかけての第二次セルビア人蜂起によって、セルビアは公国として独立を勝ち得たが、なおオスマン帝国は宗主権を維持していた。オスマン帝国内のボスニアとセルビアの接境地帯にあるヴィシェグラードの町は平穏ではいられなかった。いかなる国家、帝国と言えど反乱や陰謀がないということはあり得ない。
この物語は、このような政治状況のもとで展開される。セルビアの反乱が広がるとトルコ人に対する徴兵と戦費の供出のために租税の要求が、いや増していった。セルビアへ送られる兵士や物資の大部分はこの町を通った。近くのセルビア側では、反乱軍が地主の家を大砲で破壊しトルコ人の家を焼き払った。ボスニアのセルビア人は反乱の火が自分たちの住む地にも、もたらされるように、トルコ人たちはこの火がもみ消されるようにと祈ったし、キリスト教徒たちは闇に紛れて十字を切った。

ドリアの橋の上 中央部の少し高くなっているヶ所に
トルコの碑石とカピアがある。

カピア
セルビアとボスニアを結ぶたった一つの連絡手段としてのドリアの橋は重要性を増していく。セルビア側からは何人ものセルビア人がこの町にも避難し始めていた。やがて、トルコによって橋の中央部のカピアに木造の不細工な二階建ての関所が設けられた。二階は衛兵の宿所である。この世の旅人チャイニチェ村のイェリニシェは、セルビア諸王と貴族の聖跡、建物、墓所を訪れ、正義の上に築かれた復活の王国を夢見ていた。以前には、トルコの官憲は彼を狂信者として気にも留めなかったが、関所のできた日、彼は運悪く、そこを通りかかり、リイエスコ村の19歳になる孤児ミレとともに首をはねられた。ミレは、セルビアの勇者アリベイの歌を歌っていただけだった。セルビアの反乱が収まると関所の必要もなくなり、やがて火事で焼失した。
オーストリア軍の進駐とヴィシェグラードの発展

ボスニア・ヘルツェゴビナ地図
オスマン帝国の衰退によってボスニア・ヘルツェゴビナの主権は残されたものの施政権はオーストリア側に移り、1878年の夏にはオーストリア軍がヴィシェグラードに進駐した。その時、セルビアは既にトルコからの独立を果たして公国となっていたし、トルコの正規軍はサラエボから撤退してドリナの橋を渡っていた。サルタンは抵抗なしにボスニアを譲歩するという噂も広がっていた。何世帯かのトルコ人はトルコ領へ移住し、その中には30年前にセルビアの支配下を脱してボスニアに移ってきた人々も含まれていた。
進駐が間もなく始まろうとする頃、回教の法僧であるムフティーは反オーストリア抵抗運動を組織しようと町に乗り込んできたが、この町の優柔不断な態度にいら立った。ムフティーに反抗したのはアリホジャ・ムテヴェリチという町でも屈指の家系で信望を集めていた人物だった。この一族の長は200年もの間メフメド・パシャの建造物であった石のハン (宿舎) の管理人の家系だった。オスマン帝国がハンガリーを喪失した時、ハンの維持費は打ち切られ、ムテヴェリチ家は、その官職を失うが永年正直に勤め上げた官職の誇りは今に残って続いていた。ヴィシェグラードのほとんどの回教徒と同じようにアリホジャも武装蜂起には反対だった。サルタンは既に割譲を約していたし、ちゃんと組織されていない民衆の抵抗運動は敗北するだけで不幸をもっとひどくするだけだと考えていた。
ムフティーたちは、オスマン・エフェンディ・カラマリンを残して立ち去り、アリホジャとの一騎打ちの様相を呈した。カラマリンは激高してホジャに迫ったが、アリホジャは冷静に意地が悪いと思えるほどの些事をあげつらって対抗した。しかし、オーストリア軍が町の近くまで迫ってくると、カラマリンはサルタンの命に反抗したトルコの敗残兵と共に町を出ようとし、置き土産にハンのあった台地に檞 (かしわ) の丸太を撃ち込んで、アリホジャの耳をそれに楔で撃ち込ませたのである。救ったのは赤い十字のマークをつけたオーストリアの兵士だった。
オーストリア軍の進駐が終わると戸籍調査が行われ、下水が整備され、水道が敷かれるようになり、地方庁の役所や裁判所などが建てられ、ポーランド、チェコ、ハンガリーなどから人々がやって来るようになる。ヴィシェグラードの町は秩序立ち、豊かになり、新たなテンポと今までになかった安定とがもたらされた。19世紀の最後の四分の一は、めったに達成されることのない無風状態が続いたのである。
ロッティカホテルと鉄道の施設
進駐後間もなく、カピアの反対側、トルコ語の碑文のすぐ下にオーストリア占領軍の布告が貼りだされた。我々は敵としてやってきたのではないし、この国土を暴力をもって制圧しに来たのでもないと書かれてあった。しかし、オーストリア人を指すシュヴァーベン人は伏兵を恐れ、トルコ人はシュヴァーベン人を恐れ、セルビア人はその両方を恐れ、ユダヤ人は全てを恐れた。

ソコルル・メフメト・パシャ橋/ドリナの橋
のカピアの反対側にあるトルコの碑文
オーストリアの施政によって町が景気に沸き返るようになるとユダヤ人のツァーラ―は町でも有数の大きさを誇るホテルを開業した。二階には泊り客用の6部屋があり、一階は一般向け用の大きなサロンと官吏、将校、金満家向けの小さなサロンに分かれている。そこを実際に切り盛りしていたのは義妹のロッティカ (ロッテ) という美しく才気煥発な未亡人だった。それで人々はここをロッティカホテルと呼んだ。彼女のために金をはたいていく男たちが、アルコールに乗じて彼女に迫ることがあっても、彼女の話し方は優しく、機知に富み、鋭く、おもねるようでもあり、宥めるようでもあったという。彼女が何時休み、眠り、食べるのか、着物を着付けや化粧をする時間をどのように工面するのか誰も知らなかった。
しかし、忙しい中でも、誰も入れない小さな事務所にそっと入ると、株式市況を読み、預金を調べ、銀行に手紙を書き、決済を下し、新しい預金を送った。無数の親戚と手紙を交わし結婚した妹や弟、ガリチア、オーストリア、ハンガリーに散らばった赤貧に喘ぐ多くの従兄姉たちに金を送り、どんな細かな事、子供を学校にやること、病人の扱い、金遣いの荒い者への叱責と忠告、家庭紛争の調停といったことに知恵をかし、人生の意義を教えたのである。

ヴィシェグラード郊外の駅 1906
オーストリアの軍用馬車が初めて橋を渡って20年が過ぎた頃、ドリナ川の右岸に鉄道が敷かれ、ヴィシェグラードの郊外に駅が建設されるようになる。この時、これが町の生活を支えてきた橋にとってどういう意味があるのかを人々は理解し始める。左岸はすっかりさびれて橋も運命を共にした。サラエボには4時間で行けるようになり、日帰りしてくる人々を他人は、不思議そうに見ていた。物価は高騰して、もはや儲けよりも出費の方がかさみ始める。労働組合が生まれ、ストライキという言葉が囁かれる。サラエボではセルビア人や回教徒の宗教的・愛国的な団体が結成され、ウィーンやプラハで学んでいる大学生が休暇で帰省し、新たな言葉や珍しい土産を持ち帰った。若者の間にはセルビアを中心とした南スラヴ (ユーゴスラヴィア) 人が独立のために結束すべきだという主張が醸成され始めていた。アンドリッチもそのような若者の一人だった。
暗殺と破壊の時
1903年、公国から王国に移行していたセルビアでは王位の交代があり、19世紀後半の露土戦争、モンテネグロ・オスマン戦争に敗れ衰退が加速していたトルコでは政変が続いた。しかし、併合危機と呼ばれたこの時期もヴィシェグラードは無事に過ぎていった。1913年にはオーストリア、トルコ、セルビアにそれぞれ面していた三国国境はセルビアとオーストリア、二国の国境となり、町から15キロほどの所にあったトルコ国境は千キロ以上もトルコ側へ南下してアドリアノープル背後まで後退したのである。オスマン帝国は潮のように引いて行く一方で、オーストリア・ハンガリー帝国は民族独立の機運に大きく揺れ始め、空中分解寸前となる。

フランツ・フェルディナンド大公と大公妃

サラエボ事件はサラエボにあるラテン橋の向かって左側の道路で起こった。
その事件は1914年6月に起きた。ドリナ川とルザヴ川の合流地点の高い緑の岸辺で楽隊たちが演奏し、若者や主婦や子供たちも集まってセルビアの民族舞曲コロが歌われ、つなぎ合わせた手の熱い広がりが、ひとつの血のリズムに溶けあって踊りも最高潮を迎えた頃、憲兵がやってきた。今朝、サラエボでオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子フェルディナンド大公と大公妃が暗殺されたというのである。世にいうサラエボ事件であった。その日からドリナの橋の中央部のカピアには歩哨の兵が立つようになる。
テロリストは大セルビア主義を掲げるボスニア・ヘルツェゴビナ出身のセルビア人、ガブリロ・プリンツィプだった。アンドリッチも主要なメンバーだった南スラヴ諸民族の統一を掲げる「青年ボスニア」にも所属していた人物である。セルビア人に対する迫害がささやかれ始める。ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人の中には大セルビアを目指す人間たちが数を増やしつつあった。
1915年、橋は破壊された。かつて、地元の人間にシュヴァーべン人と呼ばれたオーストリアの人間たちが、手入れをし、磨き、基礎を直し、水道管をひき、電灯をともした橋、そのあげくに彼らは空中に四散させてしまったのだ。かつて、この橋が出来た時、同時に石の宿舎 (ハン) が建設された。それを守ってきた由緒正しい先祖を持つアリホジャは、あの大宰相の贈り物であり、世の中で最も堅固で、神に帰すべき永遠な建造物が真珠の首飾りのように四散したことを知ったのである。

破壊されたソコルル・メフメト・パシャ橋/ドリナの橋 1915年
繁盛を極めたロッティカホテルも榴弾で古い廃墟のようになっていた。ホテルのユダヤ人たち、かつて美貌と才覚でホテルを切り回していたロッティカ (ロッテ) をはじめ、名目上の支配人である年老いたツァーラーとその妻で病身の泣いてばかりいるデボラ―、恐怖のあまり変になってしまった娘のミンナ (ミナ)、体と頭に障害を持つその息子らは、いくつかの荷物を載せた手押し車を押して橋を渡った。もはや、彼らの姿は、その昔、先祖が世界中の街道をさ迷った様と同じだった。
パヴレ・ランコヴィッチの監禁
商人のパヴレ・ランコヴィッチは、第一次大戦が始まった翌日、数人のセルビア系の有力者と共に広場の下手のバラックに監禁された。橋を破壊するものがないようにと生命を担保にされたのである。橋に対する破壊行為のどのような兆候があっても彼らを射殺するように命令が下されていた。橋に爆薬が仕掛けられたことは前から知っていた。それに榴弾が当たれば爆発を誘発しないともかぎらなかった。
彼は14歳の時、旧トルコ領からこの地にやって来て、食事と年に一着の着物と二足のオパンケ (サンダル) をあてがわれる丁稚として奉公を始めた。足も伸ばせない小部屋で眠り、正式の社員となり、暖房も灯火も節約を重ねて、やがて結婚し、自分の店を持てるようになった。オーストリア占領軍が来て商売は活気づいた。新時代を掴み、順応し、対処しようと全力を尽くし、副市長にもなり、セルビアの銀行の株主総代、地方銀行の監督委員会のメンバーともなった。15年もの間、他人の髪一本損なわないようにと働いてきた。その結果がこれだった。いやしい盗賊のように兵士に挟まれて椅子に縛り付けられている。自分は本当に生きてきたのだろうかという疑問が頭をもたげた。ただ、働き、貯め、気をもんだだけではなかったのか。人間が理性をあざ笑い、教会が人々を閉め出し、政府が剝き出しの暴力に変る時代が来たのである。
事件の四日目か五日目の朝、新しい部隊、弾薬や食料、装備を運ぶ馬や車が橋をひっきりなしに通過するようになる。その橋と橋の傍の兵営に向けてセルビア側の榴散弾の砲撃が加えられるようになった。オーストリア軍の野砲隊がそれに応戦した。今度はべつの方角から二基の榴弾砲からの榴弾が飛んできて、近くのロッティカホテルや将校クラブにも損害を与えた。すぐに兵営は燃え上がった。砲撃は10日続いたが、榴弾は橋脚にあたって丸い穴を開け、榴散弾は平らな固い石に当たってもほとんど見えないほどの傷を与えただけだった。
回教徒にとっては、どちらの側についても碌なことにならないことは目に見えていた。キリスト教徒同士の戦いだったからだ。中にはかつて、セルビアの地から逃れてきた回教徒もいたのである。広場は、あらゆる種類の兵種や予備役兵、馬車などでごった返し、憲兵が縛られた農民や市民を引っ立てていった。国境の村の二人の農夫と請負師のヴァーヨという男が橋の真正面の広場に連れてこられた。絞首架が建てられている。ヴァーヨは片言のドイツ語で無実を訴えた。罪状は、セルビア国境の先に灯火信号を送っていたという。ハンガリーの予備中尉は軍法会議で死刑宣告を受けた三人にその判決を読み上げていた。セルビア人にとってオーストリアの軛から解放されるために流したのは我々の血だという思いは消えなかっただろう。
オスマン帝国時代とキャラヴァン・サライ
話はオスマン帝国時代の17世紀末に遡る。ハンガリーの地を百年近く占領していたトルコ軍の撤退の噂がボスニアでささやかれ始めた。1683年に第二次ウィーン包囲を開始したトルコ軍はポーランドの参戦により大敗し、東欧での覇権をオーストリアに譲ることになる。ドリナの橋の傍には無料で泊まれるハン (宿舎) としてキャラヴァン・サライが二世紀もの間存続していたが、そのこととハンガリーからのトルコ軍の撤退が関係しようとはヴィシェグラードの住人には思いもよらなかった。ハンガリーを失うことによって、無料で泊まれていたハンの維持費は打ち切られた。しかし、管理人のダウツホジャ・ムテヴェリチはハンを救うために自分の財産をつぎ込み、あらゆる手を尽くした。この賢明で、敬虔で強情な男はどんな事態になっても諦めることがなかった。それ故、後々まで町の人々の記憶に残ったのである。ダウツホジャの死後、ハンは急速にさびれていった。
このハンとちょうど同時にソコルル・メフメト・パシャ橋は建てられた。管理も維持費もいらない橋の方は度重なる大洪水によく耐えた。春と秋に大水が出たが20~30年に一度大水害が襲った。そのような洪水は人々の記憶に残り、長老たちの語り草となった。とりわけ18世紀末の大洪水はドリナ川とルザヴ川が町の上で一本になるという激しいものだった。泥水は橋のアーチや手すりさえも超えてカピアの高くなった部分だけを残して流れ続けたのである。

ヴィシェグラードのモスク 2007
自然の力による共通の不幸はトルコ領に住む非回教徒であるラーヤーとトルコ人とを結び付けた。ミハイロ司教は、初代のヨヴァン司祭の祈りは神に聞いてもらえないから、願い事とは反対のことを唱えればいいと町の者から冷やかされたとか、回教僧のムラ・イスメットは洪水除けの祈祷は、安全な岡の上の坊さんより危険な下町の坊さんにさせろ、その坊さんは心半分しか祈ってないぞと言ったジプシーの話をするのだった。水が引くと町中が片付けと修復に取り掛かった。人々は、この橋が自分の人生において、どんな自然の力にも譲歩しない測り知れない土台の力と極めがたい調和の力によってどんな試練にも無傷で耐え抜く存在のあることを知ったのである。
ソコルル・メフメト・パシャ橋の工事
1571年、大宰相ソコルル・メフメト・パシャが橋の工事総監督に命じたアビダガがヴィシェグラードに赴任してきた。彼は、無慈悲でおそろしく厳格な、みさかいもない人間だと評判の人物だった。歌にもなった長い緑色の杖を持ち、病気かと思うような赤ら顔に緑色の眼をし、イスタンブール風の衣装にハンガリー風の奇妙に捻じれた口ひげを生やしている。怠けたり規定通り働かない者は、この杖で指され、警吏が直ちに鞭打ち、血みどろになり卒倒した者に水をぶっ掛けて配置に戻した。この町とその周辺の者には、いつ終わるともしれない災難が降りかかったと言ってよかった。森が切り開かれ夥しい木材がドリナの両岸に積み上げられた。土を掘り立杭を打つ作業が賦役として続いた。
冬には工事が中断されるが、次の春には岸辺から大量の石が切り出され、てっきり木の橋が出来るものと思っていた賦役の者を驚かせた。小屋の一大集落が建ち、新しい道や水路が出来上がり、選ばれた人夫たちが春の緑色の川の水に浸かって太杭を打ち込み水路を変えるために粘土を詰めた籠を並べていった。工事は3年目に入ったが、賃金は払われたり払われなかったりで、食料のパンは乏しく人々は疲れ果てていた。いつ終わるとも知れない賦役にトルコ人たちは動揺し始め、周辺からはキリスト教徒たちがニワトリのように捕まえられ強制的に集められた。

現在のドリナの橋とアンドリッチ・グラード
アンドリッチ記念施設(博物館・文化施設)
賦役農夫の中にラディサダという男がいた。彼の村は40年前にトルコ領になっている。周囲の者に不満をぶちまけて、工事を中断させよう、夜になったら橋を破壊して妖精が工事を嫌っているという噂を流そうとけしかけた。夜の間に堰や石垣に被害が出るようになる。不穏な空気が満ちるとあらぬ噂が立ち始めた。橋を壊す妖精がアビダガの夢枕に立ち、橋脚にストーヤ (止まれ)、オストーヤ (留まれ) という名の双子を人柱にすれば壊すのをやめるのだと言いふらす者が現れた。ヴィシェグラードの上手の村に住む言葉のない障害のある娘が父親の分からない双子を生んだが死産だった。娘は子供が死んだのを信じなかった。しつこく何処に行ったと聞かれたためにトルコ人の橋のある街にやったと言い訳がされた。それで、その娘は工事現場に現れては子供の居所を執拗にたずね歩いた。料理人は余った粥を与え、アビダガでさえ彼女に食事を出してやれと命じた。こうして橋脚に子供が人柱として塗りこめられたという噂が語り継がれていった。
ラディサダはとうとう捕らえられた。股から肩にかけて棒杭で貫かれ、刑場にその棒ごと突き立てられたのである。セルビアの女たちは妖精が彼の骸をブツコヴォの岩の上に葬り、夜な夜な強い光がその上に降ると語り合うのだった。翌年の春、アビダガに代わるアリフ・ベイという新しい工事総監督がやってきた。アビダガの周囲にいた誰かが彼の行状を大宰相に報告したのである。アビダガは着服した金を全て弁償させられた上、残りの財産とハーレムを携えて田舎に蟄居の身となった。アリフ・ベイは仕事に情熱を持ち、健康で正直な人物だった。人夫は皆賃金を貰い、粉と塩の配給を受けるようになり、工事ははかどった。その工事は5年目に入った。そしてとうとう11個のアーチに乗った目も奪うばかりの美しさに輝く石橋が完成したのである。
付 大宰相の死

右 ソコルル・メフメト・パシャ (1506-1579)
左 フェリドゥン・アーメド・ベイ
ソコルル・メフメト・パシャは、サルタンの宮殿で盾持ちから軍の大提督にまで上り詰めた。スレイマン1世のもとで大宰相になり、その後、無能といわれたセリム2世やムラト3世に仕えた人物である。世界にその名声をうたわれた軍人であり政治家だった。想像もつかないほどの権力と栄光の高みに登ったのである。しかし、子供の頃故郷からさらわれ、途中遭遇した渡し場の険しい岸と不気味な流れが、齢を重ねるごとに後味の悪さを思い出させた。
彼は、故郷ボスニアとイスタンブールを結ぶべく自分の出費で橋を架けることを決定したのである。橋が完成した翌年、彼はカスピ海進出を狙ってサファヴィー朝ペルシアに侵攻を開始する。しかし、1579年修行僧 (ダルヴィーシュ) に扮したペルシア人に面会を求められた時、彼の体はその男の黒い刃で刺され、暗殺されたのである。

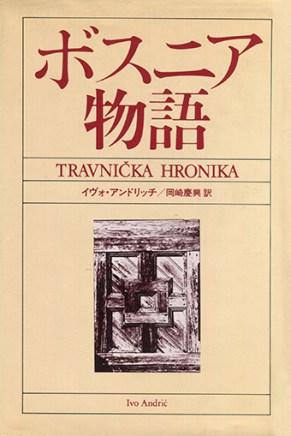
イヴォ・アンドリッチ『ボスニア物語』
『ドリナの橋』、『お嬢さん』と並ぶアンドリッチの代表作。アンドリッチは外交官としてパリに滞在中、ボスニアのトラヴニクにフランス領事として赴任したピエール・ダヴィッドの資料を精査し、ダビーユと言う名の主人公として1806年の領事館開設からナポレオンのロシアでの敗戦とその後の零落によって領事館が閉鎖される1814年までの8年間を描く小説とした。遅れて開設されたオーストリア領事館のフォン・ミッテルエルとの確執、イスタンブールの権力争いに翻弄されるトルコ太守たちとの付かず離れずの微妙な関係、領事夫人たちの対照的な振る舞い、副領事たち、市井の人々。それぞれの人間模様が多彩に彩られる。
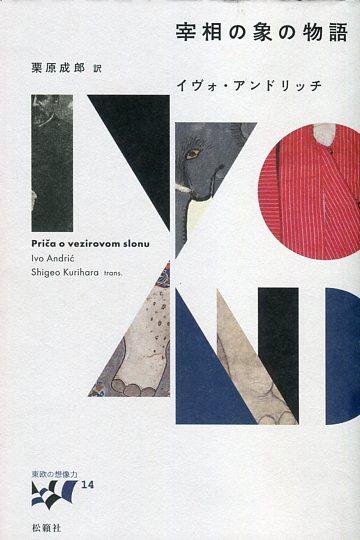
イヴォ・アンドリッチ『宰相の象の物語』
「宰相の象の物語」「シナンの僧院に死す」「絨毯」「アニカの時代」収載
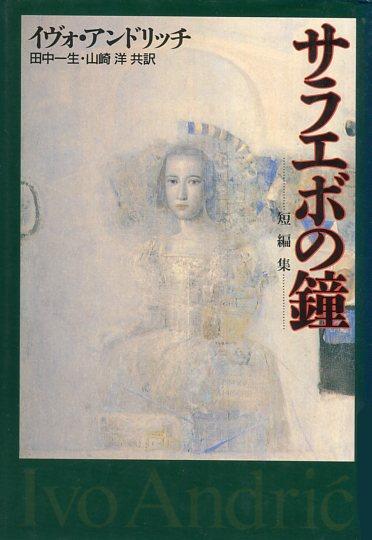
イヴォ・アンドリッチ短編集『サラエボの鐘』
Ⅰ 散文詩
エクスト・ポント(黒海より)
不安
Ⅱ 初期短編
アリヤ・ジャルゼレズの旅
蛇
サラエボの鐘 ― 一九二〇年の手紙
石の上の女
ジェパの橋
Ⅲ 随想
橋
スペインの現実
作家としてのニェゴシュ
書物と文学の世界への第一歩
収載
同じ中学に通った友人マックス・レーベドルフと何十年後かに出会った主人公はボスニアを永遠に離れるという言葉に驚く。後にその理由を手紙に知らされた。ボスニア人は疑いなく他の南スラヴ地域に住む同胞にはめったに見られない多くの道徳的価値を秘めている。信頼、強固な人格、優しさと激しい愛、深遠な感情、忠節、不動の献身がある。しかし、ボスニアは恐怖と憎悪の土地である。サラエボでは夜中、カトリック教会の鐘が二時を告げる時、75秒後に正教会の鐘が鳴り、それに少し遅れてモスクの時計塔が不思議な計算によるトルコの十一時を打ち、遠い声で時を告げる。ユダヤ人は打ち鳴らすべき時計を持たないけれどスペイン系ユダヤ人のセファルディム式の時刻と東欧系ユダヤ人のアシュケナジウム式の時刻は異なっている。それらが眠る人々に差異をもたらす。反目しあう暦にしたがって生活し、四つの異なる教会用語で祈りを天に送る。このような差異は公然とあるいは隠然と憎悪と同化する。これがボスニアの根深い疾患なのだという。憎む能力のない者、意識的に憎もうとしない者は、いつも余所者、変わり者と見なされしばしば殉教者となる。特に移住してきた者にはそうなのだ。それで自分はボスニアを永遠に離れるのだと書いていた。
(サラエボの鐘 ― 一九二〇年の手紙)
このボスニアにおける道徳的特質と憎悪こそがアンドリッチの小説のテーマだと思われる。

イヴォ・アンドリッチ『ゴヤとの対話』
マドリードでの外交官時代にプラドでの大規模なゴヤ展を契機に書かれた『ゴヤ』及び、あるカフェでの老紳士ゴヤとの架空の対話を描いた『ゴヤとの対話』が収載されている。





コメント